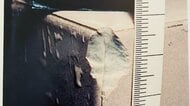国松長官の“負い目”
「目立たないように警備して欲しい」という要望は警備する側にとって、これ以上に難しいオーダーはないという。
警備は通常、充分な人数の警察官を目立つように配置し手厚く警備していることをテロリストに見せるものだ。テロを敢行しようとするテロリストに、手出しができないと思わせることが大事だからだ。
国松長官の難しいオーダーを受けた井上警視総監は、警視庁第六機動隊長をはじめ、警視庁警備第一課長、警察庁警備課長、警視庁警備部長を歴任してきた警備実施のプロだ。そのプロ意識がゆえに難しいオーダーに何とか応えようとした。
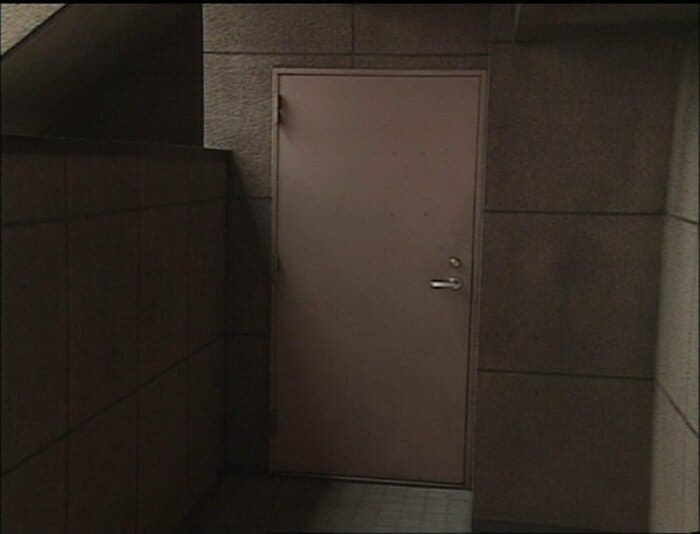
だからこそ長官宅を受け持つ南千住署の佐藤警備課長は、しばしば私服で、それこそ目立たないようにEポートの通用口前に日参し、朝の見送りをしていた。目立たないようにする警備のため、所轄署警備課長自ら長官身辺警護の最前線に立たなければいけない緊張感が現場にあったと言える。
それが、あの日の朝だけ佐藤警備課長は署長に呼ばれて長官宅前を留守にした。その矢先に事件がおきたのである。

地下鉄サリン事件の直後だ。警察のトップが銃撃されたことで未曽有の社会不安が生まれ、自分の持ち場でそれを許した佐藤警備課長はもちろん井上総監も「警察は何をやっているのか」とのバッシングを浴びたに違いない。
自分が「目立たないようやって欲しい」と言ったために井上総監率いる警視庁に迷惑をかけた。国松長官はこの思いにかられたのではないか。

当時警察庁のある幹部は、長官事件発生を許したことについて責任者を処分するよう再三にわたって国松長官に具申したという。しかし国松長官が関係者を処分することはなかった。
自ら「警備を目立たないようにやって欲しい」とオーダーしたことで、内外から責められている井上総監率いる警視庁に申し訳ないという思いを国松長官自身が強く持っていたからではなかろうか。
こうした負い目が井上総監への遠慮や配慮を生み、井上総監のX案件での独断専行を許す雰囲気を生んだと指摘する声もある。
警察庁人事にも影響か
国松長官の配慮が人事にも表れたとされる場面もあった。
まだXの存在が暴露される3カ月前の96年8月、警察庁ナンバー3の菅沼清高官房長の勇退が発表されたのだ。官房長は組織の中核である人事・会計・総務の官房3課を束ねる大官房制のトップであり、菅沼官房長は井上総監の後継として警視総監に就任するのではないかとみられていた。
菅沼官房長の後任である前田健治氏も、その後任の野田健氏、さらに後任の石川重明氏も警察庁官房長から警視総監に3代連続で就任している事実を見ても、官房長を最後に退官させられる人事がどれだけ異例か表れている。
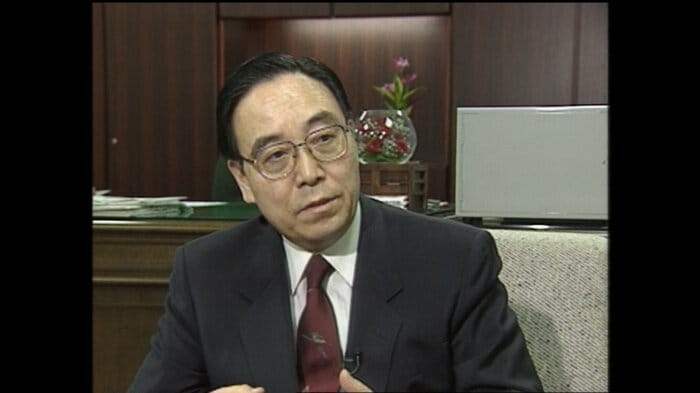
一説によれば、井上総監が自分の後任に菅沼官房長は好ましくないと判断し、国松長官がその意向を汲むかたちで断行した人事だったというのだ。
菅沼官房長は、井上総監が務めた千葉県警本部長も、その次のポストであった警視庁警備部長も井上総監の後任を務めた。前任後任としての接点が多かったはずだが、2人は肝胆相照らす仲ではなかったようだ。また菅沼官房長を大森内閣情報調査室長の後任にという案もあったそうだが、官邸側の意向とマッチしなかったという話もある。
人事についても国松長官は前任の城内長官と考え方が違っていた。城内長官は警備公安畑を歩み、同じ畑の後輩を重用してきたと言われている。当時の菅沼官房長、杉田和博警備局長、桜井勝警視庁公安部長は言わずと知れた警備公安畑であり“城内派”と目されてきた。国松長官は公安部門での経験も豊富だったが、刑事局長から次長、長官に進んだ経験からか城内前長官によるそれまでの“城内派重用“の情実人事に疑問を持っていた可能性は捨てきれない。
菅沼官房長退官人事は、特に“城内派”にとっては衝撃的だった。
Xの存在が暴露された際にも特筆すべき国松人事が行われる。