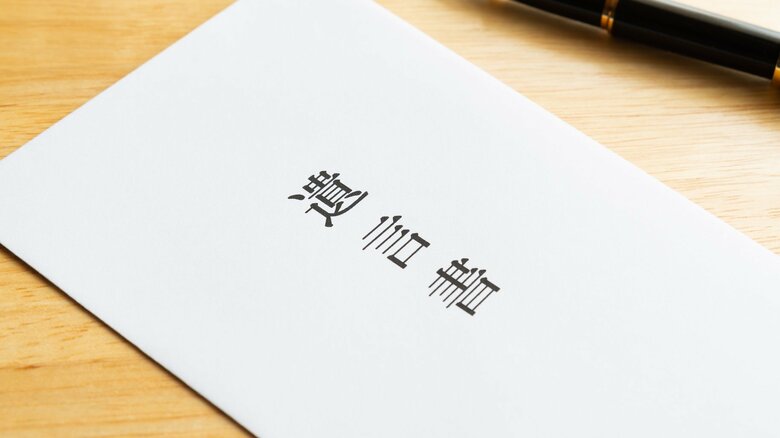(1)相続に関すること
・相続人の廃除または廃除の取り消し
・遺産分割方法や相続分の指定
・遺産分割の一定期間禁止
・相続人間の担保責任の指定など
(2)身分に関すること
・未成年後見人または未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定もしくは指定の委託
・子どもの認知
・祭祀承認者の指定など
(3)財産処分に関すること
・相続人以外への財産の遺贈
・信託の設定
・一般財団法人の設立
・生命保険の受取人を指定
・寄付行為
・遺贈が無効となった場合の財産の帰属など
法的に効力はないが伝えておきたい意思
遺言書には「葬儀は身内だけで」「兄弟は仲よく」といった内容を「付言事項」等で記すこともできます。法的な効力はありませんが、相続を円満に進めるうえでこういった遺言者の意思が役立つことも多々あります。

【遺言書が法的な効力を持つ3つの項目】
被相続人=遺言者の遺言は、法的に効力を持たせられるものが決まっています。
おもな分類として遺産の分割に関する意思を伝える「相続」、相続人とそこに関わる人を指定する「身分」、財産の使い道について伝える「財産処分」の3つがあり、相続人の廃除、遺産分割方法の指定、未成年後見人の指定とった内容は遺言書の中に記載することで効力を発揮します。
遺言書は誰に相続させるかを決める中で法定相続人の状況を把握する効果もあります。認知している子どもや行方不明となっている相続人がいる、援助が必要で財産を多めに分配したい相続人がいるといった意思を明確にし、円満な相続を目指しましょう。
また、寄付や財団法人の設立なども遺言書で明言すれば、進められるケースがあります。
残しておいたほうがよいおもなケース
【さまざまな事情により遺言書を残す場合も】
遺言書は財産の分配がおもな目的として作成されます。
家族間でトラブルを抱えている場合や、そもそも相続人がいない場合などは、自分の財産の行方を明確にさせるために遺言書を残したほうがよいでしょう。