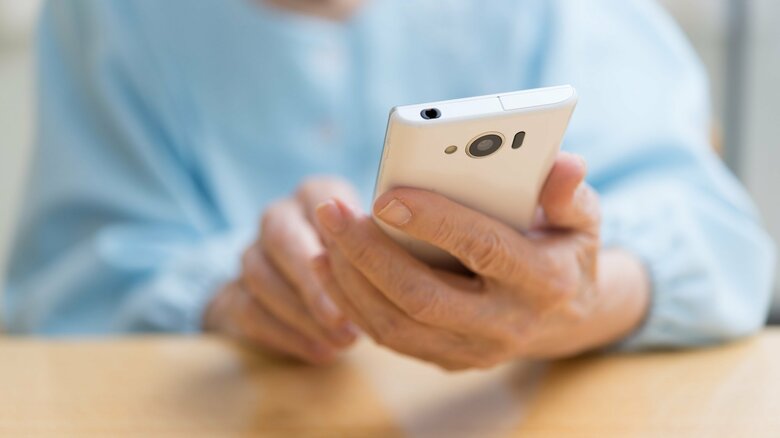近年、「デジタル遺品」という新たな遺品の分野が生まれている。
スマートフォン、ネット銀行、ネット証券、パソコンなど、さまざまなものがあるが、相続トラブルにもつながりやすいという。
相続に関する手続きに詳しい曽根恵子さん監修の『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』(扶桑社)から一部抜粋・再編集して紹介する。
デジタル遺品は相続の対象になる?
パソコンやスマートフォンの普及が進むにつれ、デジタル機器にデータを保存する人が増えてきました。故人がこのように保存していたデータを「デジタル遺品」といいます。
デジタル遺品には、写真や書類のデータ、ネット銀行やネット証券などの金融口座、電子マネーやキャッシュレス決済サービスの残高のほか、インターネット上にあるSNSのアカウントなども含まれます。

また、デジタル遺品はパソコンやスマートフォン以外にも、タブレットやUSBメモリ、外づけハードディスク、マイクロSDカード、CD-ROM、クラウド上などにも保存されているかもしれないため、これらについても探す必要があります。
遺族にとって、デジタル遺品が相続の対象になるかどうかが問題となるわけですが、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器は相続財産に含まれるものの、保存されているデータには形がないため、原則として相続財産には含まれません。
ただし、金融口座や電子マネーの残高、仮想通貨などのデジタル資産は当然ながら相続財産になります。