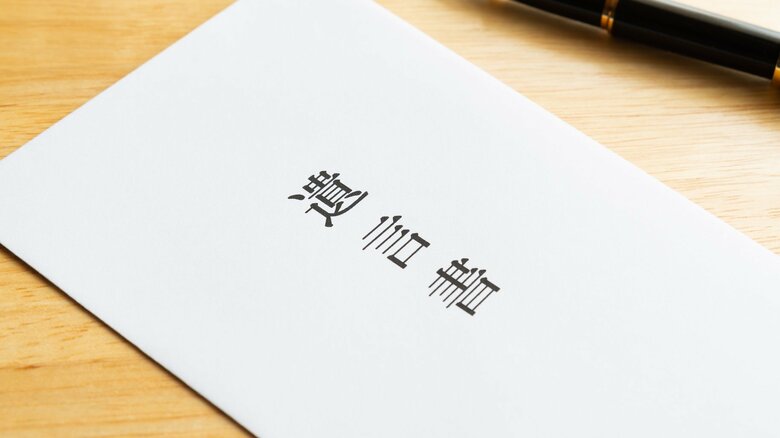自らの死後を考えたとき、遺言書を残したいと思う人もいるだろう。
遺言書は、残すことで特定の相手に相続させたいなど、遺言者の意思に基づいた遺産分割ができるようになるという。
では、どのような内容が遺言として認められるのだろうか。
相続に関する手続きに詳しい、曽根恵子さんが監修した『一番わかりやすい!【図解】相続・贈与のすべてがわかる本』(扶桑社)から、一部抜粋・再編集して紹介する。
遺言できる内容を知ろう
【余計な争いを避けるために配慮のある遺言書を】
財産があり、相続人が複数いる場合、それぞれが権利を主張し合えば、揉め事や争いの原因になりかねません。遺言制度は、被相続人の死後、そうした争いが起こらないようにするために、生前から相続の方法を明確に決めておける制度です。

相続は相続人同士の関係が良好であっても財産の分割で揉め事が起きるなど、一筋縄ではいかないケースが多々あります。また、家庭事情が複雑であれば利害関係で争うなど、なおさら深刻な事態に陥ることもあります。
揉め事を回避し、スムーズに相続を行うために作成される遺言書ですが、書き方に不備があったり、あいまいな表現があると手続きができないこともあります。
よって、そのようなことにならないよう専門家に相談しながら作成することが望ましいでしょう。相続で揉め事になるのは故人の意思が見えず、相続人が自己主張をすることが要因です。余計な争いを回避するためにも配慮のある遺言書を作成しましょう。
遺言すると効力を発揮する内容
【遺言できる内容には決まりがある】
被相続人=遺言者が遺言書で残せる意思表示は、
(1)相続に関すること
(2)身分に関すること
(3)財産処分に関すること
に集約されます。なお、これらの意思表示の効力が及ぶ範囲はある程度決められています。