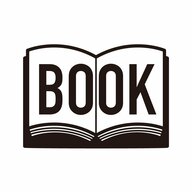御鋳立方には、藩士のみならず、刀鍛冶、鋳物師、算術家、藩外の学者など、身分にかかわらず有能な人物が集められた。
技術力を見込まれ“武士”になる
直正はさらなる軍事力の強化をはかるため、新たな技術者集団「精煉方(せいれんかた)」(理化学研究所)を組織することに決め、リーダーの佐野常民(つねたみ)に人材を集めさせた。
佐野は時習館で学んでいたこともあり、久重のずば抜けた技術力を見て藩に推挙した。すると直正は、職人出身の久重を、士分待遇をもって迎え入れる約束をしたのである。破格の厚遇だった。
誘いを受けた久重は、京都の店をたたんで佐賀へ行くことに同意した。自分への好待遇もあったろうが、やはり、佐賀という大藩の潤沢な資金を使い、個人ではできない発明やものづくりができると考えたのだろう。
久重は、妻の与志、娘の美津とその婿で門弟の岩吉(重儀)らを同伴した。岩吉は久重の甥(姉・げんの子)にあたるが、誠実な人柄だったので、二代目儀右衛門を襲名させていた。
このほか、田中精助ら数人の弟子たちも佐賀へ伴った。こうして54歳のとき、カラクリ儀右衛門こと田中久重の第2の人生がスタートしたのである。
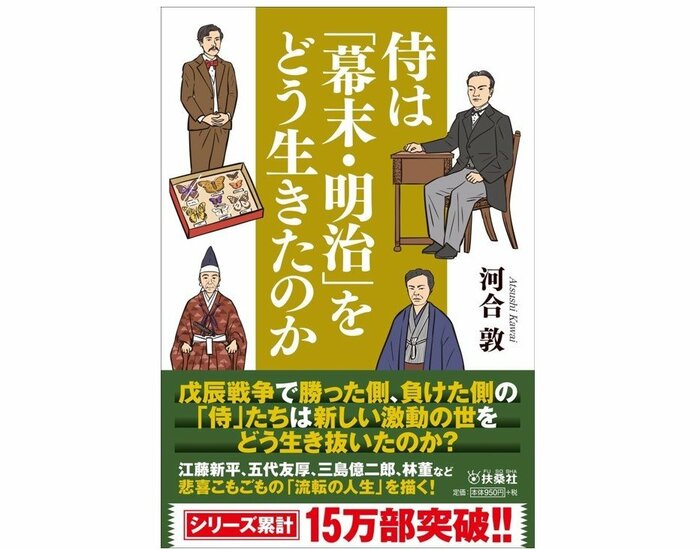
河合敦
歴史作家、多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。『殿様は「明治」をどう生きたのか』シリーズ、『逆転した日本史』(扶桑社)、『戦国武将臨終図巻 生き様死に様プロファイル』(徳間書店)、『1話3分7日でシン常識人 オモシロ日本史』(JTBパブリッシング)など著書多数。初の小説『窮鼠の一矢』(新泉社)を2017年に上梓。