新米の販売が本格化する中、JA福井県の新米販売量が昨年同時期と比較して約半分にとどまっていることが明らかになった。卸売業者が2024年産米の在庫を抱え、新米の仕入れに慎重な姿勢を見せていることが背景にあるとみられる。
販売量がコメ不足だった2024年同時期の半分に
JA福井県の関係者によると、9月22日時点での新米販売量は玄米ベースで約2200トンとなっている。これはコメ不足が話題となり需要が急増した去年の同時期と比較すると約半分の水準だ。コメ騒動が起きる前の2023年(令和5年)と比較しても約90%の販売量にとどまっている。
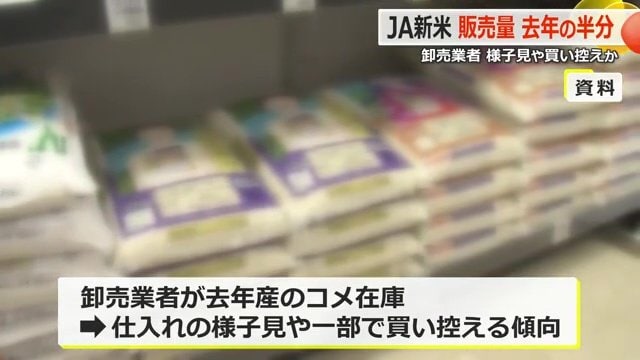
卸売業者が2024年産のコメの在庫を抱えていて、新米の仕入れを様子見したり一部で買い控えたりする傾向がみられるという。政府備蓄米の放出も影響しているとみられる。
この状況について、JA福井県の関係者は「好ましい状況ではない。様子を見ながら卸売り業者に合わせて対応したい」と懸念を示している。
卸売業者の慎重姿勢が影響か
販売量減少の主な要因としては、卸売業者が2024年産のコメの在庫を抱えているため、新米の仕入れを様子見したり、一部では買い控えたりすることが考えられるという。

また、政府備蓄米の放出も市場に影響を与えているとみられる。こうした状況は今後の米価格にも影響を与える可能性がある。
猛暑と少雨で一等米比率が低下
販売量の減少に加え、品質面での課題も浮き彫りになっている。JA福井県は9月25日の会見で、今夏の猛暑や少雨の影響により県産新米の一等米比率が低下していることを発表した。

9月13日時点での一等米比率は、「ハナエチゼン」が去年の同時期より2.2ポイント下がって89.3%、高温に弱いとされる「コシヒカリ」については6.5ポイント下がって87.0%となっている。
一方で、収量については「前年並み」を見込んでいるとしている。
米市場の需給バランスに変化
2024年夏から続くコメ不足に端を発した政府備蓄米の放出、卸売業者の在庫調整など、米市場の需給バランスに変化が生じている。

今後、新米の販売がどのように推移していくのか、また米価格にどのような影響を与えるのか注目される。






