苦難の末、日本銀行本店の設計という大きなチャンスをつかみ、さらに、東京駅の設計を任された。
辰野は、常々、日本銀行本店、東京駅、国会議事堂という国を代表する大建築を設計したい、と語っていたが、ついに東京駅の設計を手にした。
建築家という職業がまだ理解されていなかった当時は民間にいて大きな仕事をとるのは至難の業であったから、この時、辰野は所員の前で万歳を三唱して喜びを表した。
紆余曲折あった東京駅の設計
しかし、設計は何度も計画の変更があり、苦難の連続で、竣工まで11年もかかった。
その当時、東海道本線は新橋まで、東北本線は上野までだった。それを繋げば便利になるから、その中心に中央停車場を作る。皇居前、丸の内の真ん中に駅を設けるという、今考えれば当たり前のことだが、この決定までに紆余曲折があった。

335メートルもある長い建築の中心に皇室のための出入口を作り、左右に一般市民のための出入口(南側に入口、北側に出口)を作ると決められた。ずいぶん不便な計画だが、戦後まで、これが続いた。
設計に着手してから、いよいよ本格的に検討する段階になって、またも重大な問題が浮上した。設計の担当者は、当時普及し始めていた鉄筋コンクリート造を考えていた。しかし、辰野はどうしても納得できない。長年使い慣れた赤レンガでやりたい。ドロドロのコンクリートが固まるといわれてもしっくりこないのだ。
辰野は最後まで譲らず、やはりレンガ造と決まった。当時のレンガ造は、中にしっかりとした鉄骨が組み込まれており、鉄骨レンガ造というべきもので非常に強固であった。
竣工の9年後に関東大震災が起こり、東京駅の目の前で完成したばかりの丸ビルなどのビルに大きな被害があったにもかかわらず、東京駅は被害がなかった。東京市内の多くのレンガ造建築は倒壊し、それ以降、レンガ造は衰退し、鉄筋コンクリート造が主流となってゆく。
このため、東京駅は辰野の赤レンガ建築の最後の大輪の花であり、このあと日本のレンガ造建築は急速に収束に向かう。
辰野は、東京駅の竣工の5年後にスペイン風邪のため64歳で逝去。国会議事堂の設計コンペの審査が始まった時だった。
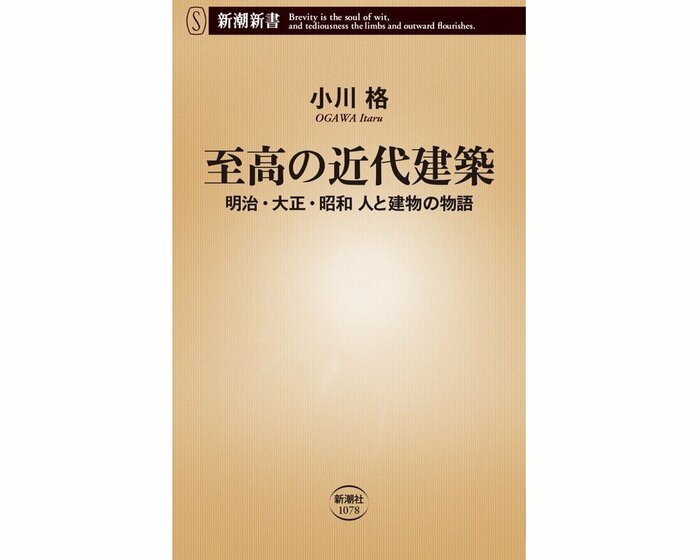
小川格
ブログ「近代建築の楽しみ」で新たな価値を発信。編集事務所「南風舎」顧問。著書に『日本の近代建築ベスト50』(新潮新書)
(写真は著者撮影)






