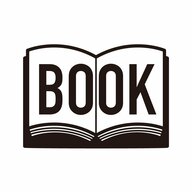天守の周囲を四重に囲み、水都大垣を体現していた堀はすっかり失われており、全体としての景観は永遠に戻らないものの、前進ではある。
内部の見どころも増した岡山城
昭和41年(1966)に竣工した岡山城の外観復元天守は、令和4年(2022)11月に、約1年を費やした改修工事が終わった。外壁をおおう下見板には、艶やかな漆黒の壁面がよみがえり、最上階の壁面にあった華灯窓も、再建時には省略されてしまっていたのが再現された。

また、内部にも見どころができた。空襲で焼失する前は2階に、床の間、違い棚、帳台構がしつらえられた書院造の城主の間があった。
それが鉄筋コンクリート造の内部に木造で再現されたのである。小田原城天守の最上階のように、往時の空間が一部であっても、視覚をとおして確認できるようになったのはうれしい。
とはいえ、石垣を崩してもうけた地階とその開口部は、以前と変わらず天守の入口として使われている。史跡の状況が、破壊をともなって根本的に改変されてしまうと、もとに戻すのはきわめて困難だという例で、教訓にすべきだろう。
改修でもっとも変わった福山城
改修をへて見た目がもっとも変わったのは福山城天守だろう。この城は昭和41年に再建された際は、戦災で焼失する前の姿と大きく変わってしまっていた。
しかし、令和4年8月の築城400年に向け、その2年近く前から耐震補強を兼ねた改修工事が進められた結果、天守は戦前の雄姿に近い外観を取り戻すことになった。

最大の変化は、北側の壁面に鉄板を張り、この天守の最大の特徴をよみがえらせたことだった。
鉄板も天守と一緒に焼失したため、これまで、その形状はもはやわからないと考えられていた。ところが、福山市内にその一部が保存されており、小さな鉄板をすき間なく張り合わせていたことが判明したため、再現することが可能になったのである。
また、北面以外の窓も、これまですべて白く塗られてしまっていたが、窓枠や格子に銅板が巻かれていた戦前の色彩に近づけられた。
最上階の華灯窓も、焼失した天守と同じ位置に移され、真壁の柱もこれまで白かったのが黒く塗られた。廻縁の高欄、つまり手すりも、これまで寺社建築のように赤く塗られていたが、元来の黒っぽい木調になった。
細かな指摘をすれば、いろいろある。
窓枠や格子をおおっているのは、戦前のような銅板ではなくアルミであるし、最上層の真壁には木材は使われず、コンクリートで柱のように造形し、彩色しているだけである。
とはいえ、天守のプロポーションも破風の形状も、昭和41年に再建された当時のままなのに、こうして意匠をあらためただけで、印象がはなはだしく変わることに驚かされる。見た目だけでも元来の姿に近づいたことは、素直によろこぶべきことだろう。
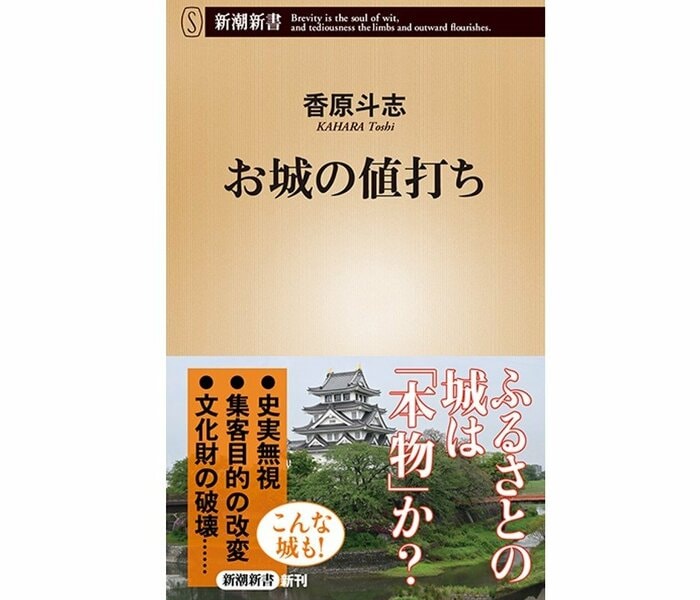
香原斗志
歴史評論家、音楽評論家。日本古代史から近世史まで、幅広く執筆活動を行う。主な著書に『教養としての日本の城』など。