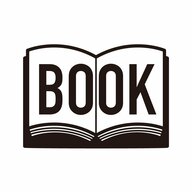ちなみに上野の博物館は明治19年に宮内省に移管され、明治22年には帝国博物館となった。そして戦後、東京国立博物館や上野動物園となっていくのである。
芳男が大切にしたコンセプトは、わかりやすい展示・解説、人々の生活に役に立つ博物館・博覧会であった。芳男の脳裏には、つねに幼い頃に父から教えられた『三字教』(中国の宋の子供用の儒教テキスト)の教えがあったという。
76歳と79歳のとき、芳男は講演の中で次のように話している。
「私は幼年の時に、専ら親から教わって覚えたのは、『三字教』に出ておることである。親から書き抜いて貰って導かれた中に、最も身に染みましたのは、ちょっと読んでみますが、末のほうに『犬は夜を守り、鶏は晨を司る、苟も学ばざれば、なんぞ人とならん。蚕は糸を吐き、蜂は蜜を醸す、人学ばざれば、物にしかず云々』とありまして、これについて親から訓誡を与えられました。
『人たる者は、世の中に生まれ出たからは、自分相応な仕事をし、世用を済さなければならぬ』と懇々と教えられました。それで、自分もこの至極な道理を深く深く感得しまして、これが把柄となって、田中芳男の一生涯の精神となりました」、「私はこれを以て親から導かれて、私の一生の精神となったのであります」、「農商務省におるにも、博覧会の審査官になるにも、伊勢の農業館に従事するにも、矢張りこの精神を失わずにやっておりました」(前掲書)
さて、政府の役人を辞した芳男だが、それからもさまざまな博覧会に関わったり、農林水産関係の多くの団体の役員や幹事となったり、日本の産業の発展に貢献した。
これを感謝する意味で、芳男が76歳の大正2年(1913)、大日本農会、大日本山林会、大日本水産会が主催して「田中芳男君七六展覧会」が開催され、来賓の前で芳男は自分の生涯を語った。
本人もさぞかし嬉しかったことだろう。そして78歳のとき、芳男はこれまでの功績をたたえられ、国家から男爵を授けられ、翌大正5年(1916)に東京本郷の自宅で生涯を閉じたのである。79歳であった。
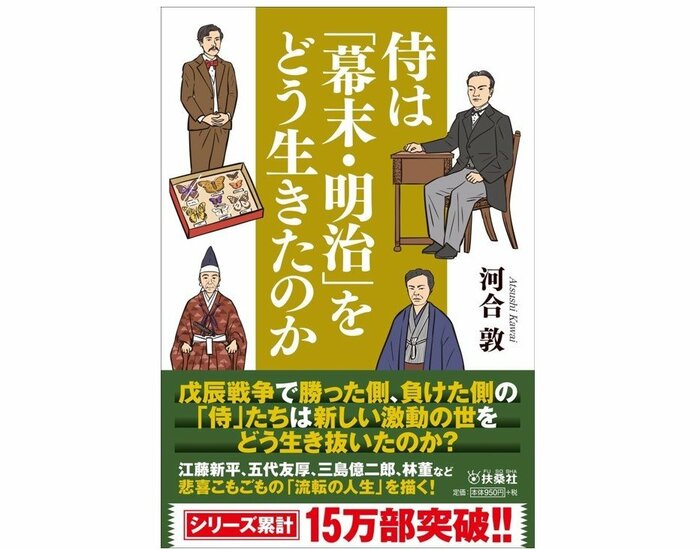
河合敦
歴史作家、多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。『殿様は「明治」をどう生きたのか』シリーズ、『逆転した日本史』(扶桑社)、『戦国武将臨終図巻 生き様死に様プロファイル』(徳間書店)、『1話3分7日でシン常識人 オモシロ日本史』(JTBパブリッシング)など著書多数。初の小説『窮鼠の一矢』(新泉社)を2017年に上梓。