採捕や流通ルールの整備が先決
「完全養殖のウナギに夢を託すのも悪くはありませんが、今は採捕や流通のルール整備を進めるほうが大切です。日本・中国・韓国・台湾の間では、養殖に使うシラスウナギの量について一応ルールらしきものがあるのですが、罰則のない緩やかな努力目標のようなものなので、あまり守られていません。国境をまたいで回遊するウナギを管理していくには、国際的な法的管理を行う組織も必要とされますが、東アジアの政治状況では、その実現は困難でしょう」
まだまだウナギの周りには、解決すべき問題が多く残されているようだが、私たち消費者がウナギを守るためになにかやれることはあるのだろうか?
「まずは、『知る』ことが大切になります。ウナギを食べるかどうかはご自分で判断してほしいのですが、その前にウナギが絶滅危惧種であることや、その裏には密漁や密輸など闇が存在していることなど、ウナギやそのまわりで起こっている事実を知ってほしいのです。そうした知識を多くの消費者がもつことで、何かが少しずつ変わっていくことを期待しています」
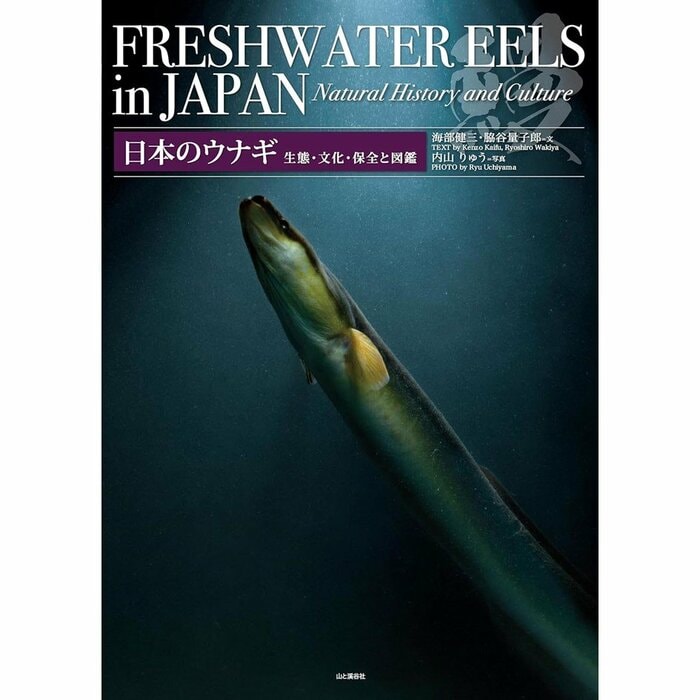
海部健三(かいふ・けんぞう)
中央大学法学部教授。河川や沿岸域におけるウナギの生態研究のほか、ウナギを適切に管理する仕組みづくりに関する研究活動を行う。著書に『結局、ウナギは食べていいのか問題』(岩波書店)など。
取材・文=中村宏覚






