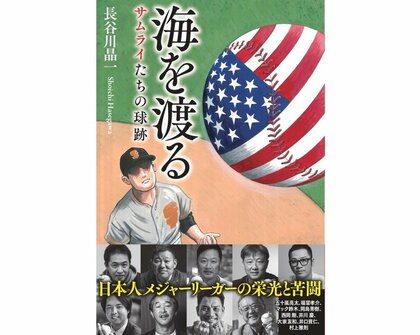「……もしも内容がわからなかったら、首をひねりながら“What you say?”なんて言ってみる。そうするとわかりやすい言葉で置き換えて話してもらえる。
毎日しゃべっていると少しずつ単語も覚えてくる。まずは単語を2つ並べてみる。次に3つ並べてみる。そうすると、だんだん深い内容の会話もできるようになってくる。
文法なんか気にしなくていい。主語や述語なんて意識しなくていい。その気概が大切なんじゃないのかな?」
今もなお残る志半ばで帰国した悔しさ
村上が渡米したのは、第二次世界大戦の終結から20年が経過する頃だった。
日本では、高度経済成長が本格化し、世界で確たる地位を築きつつある頃だ。まだまだ日本人の地位は低かった。1ドル360円という経済格差もあった。

そうした中で、成人する前に単身で海を渡り、独力で生き抜いたのが村上だった。さまざまな不安に押し潰されそうになる中で、彼は自分の左腕で居場所を作り上げた。
アメリカから帰国してしばらくした頃、世話になっている人物に招かれて夕食をともにした。このとき、「何か歌を歌ってくれないか」と頼まれた村上が静かに口ずさむ。
「I left my heart in San Francisco……」
トニー・ベネットが歌って62年に大ヒットした曲である。邦題は『想い出のサンフランシスコ』。歌っているうちに村上の頬を涙が伝う。
海を渡った青年は、アメリカでの手応えをつかんでいた。けれども、志半ばで帰国することになった。実力不足や故障のためではない。「まだまだ自分は成長できる」という手応えを覚えていただけに悔しかった。無念だった。すでに80代を迎えた村上は言う。
「あのときの私には、ああするしかなかった。鶴岡さんを恨んではいません。入団時の約束をきちんと守ってくれたんですから。ただね……」
一拍おいて、村上はつぶやいた。
「……ただ、あのときもしも鶴岡さんが、“よし、わかった。お前が納得するまでアメリカで頑張ってこい!”って言ってくれていたら、私はどんな人生を歩んでいたのかな、そう考えることはしばしばありましたね……」
感情のこもったひと言が静かに響き渡った――。