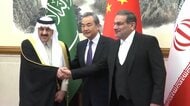テロ関連の容疑者の拘束相次ぐ
シンガポール当局は11月末、建設作業員として2017年にシンガポールにやってきた26歳のバングラデシュ人イスラム教徒の男をテロ容疑で逮捕したと発表した。
内務省によると、男はシンガポール入りした翌年の2018年からインターネット上で「イスラム国」のプロパガンダに触れて過激化、匿名アカウントを使ってそれらを拡散させただけでなく折りたたみ式ナイフを購入し、取り調べに対してそれを攻撃に使うつもりだったと自白している。
またシンガポール当局は、10月にフランスで預言者ムハンマドの風刺画を授業で見せた教師が斬首されたテロ事件に関連し、シンガポール人14人と外国人23人を取り調べ、外国人16人を本国に強制送還したとも発表した。
これらの人々はソーシャルメディア上に教師の斬首をはじめとするフランスで発生したテロを支持する投稿や、フランスやマクロン大統領に対する報復、暴力を扇動する投稿をしていたとされる。

送還された外国人16人のうち1人はマレーシア人で、武装闘争に参加するためイラクかパレスチナに渡航する準備をしていた、残り15人はバングラデシュ人で、ほとんどが建設作業員として働いていたと発表された。
許可なしのデモ・外国の政治問題への介入もNG
シンガポールは、暴力や過激思想については一切容赦しない「ゼロ・トレランス(寛容ゼロ)」の政策で知られている。
当局はここ数カ月間の暴力扇動案件の増加を受けて、外国人労働者はソーシャルメディア上であっても暴力を扇動すれば刑務所に入れられ、罰金を科せられ、シンガポールへの入国が無期限に禁止される可能性がある旨の注意喚起を改めて行った。
シンガポールでは当局の承認なしに抗議デモや集会を開催したり、外国の政治家や組織、運動への支持を公然と表明したりすることも違法行為とされる。日本でも10月30日、在日イスラム教徒がマクロン大統領に対する抗議デモをフランス大使館前近くで行ったが、シンガポールではこのような行為は認められない。
また、外国人労働者に対しては、外国の政治問題をシンガポールに持ち込まないよう強く要請される。外国の問題はその国の法に基づきその国で解決されるべきであり、それに介入してシンガポール国内の安定が損なわれるようなことはあってはならない、という考えだ。
特定の人種、宗教、国籍、団体を侮辱したり、憎悪を煽ったりするような発言や投稿も禁じられる。

シンガポール独自の介入主義
シャンムガム内相兼法相は11月、シンガポールもフランスと同様に信教の自由を保障する世俗国家だが、フランスの不介入主義とは異なり介入主義をとる、人種や宗教の調和を保つためシャルリー・エブドのような風刺画はシンガポールでは許されない、と述べた。
風刺画禁止、どんな相手に対する侮辱やヘイトスピーチも禁止、あらゆる暴力の扇動も禁止など、シンガポールで認められる表現の自由の範囲は日本やフランスと比べると狭い。また、外国人労働者が違法行為を行った場合の処罰も強制送還、再入国禁止など極めて厳しい。

シンガポールには、当局が安全保障上の脅威とみなした人物を逮捕状なしに拘束できる国内治安維持法(ISA)という法もある。かつてアメリカから人権侵害の法だと非難されたこともあるが、シンガポール当局はテロとの戦いと人権保護が常に両立するとは限らないと反論した。冒頭で述べた26歳のバングラデシュ人も最初はISAで拘束され、その後、逮捕に至っている。
これらはいずれも、多くの外国人労働者を受け入れる多民族、多宗教国家であるシンガポールが、多様な人々の調和と安定、治安維持のために必要不可欠な法であり制度である、というのが当局の立場だ。
シンガポール建国の父であるリー・クアンユーは2012年、「私がイスラム原理主義の勝利を目にすることはない。つまり、シンガポールをイスラム原理主義体制にはさせないということだ」と述べた。
多くのイスラム教徒労働者を受け入れつつもシンガポールでイスラム過激派テロが発生していないのは、厳格な法制度と国家の強い統制ゆえだという側面は間違いなくある。
シンガポールと日本は、国土の大きさや人口規模などの前提条件は全く異なるとはいえ、多文化共生社会の先駆者として学ぶべき要素は多い。日本でも外国人労働者が増加する中、自由や人権と治安維持のバランスをどう図るべきかという問題についての議論を、いつまでも先送りするわけにはいくまい。
【執筆:イスラム思想研究者 飯山陽】