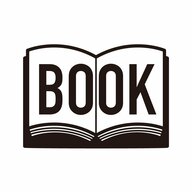圭介は師から譲り受けたツンベルク著『日本植物誌』を独力で翻訳・出版しており、すでに洋学者としてその名を知られていた。若い頃に著した『泰西本草名疏(たいせいほんぞうめいそ)』では、「花粉」、「おしべ」、「めしべ」といった言葉を初めて使用している。
きっと芳男にとって、名古屋の遊学時代は充実した日々であったろう。ただ、いつまでも名古屋にいるわけにはいかず、万延元年(1860)に故郷の飯田へ戻った。
以後は父の家業を手伝いながら、西洋の原書や翻訳書を学びつつ、自作の辞書『音訳彙纂(おんやくいさん)』をつくったり、ガルバニー式越列幾機(電流を用いた医療機器)を製作したり、電気を用いて金銀のメッキをおこなう実験をしたりしていた。大好きな学問や実験はやめられなかったようだ。
そんな田舎暮らしの芳男のもとに、その人生を大きく変える話が舞い込んできた。「一緒に江戸へ行かないか」という誘いが、師の伊藤圭介からかかったのである。文久元年(1861)のことであった。
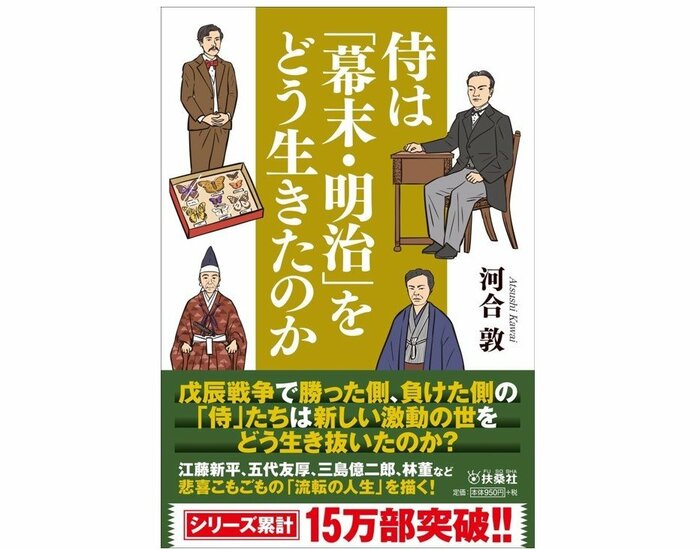
河合敦
歴史作家、多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。『殿様は「明治」をどう生きたのか』シリーズ、『逆転した日本史』(扶桑社)、『戦国武将臨終図巻 生き様死に様プロファイル』(徳間書店)、『1話3分7日でシン常識人 オモシロ日本史』(JTBパブリッシング)など著書多数。初の小説『窮鼠の一矢』(新泉社)を2017年に上梓。