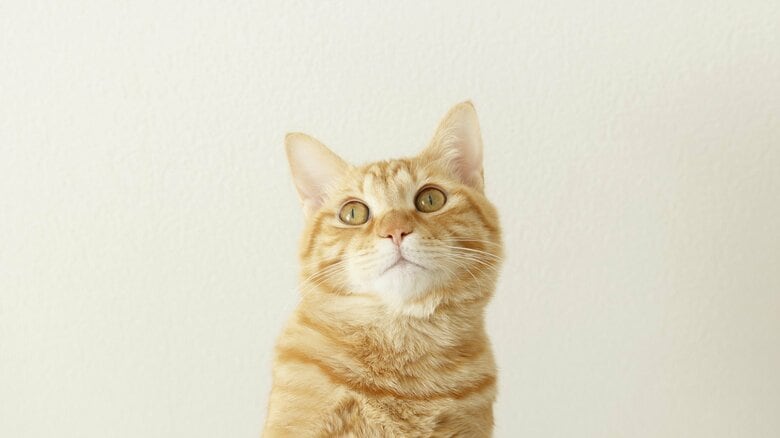首輪だけでは再会できない!
平井さんは、被災時にこそ大切になってくるのが、迷子対策だと言う。
環境省がまとめた『東日本大震災における被災動物対応記録集』(2013年発行)によれば、東日本大震災時の猫の被害状況はほとんどわかっていない。猫は、犬のように自治体に飼育を登録する義務がないためだ。そのような中でも、被災した10自治体で首輪をした猫 39 頭が保護されたが、このうち一頭も飼い主は見つかっていない。これらの猫は、首輪のみで迷子札はなかったという。

そこで『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』では、猫の迷子対策として、日ごろから首輪に慣らしておき、同時に迷子札や、マイクロチップを装着しておくことを勧めている。
マイクロチップは装着とともに、環境省のウェブサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から飼い主情報の登録をすることも忘れてはならない。装着していても登録がされていなかったため、飼い主が判明しなかった事例もあった。また、譲渡で飼い主が変わっている場合は登録情報の変更も忘れずに。
さらに、あらかじめ迷い猫チラシを作っておき、非常用持ち出し袋に猫の健康状態やワクチン履歴などをまとめた健康手帳などと一緒に入れておくと心強いだろう。
被災地で野良猫が急増
健康管理も忘れてはならない。
「たくさんの犬猫が集まる避難所では感染症のリスクも高くなります。ご自分の猫を守るため、平時のうちにワクチン接種をしておきましょう。また、繁殖しないのであれば避妊・去勢もしておいたほうがいいでしょう」
実は現在、2024年元日に発生した能登半島地震の被災地では猫が繁殖し、野良猫が急増しているという。
「結果的に殺処分される猫を増やしてしまうことになってしまいますので、繁殖制限処置も大切だと思います」
感染症予防のワクチン接種、マイクロチップ挿入などの迷子対策、そして、不妊手術など、どれも平時から飼い主が心がけてやっておくべきことではある。そうした飼い主としての自覚や責任感を常日頃から持っていれば、準備も自然とできるもの。それがいざという時に役に立つ。
平井潤子(ひらい・じゅんこ)
人と動物の防災を考える市民ネットワーク、NPO法人アナイス代表。緊急時に飼い主と動物が同行避難し、人と動物がともに調和して避難生活を送ることができるよう、知識と情報の提供を行っている。
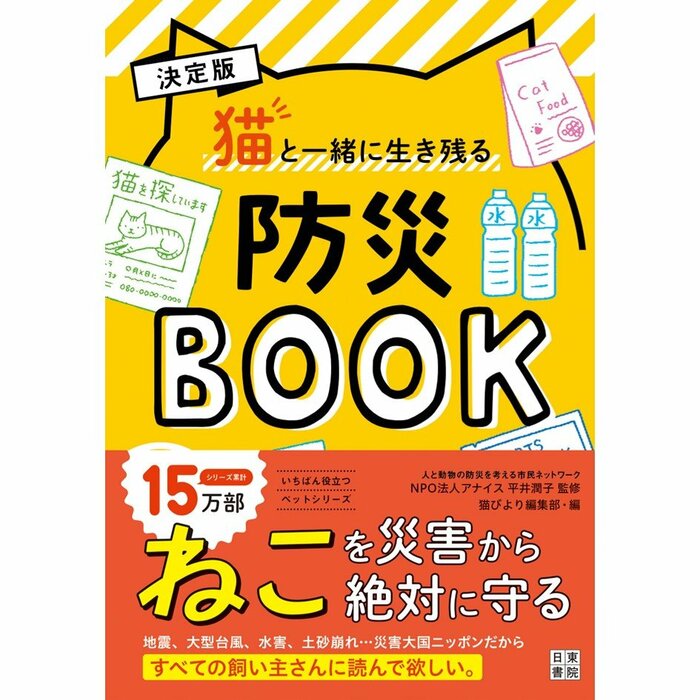
取材・文=青山 誠