政府が近くまとめる経済対策に「おこめ券」の活用を盛り込む方向で調整していることがわかった。新米の流通が進むなか、コメ価格は高値圏で推移している。
9週連続で4000円台
農水省が発表した、10月27日~11月2日に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キログラムあたり4235円だった。2週ぶりに値上がりし、5月中旬に記録した過去最高の4285円に迫る水準となっている。4000円台をつけるのは9週連続だ。
随意契約による政府備蓄米の販売が6月に本格化し、価格はいったんは下落傾向を見せたが、割高な新米の流通が広がるなかで、再び高止まりに転じた。新米を含む銘柄米は、前週に比べ17円高い4540円と、過去最高を3週連続で更新している。
「おこめ券」の活用 440円券×10枚などの例も
「おこめ券」の活用は、高市政権のもとでコメ政策を担うことになった鈴木農水相が意欲を示していたものだ。この「おこめ券」とは、どういうものなのだろうか。
全国米穀販売事業共済協同組合が発行しているのが「全国共通おこめ券」だ。物価高対策としての自治体の取り組みとして、すでに配布が行われているケースがある。
たとえば、兵庫県尼崎市は、この「全国共通おこめ券」を、10月末までに全世帯を対象に発送した。1世帯あたり440円分の券を5枚、2200円分だ。コメ店のほか、スーパー、ドラッグストアなど、券の取り扱い店舗で、コメなどの購入に使用可能だという。
愛知県日進市は、8月下旬ごろから、2025年度に65歳以上になる人がいる世帯を対象に、440円分の券を10枚、4400円分を送付した。
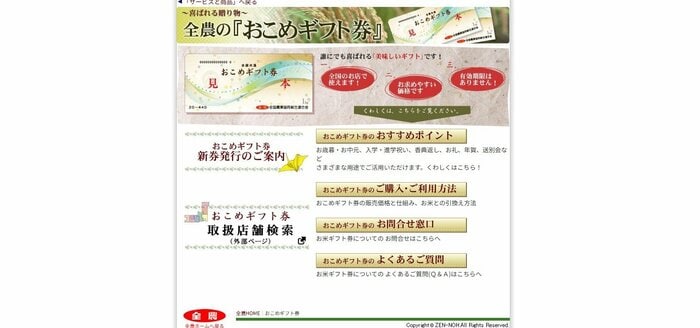
また、JAグループの全国農業協同組合連合会(JA全農)が発行する「おこめギフト券」もある。東京都台東区は独自の生活支援策として、全世帯を対象に、この「おこめギフト券」の配布を10月24日から始めていて、12月上旬にかけて順次発送する。1世帯あたり440円分の券が10枚、4400円分配られ、18歳以下の児童がいる世帯や3人以上の世帯には20枚、8800円分が配布される。
政府は、こうした事例を踏まえ、国が直接おこめ券を配るのではなく、自治体が配布する場合、国がその費用を交付金でサポートするというやり方を念頭に置いている。
自治体が自由に使いみちを決められる「重点支援交付金」を拡充し、各自治体が物価高対策として行う「おこめ券」の配布を、政府が推奨する事業として位置付ける方向だ。




