「出力形式を指定する」「役割を与える」「文体を決める」など、コツを覚えれば誰でもAIの出力精度を向上させられることから、SNSやYouTube、書籍、eラーニングでも多くの学習コンテンツが生まれました。
大手企業が研修に組み込むようになり、大学の講義にも採用され、「成長期」を迎えました。
誰もが使いこなせるようになったが
やがて2024年には、プロンプトの基本スキルは多くのビジネスパーソンが習得するようになります。テンプレートも出回り、誰もがある程度使いこなせる環境が整いました。
こうしてプロンプト初級スキルは成熟期に入り、特別なものではなく、ビジネスリテラシーの一部として扱われるようになったのです。
しかし、そのわずか半年後、状況は再び大きく変わり始めます。GPT-4oやClaude3などの最新モデルが登場し、文脈理解力が飛躍的に向上しました。
ユーザーが曖昧な指示をしても、AIが適切に意図を汲くみ取って出力できるようになったことで、「精密なプロンプトを書く」初級スキルの価値は急激に低下しました。
この時点で、プロンプト初級スキルは「陳腐化」フェーズに入り、注目は「AIの出力をどう評価・統合・判断するか」という応用力やメタスキルへと移ってきているのです。先進的な企業ではすでに、プロンプト研修の必要性を見直し始めたというお話も聞きます。
そして今後数年のうちに、AIが自動でプロンプトを生成し、ユーザーが音声や画像、動作など多様な手段でAIに指示を出す時代が来るという予測もあります。
その頃には、「プロンプトの書き方を学ぶ」という行為そのものが不要になり、初級スキルは完全に「消滅」の段階へと移行するかもしれません。数年前には最先端だったスキルも、時間の経過とともに不要となっていくのです。
このスキルライフサイクルのプロセスが以前とは比較にならないスピードで起きているという事実を理解する必要があるのです。
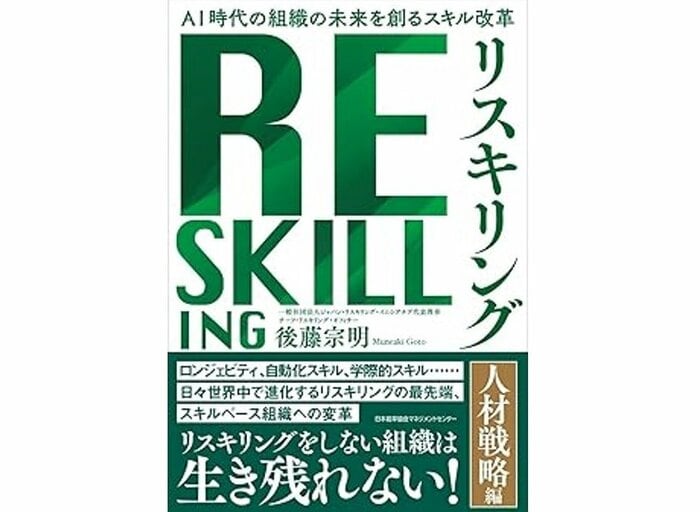
後藤宗明
一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事。SkyHive Technologies 日本代表。著書に『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』『新しいスキルで自分の未来を創る リスキリング【実践編】』(ともに、日本能率協会マネジメントセンター)、『中高年リスキリング』(朝日新聞出版)がある。






