車社会において安全確保のために欠かすことが出来ない信号機の撤去が、いま全国で進んでいるという。一体なぜなのか?
1年間で600超の信号機が撤去
実はいま、全国各地で信号機の撤去が進んでいる。
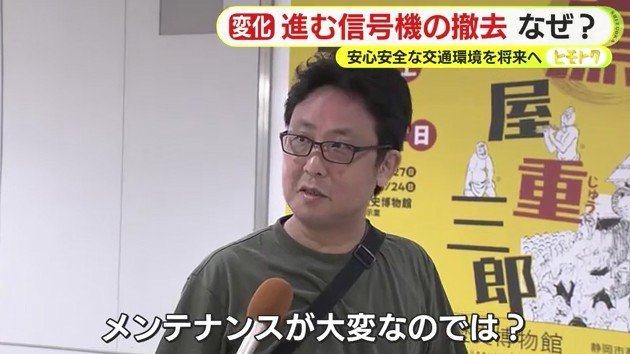
街の人に聞いてみると「歩行者がいれば止まる。そうした風潮が浸透してきたのでは?」「メンテナンスが大変では?」「もう寿命じゃないの?」と様々な答えが返って来た。
交通事故を防ぐために無くてはならないはずの信号機がなぜ減っているのか?

19年と言われる耐用年数を大きく超え、30年近く運用されていた静岡県沼津市内の信号機。
青や赤に光る部分の一部が欠け、その下を見てみるとかなりさび付いているのがわかる。
このように信号機や信号柱の老朽化を主な原因として、全国では2024年度に600を超える信号機が撤去された。
県内では5年間に2基倒壊
県警交通規制課の奥野仁 次席によると、県内には信号柱が約2万6000本あるものの「耐用年数を超えているものが約4割。現在、大量の更新期を迎えていて、老朽化に更新が追い付いていない」という。

信号柱の老朽化が進めば言うまでもなく倒壊のリスクが高まる。
全国では直近5年間で11基が倒壊し、このうち2基は県内に設置された信号機だった。
2024年7月に静岡市で起きた倒壊事故では折れた信号機がトラックの荷台を直撃。

このため、奥野次席は「本来、県民を交通事故から守る信号機などが、県民の生命財産を脅かしかねない状態」と危機感を募らせ「必要性が低下した信号機などを減少させていくことで、持続可能な交通規制を強力に進めている」と説明する。
国道との交差点でも撤去
市道と国道150号が交わる牧之原市の交差点には車両用と歩行者用の信号機が設置されていたが2023年に撤去された。

理由は老朽化だけでなく、牧之原市地頭方区の山下裕彦 区長は「交通量が少ないことと維持費がかかるため」と話す。

信号機を新しくするためにかかる費用は1基あたり数百万円。
更新は各都道府県警の予算で行われる。
ただ、予算には限りがあることから古くなった信号機のすべてを新しくすることは出来ないのが現実だ。
交通の流れがスムーズになる効果も
それ故に、県警では過疎化などを理由に交通量が減っている交差点については信号機を撤去した上で一時停止の標識を設置するなどして対応している。

山下区長は「待ち時間もなく、個人的にもよく使うようになった」と口にし、地区の住民からも信号機が無くなったことによる不満の声はなく、事故も起きていない。
県警によれば不要な信号機を撤去することで、交通の流れがスムーズになる効果も期待されている。

奥野次席は信号機について「一律に全部変えるわけではなく、車や歩行者の道路利用状況、交通情勢をよく分析し慎重に判断して、必要性が低下している信号機であれば廃止する」との方針を示し「目指すべきところは将来の世代に安全安心な交通環境を引き継ぐこと」と話す。
老朽化に伴う思わぬトラブルを未然に防ぐことはもちろん、限られた財源の中で交通事故や渋滞を減らすために各地で信号機の撤去が進められている。
(テレビ静岡)






