その背景には、主に2つの原因が指摘されています(※Ingham et al.(1974))。
1つ目は、モチベーションの低下です。
「他のメンバーが頑張ってるから、もう任せてしまおう。自分ひとりくらい手を抜いても大丈夫だろう」という心理状態になるのです。
しかし、自分ひとりだけがそう考えているわけではありません。他のメンバーも同じくそう考えています。
結果として全員が手を抜いてしまうため、集団全体の生産性が大きく低下します。

特に、集団のサイズが大きいとき、もしくは自分がどれだけ集団に貢献しているのか不明瞭なとき、あるいは全体に対して自分の貢献が小さく感じるときには、モチベーションの低下が起きやすくなります。
大規模なプロジェクトでは、個々の仕事の貢献がまわりからも自分自身からも見えにくいため、メンバーは自分の仕事の重要性を低く見積もり、やる気を失ってしまいがちです。
もう1つは協調の難しさです。いわば連携やチームワークの問題です。

綱引きの例では、集団でタイミングをぴったり合わせる必要があります。理想的には全員が同じ瞬間に最大の力(たとえば50kg)を発揮する必要がありますが、実際にはそれは完璧な連携が取れないと難しいため、多少のタイミングのずれが生じます。
45kgの力の瞬間しかタイミングが合わないならば、理論上は100kgの力が出るはずのところが、実際には2人で90kg程度にしかならないのです。人数が増えるほど、連携は困難になり、目減り幅は大きくなります。
この問題は綱引きに限らず、他の集団活動でも同様です。チームメンバーがそれぞれのタスクや役割をはっきりと理解しておらず、的確に協調できていない場合には、努力がむだになったり、作業も重複したりなどしてしまい、全体の効率が低下すると考えられます。
職場の場面で調べた研究でも、集団サイズが大きいほど、特に人間関係がうまく結べず、助け合える関係が構築できないことが、個人のパフォーマンスを下げてしまうことが指摘されています(※Mueller(2012))。
したがって、集団で課題に取り組む際には、効率的な連携やチームワークが必要になりますそれがうまく機能しない場合には、1人あたりの成果が目減りしてしまい、集団全体のパフォーマンスは低下してしまうのです。
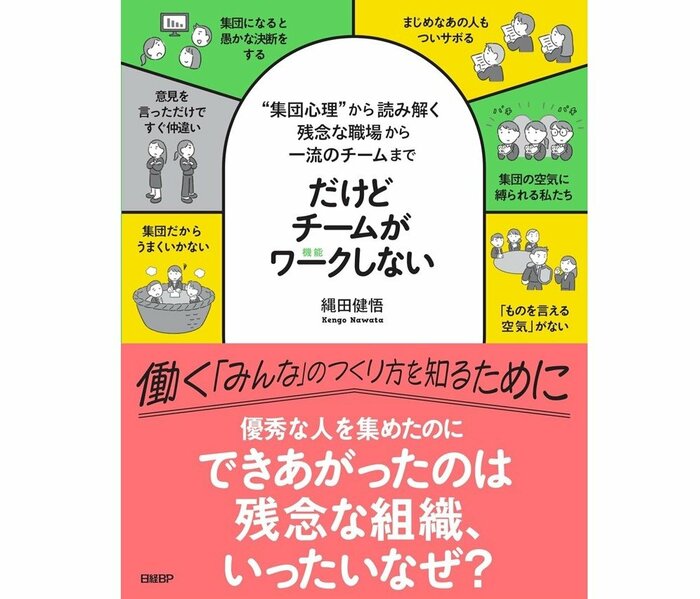
縄田健悟
福岡大学人文学部准教授。専門は、社会心理学、産業・組織心理学、集団力学。集団における心理と行動をテーマに研究を進め、特に組織のチームワークを向上させる要因の解明に取り組んでいる。一般社団法人チーム力開発研究所理事も務める。著書に『暴力と紛争の“集団心理”:いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ』(ちとせプレス)などがある。






