職場など集団で物事に取り組むとき、アイデアがたくさん出てきたり一緒に全力投球できる仲間がいて心強く思う一方、集団だからこそ一人のときには見られないような行動がされるという。
それは“負の集団心理”の一つ、「サボる」ことだ。
福岡大学人文学部准教授の縄田健悟さんは、著書『“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで だけどチームがワークしない』(日経BP)で、「どうしたらもっとうまく組織が動くのか」という問いに対して、集団の心理の視点からそこに潜む問題と解決策を解説している。
本著から「集団だからこそサボる」ことについて、一部抜粋・再編集して紹介する。
集団だからサボってしまう
「サボる」という日本語、もともとはフランス語のサボタージュから来た言葉ですが、すでに日常的な言葉として根づいています。
私もあなたも、職場の誰かも、みんな常に全力投球で働いているわけではありません。ついついサボってしまいます。
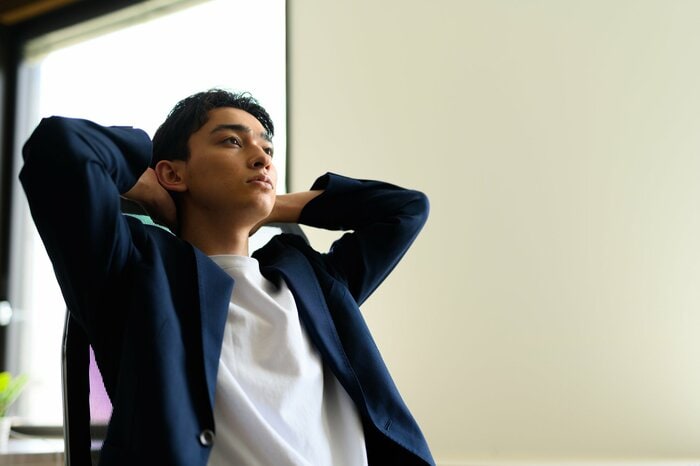
しかし、これは集団研究の観点からすると、単なる個人の性格や意志の弱さの問題だけではありません。集団の中で働く際に生じやすいものなのです。
もちろん「だから良い」というものではなく、「集団はサボりが生じやすい」というのを出発点として、「サボりが生じやすい集団の中で高いモチベーションをどう維持するか」というのを考えていくことが必要になります。
これを、「社会的手抜き」という現象から考えていきます。
集団では、集団の人手を増やすほどに、1人増やすことで得られるはずのプラスの効果が、なぜか目減りしていくことが起きます。





