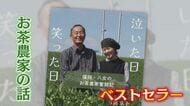「国際女性デー」が制定されている3月にあわせ、フジテレビのアナウンサーが自分の視点でテーマを設定し取材し、「自分ごと」として発信します。
2024年5回目の担当は梅津弥英子アナウンサーです。
「ルッキズム」という言葉を見聞きする機会が増えた。
「人を見た目で判断してはいけない」ということは分かっているし、子どもたちにもそう教えてきた。しかし、第一印象で相手を判断することはあるし、中学生の娘は見た目をいつも気にしているように見える。

正解が見えにくいルッキズムついて、子どもたちにどう教えればいいのか。外見についての差別に詳しい、東京理科大学・西倉実季教授に話を聞いた。
「ルッキズム」は単に「見た目で判断すること」ではない
ルッキズムというのはLooks(見た目)+ ism(主義)を合わせた造語で、元々は太っている人への差別を問題視する言葉だった。
西倉さんはそんなルッキズムが、最近の日本、特にSNS 上では単に「人を外見で判断すること」という意味で語られていて、背後にあるジェンダーの問題がどこかにいってしまっていると危惧している。

その一例として、自民党・麻生副総裁の発言を挙げている。
2024年1月、麻生氏は上川外務大臣に対して「そんなに美しい方とは言わない」「おばさん」と評し、批判を浴びた。
見解を問われた上川大臣は、「どのような声もありがたく受け止める」と応じた。
この麻生氏の発言を西倉さんは「社会的な集団として圧倒的な『俺たち(男性)』が、『女性』を評価する構図だ」と指摘する。
西倉さん:
上川さんが抗議しなかったのに、麻生さんにあれだけ批判の声が上がったのは、政治の世界だけでなく、企業や組織の中で、多くの女性が望まない場面で外見評価を受けているからです。それなのに、“ルッキズム”が単に『人を見た目で判断しちゃダメ』という意味で捉えられ、その理不尽さがきちんと理解されていないと感じます。
麻生氏の発言の”本当の問題点”
西倉さんは、「麻生氏の発言の問題点は、外見批判だけでなく、背後に女性蔑視、つまりはジェンダー差別があること」 だと繰り返す。
確かに「麻生さんが上川さんの外見を褒めていれば問題にならなかったんでしょ?」という反応を、私も耳にした。 この反応こそが、“ルッキズム”の背後にある“ジェンダー差別”が理解されていない証拠なのかもしれない。
さらに西倉さんは、ルッキズムの背後には“ジェンダー差別“だけでなく「人種や障害の有無などの差別も横たわっている可能性がある」と指摘する。

西倉さん:
例えば「制服が着られない」というのが典型的です。周りから望ましいとされる外見に合わせられない理由に、その人のアイデンティティや、尊厳の問題が関わっていることがあるのです。
「制服を着るのが辛い」という声は社会に波及し、その苦しみを理解しようとする動きが少しずつ生まれている。一方で、あらゆる場面を想像した時、声の存在に気付かず、無意識のうちに誰かを差別する側になっていないだろうか、そんな不安が頭をもたげた。
特に思春期の子どもたちの声に耳を傾けられているだろうか。
フィルターや加工、顔面や骨格診断…見た目から逃れられない若者たち
ルッキズムが社会問題化するのに反して、若い世代の見た目への関心は加速しているように感じる。

写真にフィルターを掛け、アプリで顔を加工するのが当たり前な時代。 そんな若い世代が外見にコンプレックスを抱いてしまうのは当然だと西倉さんはいう。
西倉さん:
一重まぶたを直すべきもののように美容広告では謳われていて、それがあれだけ若い世代の目に触れてしまう状況ですから。若い人たちは、縛られなくてもいいものに縛られている可能性があると思います。
さらに顔面や骨格を診断するアプリは「見た目の問題をみつけるツール」だといい、それらに囲まれている状況も、例えば「ブルベはイエベより色白」などと、暗に診断結果で序列をつけられているように感じかねないという。
では、そんな呪縛から解放するために、親はどんな声をかければいいのだろうか。
そのコンプレックスは「あなた側の問題ではない」
西倉さんは『もし身体や顔にコンプレックスを持っているとしたら、比較しているものに問題があって、あなた側に問題があるわけじゃないかもしれない』そんな声がけだけでも、ハッとする子はいると、アドバイスを送る。

西倉さん:
現実の人間の身体はすごく多様なのに、SNSやメディアで美しいと描かれるものには相当な偏りがあります。そのことに、子どもの年齢によっては気づけないと思うんです。
また、日本で性教育がほとんど行われていないことについて、さらに包括的な性教育(セクシュアリティ教育)の導入も必要だと考えています。
身体や生殖の仕組みだけでなく、性の多様性やジェンダー平等など、幅広く性について教えることで、外見の違いを認め合う姿勢が身につくのではないかという。
西倉さん:
例えば、『ふくよかな体型の美しさもあるよ』というメッセージで救われる人がいるのは確かです。
私自身、多様な美のあり方が認められるようになれば、一つの大きな物差ししかないよりは良いと思っていました。
その一方で、ある学生から受けたコメントが忘れらないというのだ。
ただ生きていきたい…ある学生の訴え
『いくら物差しが増えても、そこから外れる人は必ず出てくる。特定の野菜が嫌いでも死ぬことはないのに、自分の外見がものすごく嫌いだということが死に結び付く場合がある。それぐらい外見に価値が置かれている社会がおかしい』
外見評価に振り回されず、ポジティブじゃなくても、ただ単に生きていきたい。そんな訴えだったという。

私たちは視覚的な情報に相当影響されているし、それを避けることは難しい。
ルッキズム研究の歴史は浅く、言葉の定義も定まっていない。人の容姿に言及する時には、「もしかしたら…?」という心持ちでいることが求められる。その上で、西倉さんは「個人の心持ちに委ねるのではなく、社会の仕組みを変えていくべきだ」と提言する。

西倉さん:
外見が評価基準でないのであれば、就職の際に写真を要求しないこともできるはずですから。
多様性を感じさせる広告モデルが支持されたり、芸人が容姿ネタを封印したり、アイドルの過度な露出に疑問を呈したり。一足飛びにはいかないけれど、ちゃんと社会は変化している。
ルッキズムは正解・不正解ではなく、「これはどうなの?」と確かめることが大切なのだと思う。
子どもたちには、見た目にとらわれず、自分や相手を大切にすることを伝えていきたい。
(取材・文/フジテレビアナウンサー 梅津弥英子)
東京理科大学教授・西倉実季(にしくら みき)
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士(社会科学)。現在、東京理科大学 教養教育研究院 教授。著著『顔にあざのある女性たち―「問題経験の語り」の社会学』は2010年第29回山川菊栄賞を受賞している。
「ジェンダーについて、自分ごとを語る」
2023年に続き、フジテレビアナウンス室では、アナウンサーが自主的に企画を立ち上げ、取材し、発信します。
「私のモヤモヤ、もしかしたら社会課題かも…」まずは言葉にしてみることから始める。
#国際女性デーだから
性別にとらわれず、私にとっての「自分ごと」、話し合ってみる機会にしてみませんか。