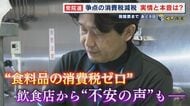「踏切」というと警報機や黄色と黒の遮断機をイメージすると思うが、一方で遮断機などがついていない踏切も…。警報機や遮断機がついていない踏切は「第4種踏切」と呼ばれていて、死亡事故も起きている。危険であるのになぜ無くならないのか取材した。
遮断機と警報機のない踏切で死亡事故
大分市木佐上にあるJR日豊本線関田踏切。
11月18日、高齢の男性が特急列車にはねられ亡くなる事故があった。この踏切は遮断機と警報機のない「第4種踏切」だった。
幅は軽自動車が通るのがやっとの小さな踏切。付近には列車の接近を知らせるものは何もない。また、線路がカーブしているため、東側から渡る際にはかなり見通しが悪くなっている。遠くからかすかに聞こえる踏切の警報音で列車が来ることを認識しているような状態。

近くに住む人に話を聞くと、普段から危険だと感じていて遮断機か警報機をつけてほしいと感じているという。
こちらでは線路を挟んで家と駐車場の行き来をする人がいるため、踏切を廃止するのはやめてほしいとのことだった。
危険な踏切、無くならないのはなぜ?
JR九州によると、ことし4月時点で遮断機も警報機も無い第4種踏切は九州内に212か所。
大分県内では26か所に設置されている。
国によると100か所あたりの踏切事故件数は遮断機と警報機がある「第1種踏切」が0.59件なのに対し、遮断機も警報機も無い「第4種踏切」は1.02件と約2倍となっている。
しかし、危険な踏切はなかなか無くならない。
それには様々な理由があるようだ。

続いて取材に訪れたのは大分市賀来にある中片面踏切。こちらも遮断機と警報機が無い第4種踏切。
踏切には止まってしっかり確認するように促す標識しかなく、道幅もわずか1mほど。
さらに130mほど歩けば警報機と遮断機のついた踏切があった。
すぐ近くに安全性の高い踏切が設置されているのにどうして、この踏切は廃止されていないのか。

利用する人に話を聞いてみると「この踏切を渡ったあちら側の人がこちらに渡ってくる。あちらに住んでいる人がこの踏切を利用するというのは、かなりあると思う」という。
もし踏切が無くなったら…という問いに対しては「ちょっと遠回りではあるがそれの方が安心かなとは思う。ただ利便性からするとこちら側から渡っていける方が本当にありがたい」という。
利用する人の話によれば踏切の先に住宅があり、その人たちが徒歩や自転車で移動する際の生活道路として利用しているとのこと。
利便性を求める声と費用の壁
JR九州大分支社によると、県内で廃止された第4種踏切の数はここ10年でわずか3か所に留まっている。
国も鉄道事業者に対し危険な踏切を無くすよう求めているが、地元からは利便性を求める声も多く合意形成がなかなか進まないという。
また、遮断機や警報機を新たに設置するのに1か所あたり数千万円の費用がかかるといいJRは「現時点では難しい」とのスタンスだ。
いまだ各地に残る危険な踏切。
安全性と利便性さらには経費の関係もあり解消されるにはまだ時間がかかりそうだ。
(テレビ大分)