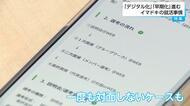多くの学校で夏休みが明けるこの時期、18歳以下の自殺が最も増加する傾向にあります。
子どもたちのSOSにどう気づき、命を守ることができるのでしょうか?
(取材・執筆:フジテレビアナウンサー 佐々木恭子)
親に「助けて」とは言えない
精神科医で子どもたちの自殺予防に取り組む国立精神・神経医療センター 精神保健研究所の松本俊彦氏(薬物依存研究部部長/薬物依存症センターセンター長)に聞きました。
佐々木恭子:
親は子どもの異変、「死を考えるまで追い込まれている」というサインにどう気づくことができるでしょうか。
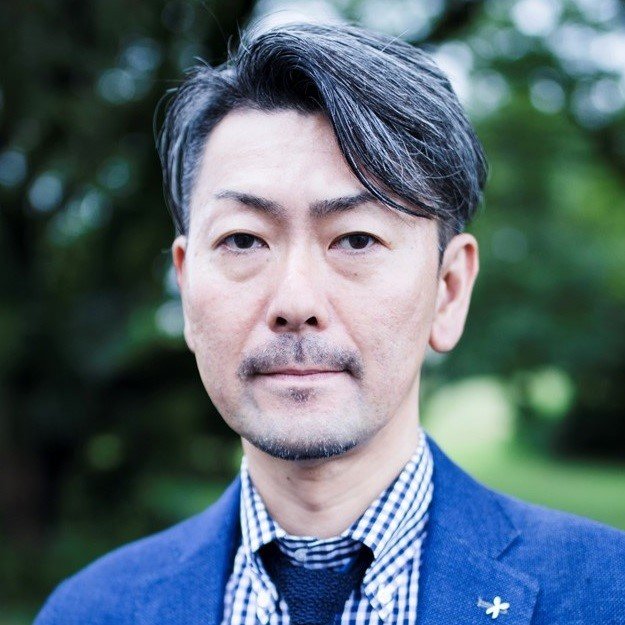
松本俊彦氏:
まず、子どもたちは自分のことを大切に感じている大人たちを心配させたくないものです。
身近な人にほどサインは出さない。
しかも、大人よりずっと簡単に「死」を考えてしまうのです。
小学校4年生くらいまでは家庭が世界の全て。高校1年生くらいまでは学校が世界の全て。
そこで何か行き詰まると、世界が終わったような感覚を得てしまい、また死生観も未熟なので、大人よりもすぐに「死」を考えがちです。
だから、日常のちょっとした変化・・・たとえば、“食欲がない”“睡眠がとれていない”“なんだか元気がない”など、様子が違うと思ったらすぐに声をかけてみる。
また、悩みを抱えていることは恥ずかしいことではないと、伝えていくことが大事です。
親も地域の「支援」に頼ってみる
佐々木:
そういった小さな変化に気づいた場合、親はどういう支援先を探していけばいいのでしょうか。
松本氏:
地域の精神保健福祉センターに相談に行くことを強く薦めます(都道府県と政令指定都市に少なくとも1カ所は設置されている)。
精神科医、臨床心理士、精神保健福祉士といった専門のスタッフがいて、本人だけではなく家族の相談にも乗ることができ、そこで医療機関や親としてどう対応するのか、といった情報を得られます。
親自身が悩みを聞いてもらい、安定感をもって子どもに声かけをすることによって、子ども本人が救われることも結構あるのです。

佐々木:
親自身も悩んだときにはだれかを頼っている姿勢が子どもにも伝わりそうですね。
松本氏:
それがいいロールモデルになります。
親が我が子のことは自分たちで何とかしないといけないと抱えすぎてしまうと、子どもはますます本音が言えなくなり、追い詰めてしまいます。
また、子どもの場合は精神科で診療を受け、服薬してパッと解決するような問題ではないことが多いです。
ただ、すぐに効果がないと考えて通院が無駄だと思ってしまい辞めてしまうと、次の手が打ちづらくなってしまうのです。
頼れるのは「子ども同士」のネットワーク
2017年来、学校で実施される「自殺予防」の教育においても”SOSを出そう”と提唱される中で、松本氏はむしろ自殺リスクの高い子どもたちはその反対にいる、といいます。
また、SOSを出せないことを責められるようで、さらに孤立を深めてしまうことになる…とも。

松本氏:
子どもたちが一番SOSを出せるのは、大人ではなく、子どもたち同士なんですよ。
だから、むしろ子どもたちに「友達のSOSに気づこうよ」と伝えたいのです。
「評価」とは関係のない大人につなぐ
松本氏:
子どもたちの中にも成功体験が多く、自己肯定感の高い人がいます。
そういう人にはぜひ教室の中で浮いていしまいがちな人、みんなを傷つけるような言動をしてしまう不器用な人に、挨拶から始めてもいい。
「私もついていくから、一緒に相談に行ってみない?」と声をかけてほしい。
担任の先生でももちろんいいし、養護の先生やスクールカウンセラーなど、教科の評価に関わらない人のほうが安心できれば、それでももちろんいい。
身近にいて信頼できる大人、評価の対象外にいる大人たちのところに一緒に行って支援につないでほしいのです。

佐々木:
令和4年には小中高生の自殺者が500人を超えたというショッキングなデータが厚労省の統計によって示されました。
この現実を社会でどう受け止めていけばいいのでしょうか。
松本氏:
自殺者総数自体は平成10年から14年間3万人を超えた高止まりの状態を現在は脱しているにもかかわらず、児童生徒は右肩上がりで増えており、しかも同じくらいの勢いで学校の教職員のメンタルヘルスによる問題で休職者の数も増えています。
自殺リスクの高い子どもたちの背後には自殺リスクの高い大人たちがいるのです。
子どもたちを支える大人たちが疲弊していないか目配りしながら、学校にだけもっと頑張れ、というような単純な問題ではない認識が必要です。
楽なところに「逃げてもいい」
2学期を目前に行った今回の取材で、松本氏は子どもたちには「楽なところに逃げてもいい」ことを伝えたいといいます。
学校がしんどければ行かなくてもいい、家庭がしんどい人はそれ以外の方策を考えていい、と。
苦痛を根性で乗り越えた先に光が見えるということではなく、自分自身のエネルギーはもっと大事なことに使っていいのです。
私たちアナウンサーも著名人の自死のニュースのたびに、何をどのように伝えるか、葛藤があります。また誰かの心を激しく動揺させることにつながらないか、恐れもします。
だからこそ、平時から自殺の「予防」につながるような発信を。
9月10日~16日の自殺予防対策週間に向けて、フジテレビアナウンサーが取材を連ねていきます。