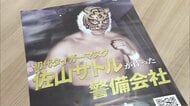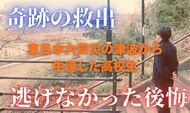東日本大震災から間もなく12年。宮城県石巻市雄勝町には、廃校を活かして子どもたちが自然を体験する施設「MORIUMIUS(モリウミアス)」がある。2015年にオープンして7年半、日本中の子どもと親が訪れるこの施設の油井元太郎代表に、“森と海から子どもと町の明日をつくる”MORIUMIUSが目指す子どもと町の姿について聞いた。

津波が襲った雄勝町は人口流出が続く
MORIUMIUSのある雄勝町は石巻市の北東部にあり、美しいリアス式海岸に面した漁業の町だった。しかし震災時巨大津波が襲い200人以上が犠牲となった。また津波によって町の8割の住宅が全壊し、震災前に4千人以上いた人口は流出が止まらず、いまは当時の1/4の約千人となっている。
平地が少ない雄勝町は宅地のほとんどが災害危険区域に指定された。住民は高台に移転したが、移転の決定に時間がかかったことが人口流出の原因になった。沿岸全域には巨額の予算が投じられて全長3.5キロメートル、高さ最大10メートルの防潮堤が建設された。漁業の町でありながら、沿岸を車で走っても防潮堤で海はほとんど見えなくなった。

豊かな自然の中で子どもの学びを実現
油井さんは職業体験施設キッザニアの立ち上げメンバーだったが、東日本大震災を機にボランティアとして石巻市雄勝町を訪れた。その際に豊かな自然や人々に魅せられた油井さんは、震災前からやりたかった自然の中での子どもの学びをこの地で実現しようと、廃校となった小学校を見つけて新しい学びの場を立ち上げた。
また代表理事の立花貴さんは宮城県出身で、震災時にボランティアとして雄勝町に入った。MORIUMIUSはこれまで延べ1万5千人が訪れ、子どもだけでなく企業研修の場としても活用されている。

ハードを優先した行政主導のまちづくり
雄勝町を10年以上見てきた油井さんに、まず雄勝町のいまをどう見るか聞いた。
「過疎化が進んでしまいましたね。高齢化の町なので、復興住宅をつくっても住民が亡くなって空き家が出たりしています。石巻市全体では復興交付金事業が本年度で終了となります。12年近くかけた行政主導による公共工事中心のまちづくりが終わるんだなと思います」
こうしたまちづくりを油井さんは「ハードが優先された」と語る。
「行政にはハードを作る知見や経験、予算はありました。しかしハードの整備ができたことで、多くの人が来るかというとそうではなかった。これは雄勝町に限らず全国の地方の課題で、ハードに合わせて必要なソフトづくりは、これまでやっていなかったのが現実なのかなと思います」

MORIUMIUSはソフトで人を集める
一方でMORIUMIUSはまさにソフトによって雄勝町に人を集めた。設立までは延べ約5千人のボランティアが集い、知見を出し合いながら協力した。油井さんは「子どもの学び場として雄勝町を選んだのは、まさに大正解だった」と言う。
「自然が身近に無くなっているいま、雄勝町のような場所こそが子どもの成長に欠かせないと確信を持っていました。オープン当初はSDGsという言葉もほとんどありませんでしたが、いまは学校の先生から『MORIUMIUSはSDGsを実践できる場所ですね』と言われるなど、学び場として価値を高めています」

子どもの自主性や主体性を育む自然体験
これまで7年半、MORIUMIUSの体験を通して、子どもたちにはどのような変化があったのか?そう聞くと油井さんは「一番顕著だったのは自主性や主体性です」と答えた。
「いまの子どもは社会や大人に守られ過ぎている一面があります。さらにテクノロジーの力で何でも簡単に出来てしまうので、子どもが自らやり抜く機会がなくなりました」

MORIUMIUSで子どもたちは、自ら火をおこし、料理を作り、堆肥にして土に還して農業をする。そうすると自分では上手くできないことのほうが圧倒的に多いことがわかる。「ですが我々は子どもに指導したり手伝うことはしません」と油井さんは言う。
「自分で考え失敗を繰り返し、協力しながら最後は達成感を得ることを大事にしています。そうすることで自主性と主体性がつきますし、生きることを実感し、感覚や感性、創造性も磨くことになります」

葡萄づくりで学びと地域経済への貢献を
MORIUMIUSでは今年から農業により注力していく。その一つ、葡萄づくりを行う土地の面積は2万平方メートルで、地域資源を生かした環境再生型で自然を取り戻し六次産業化も目指す。震災後、町の中心部は災害危険地域だったが、2021年から石巻市の規制緩和で農業整備がされて、来月から利用できるようになった。
油井さんはいう。
「地域住民が主体となって官民連携しながら農業を進める中で、MORIUMIUSは加工して付加価値が高く、景観もいい葡萄の栽培にしようと決めました。もちろんこの葡萄畑は子どもたちの学びの場として活かされますし、地域経済への貢献も目指していきます」

持続可能な町にするMORIUMIUS
最後に油井さんに、今後MORIUMIUSはどのように雄勝町のまちづくりに貢献していくのか聞いた。すると「持続可能な町にしたい」と答えが返ってきた。
「人口は千人に満たない小さな町になってしまいましたが、自然はまだまだ豊かですし、災害危険地域を農業利用できるようになって、これから多くの人が集まるチャンスだと思います。持続可能な町になるためには、人を呼び込みながら関係性を作っていかなければいけない。そのためにMORIUMIUSは、成長した子どもたちが第二の故郷のように戻ってくるきっかけになればと思っています」

油井さんはMORIUMIUSと同じような発想を持った拠点が、全国に広がってくれたらいいと考えている。
「こういう考え方は全国どの地域でも活かせるはずです。子どもたちにとってもポジティブな新しい学びの場になりますし、地方創生にもつながるはずです。そんな夢を持ち続けていきながら、仲間を増やしていけたらなと考えています」
雄勝町発の学びが、日本全国に広がっていく。そんな夢が実現するときも近いだろう。
子どもたちの写真提供:MORIUMIUS ほかは筆者撮影

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】