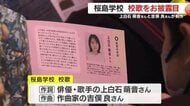ITやAIなど最新のテクノロジーで教育界にイノベーションを起こすEdTech(エドテック)が、一人一台端末の普及で益々重要性が増している。学校教育はいまやエドテック無しには語れない。誕生して約20年と言われるエドテック次世代の現状を取材した。
SXSWにいま多くの日本のエドテックが参加
「2009年から教育イノベーターを支援するプログラムを始めたのですが、2013年にSXSW(※サウスバイサウスウエスト)に何人かを連れて行って。当時は会場の教育ブースに日本人はほとんどいませんでしたが、いまは多くの日本人が参加していますね」
こう語るのは、デジタルハリウッド大学大学院(以下デジハリ)の佐藤昌宏教授だ。
(※)毎年アメリカで行われる音楽・映画・新興企業のイベント

佐藤さんは2021年10月から次世代の教育イノベーターを育成するプログラム「Edvation Open Lab(エドベーションオープンラボ)」を開始した。このプログラムでは20社の教育イノベーターが参加して、メンタリングやピッチイベントを軸としたイノベーター育成を行われた。
教育産業は世界的にも大きく伸びる市場
佐藤さんはその狙いをこう語る。
「教育は誰もが経験したことがあるので課題意識を持ちやすい。ただ素人的な発想なので、学校教育の閉鎖性にぶち当たると『教育は変わらない』『市場規模が小さい』と諦めてしまう。しかし日本の教育産業は学習塾や語学学校など3兆円程度ありますし、世界的にもこれからも大きく伸びる市場のひとつです」

そして佐藤さんは「教育のありかたは変わるはずだ」と続ける。
「GIGAスクール構想(※)のようにデジタルに変われば、教育のありかたを大きく変えられるはずです。『実は儲かるんだよ。変えられるんだよ』と紐解いてあげながら、次のプレイヤーがどんどん出てくるようなエコシステムを健全に回したいんですね」
(※)全国の児童・生徒1人に1台の端末を整備する文科省の取り組み
「子どもたちのやりたい!をカタチに」
エドベーションに参加した、子ども向け動画制作スクールのFULUMA(フルマ)株式会社。2016年に会社を設立したきっかけを代表取締役の齋藤涼太郎さんはこう語る。
「もともと『子どもたちのやりたい!をカタチに』をミッションに掲げて設立して、当時最も子どもがやりたいのに社会が応援できてないYouTuber(動画制作)を始めました」

当初オフラインの教室としてスタートしたフルマは、オンライン化すると日本だけでなく世界中の子どもが受講するようになったという。
「単に動画の編集スキル向上だけでなく、人前で話すのが苦手だった子がカメラに向かって堂々と話せるようになったり、ネットリテラシーを教えることで著作権を気にする子どもが出てきて面白いです」(齋藤さん)

共同編集できるツールに「これは需要がある」
また参加社の株式会社プログミーは、複数人で同時に編集できるプログラミングアプリを開発した。元パイロット訓練生だったという異色のキャリアの持ち主である代表取締役の石橋康大さんは、共同編集機能を業界で初めて開発したきっかけをこう語る。
「息子が4歳のときにスクラッチ(※)を使ってプログラミングを教えてみたところ、息子を膝に乗せて一緒にキーボードとマウスを使うと非常に操作しにくい。そのときに共同編集できるツールを探してみたのですが世の中に存在せず、この機能を求める声が多いことも分かったので『これは需要があるな』と感じました」
(※)MITのグループが作った小学生でもプログラミングができるソフト

プログミーは2020年にプロトタイプを開始し、全国のプログラミング教室などで利用されている。
「子どもたちは一人でプログラミングするよりも、楽しそうに作っています。まるで遊んでいるようですが、トライ&エラーが繰り返されることで成果物に生かされています。今後はプログミーをグローバル展開していきたい。いま東南アジアで展開予定ですが、ヨーロッパを中心に引き合いもあります」(石橋さん)

「なぜヘリウムには手がないのだろう?」
最後に紹介する参加社は「学びをエンタメにする」tanQ株式会社(タンキュー)だ。2014年に設立したタンキューでは、小学生向け教育コンテンツとしてボードゲームなどゲーム型教材や通信教育サービスを提供している。なぜ教育でボードゲームなのか?CTOでマジシャンでもある岩城信二さんはこう語る。

「当初は探求学習型の塾運営を行っていたのですが、学問に興味を持てずにタブレットゲームで遊び出す子どもたちを見て、『そもそも学問にどう興味を持ってもらうか?』を大きな課題として捉えるようになりました。子どもたちが“学問”の入り口でつまずかずワクワクしながら取り組んでもらうため、いまのゲーム型教材に至りました。また、個人的にはマジシャンとして子どもたちにショーを行っていることもあり、勉強をより楽しくエンタメ性に富むものにしたいとずっと考えていました」
2019年から展開しているゲーム型教材は、全国の学童や保育園、学校へと徐々に広がっている。
「化学ゲーム“アトモン”では、小学2年生の男の子がトイレに行く際『アンモニアを出してくる』と言ったり、キャラデザインを見た子どもが『なぜヘリウムには手がないのだろう?』と疑問に思って自分で調べ始めたり。まだ着手できていない学問分野をゲーム化して、より多くの子どもが体験できるよう公教育への導入とそのためのデジタル化を推し進めたいです」

「エドテック志向は思考停止していた」
オープンラボの中でそれぞれのイノベーターは何に気づいたか。
フルマの齋藤さんは「自分達になりに子どもたちと向き合っているつもりでしたが、もっとリアルな声を聞く機会を増やし、子どもたち、保護者の期待値を超えられるプログラムにする必要があると感じた」という。
また、プログミーの石橋さんは、「教育分野の専門家から、プログミーの教育効果をどのように実証していくべきか、具体的な方法論を示して頂いた」と振り返り、タンキューの岩城さんは「単にデジタル化して誰でも使えるようにするというエドテック志向は思考停止していたなと気づかされました」と語った。

既成概念を変え子どもの幸せと学びにつながる
こうした次世代のエドテックにどんな希望を見出すのか。デジハリの佐藤さんはこう語る。
「学校教育の複雑な仕組みやルールを理解している人と、イノベーターたちのマッチングをできれば教育は変わるんじゃないかと思っています。素人発想に対して『それは教育じゃない』という既成概念がありますが、そもそも教育の体験者である“素人”が一番中立的に見ている。テクノロジーによる学びの変化を受け入れるために、制度や学校のあり方を変えていくべきだというのが未来への提案です」

イノベーターからの提案は、学校教育の既成概念を変え、子どもの幸せと学びにつながることができるはずだ。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】