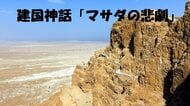An Apology Facilitated the Peace(謝罪が平和を動かした)
外交の歴史において「謝罪」が果たす役割は、しばしば過小評価されてきた。武力や制裁よりも、時に一言の謝罪が関係修復の糸口をつくることがある。
今回のガザ停戦合意も、そんな「一言」から動き出した。
きっかけは9月9日のイスラエル軍によるドーハ空爆だった。標的はハマスの政治部門幹部とされたが、実際にはカタールの治安要員1名が死亡し、同国の主権が侵害されたとして外交危機に発展した。

和平仲介の要を担ってきたカタールは強く反発し、調停役を一時停止。これでガザ停戦への道筋は途絶えたかに見えた。
転機はその20日後に訪れる。ワシントンを訪れていたネタニヤフ首相が、トランプ大統領立ち会いのもと、カタールのムハンマド首相に電話をかけたのだ。「カタールの主権を侵したことを深く遺憾に思う。再発はない」と謝罪を伝えた。

報道によれば、この謝罪の文面はホワイトハウスとカタール双方の協議で作成され、さらに「カタール首相の親密な側近」が執筆に加わっていたという。
その側近は謝罪電話の際、トランプ、ネタニヤフ両氏と共にホワイトハウスの大統領執務室(オーバルオフィス)に同席し、首相が台本どおりに発言しているか確認していたと米政治専門誌Politicoは報じている。

イスラエル首相府は「フェイクニュース」と否定したが、同席したカタール高官の存在は米政府関係者も認めている。
なぜカタールだったのか?
興味深いのは、謝罪の相手となったカタールという国の位置づけである。
湾岸諸国の中でも最も独立色が強く、時に「強硬派」と評されるこの小国は、2017年にはイランとの関係やイスラム組織支援を理由に、サウジアラビアやUAEなどから事実上の「追放」を受け、湾岸協力会議(GCC)から孤立した。

しかし、その独立路線こそが今回の和平で決定的な意味を持った。カタールはハマスの政治局をドーハに受け入れており、ガザ戦争をめぐる交渉で唯一、ハマスと米国の双方に直接パイプを持つ存在だった。
ワシントンやテルアビブにとっては「嫌悪すべきがゆえに必要な仲介者」だったのである。
言い換えれば、かつて「問題児」とされたカタールだからこそ、誰も触れられない相手と話ができた。謝罪によってその関係が修復されると、カタールは再び交渉の場に戻り、ハマスとイスラエルの間に橋を架けた。強硬で孤立してきた国が、結果的に最も柔軟な和平の推進者となったのだ。
この構図は中東外交の逆説を象徴している。イスラエル側では最も右派色の強い政権が、最も強硬とされた湾岸国家に頭を下げ、その仲介によって停戦が成立した。しかもその舞台裏には、ホワイトハウスが書いた“台本”と、それを見届けるカタール高官の姿があった。歴史の皮肉と言うほかない。
謝罪が開いた外交の扉
米紙Axiosは「カタールの調停を取り戻すためのカギは謝罪だった」と報じ、CSIS(戦略国際問題研究所)は「トランプ政権がネタニヤフに謝罪を迫った」と分析している。 この一件をきっかけに、カタールは再び仲介に復帰した。ハマスとイスラエルの交渉ルートが再開され、10月初旬には第一段階の停戦と人質交換で合意が成立した。
もちろん、謝罪だけで和平が成ったわけではない。エジプトやトルコの協力、米国の圧力、そしてイスラエル国内の政局など、複数の要因が交錯している。それでも、外交が再び動き出すための「感情的障壁」を取り除いた点で、この謝罪の意味は小さくない。

外交の舞台では、メンツがしばしば理性を凌駕する。特に中東では、尊厳と敬意の表現が何よりも重要だ。
一方で、イスラエル国内では反発も強い。極右閣僚は「国家の恥」と批判し、首相府は「米国が書いた謝罪文」という報道を否定した。だが結果的に、謝罪のあと和平への流れが動いたことは否定しがたい。

「謝罪外交」はしばしば国内政治では弱腰と受け止められる。しかし、国際政治の現場では、謝罪は時に最高の戦略となる。9月29日の短い電話が、10月9日の停戦合意へとつながった事実は、その好例である。
力の政治の時代にあっても、「一言の誠意」が平和を呼び戻すことがある――今回の中東の一幕は、そう教えているように見える。
(執筆:ジャーナリスト 木村太郎)