たとえば、取引先の担当者のエピソードとして、「あの人は、こちらの提案に対して非常に細かな点まで確認してきた」といった記憶があったり、「あの人は、こちらが詳しい説明をすると、そんな説明はいらないから、どういうメリットがあるのかを端的に示してほしいと言われた」といった記憶があったり、「あの人は、こちらの提示した資料の数字にやたらこだわって質問してきたなあ」といった記憶があったりすれば、それぞれの人物を相手にするのにふさわしい資料を準備したり、説明の仕方を工夫したりできる。

取引先の人物でも、社内の人物でも、「こちらがこんな言い方をしたとき、あの人は怒ったような口調になった」「あの人は、コンプレックスが強いみたいで、ちょっとした話題にすぐに反発する」というような記憶があれば、言い方や話題に気をつけることで、再び地雷を踏むのを避けることができる。
モチベーション向上にも活かせる
ポジティブな感情と結びついた過去経験を引き出すことで、自分自身を勇気づけ、モチベーションを高めるというように、自分の心理状態のコントロールに活かせるという効用がある。
モチベーションには大きな個人差があるが、個人差をもたらす最も重要な要因が過去の経験である。
これまでにうまくいった活動領域、気持ちよくやってこられた生活領域では、当然ながらモチベーションが高い。あまりうまくいかないことが多かった活動領域、嫌な思いをすることが多かった生活領域では、どうしてもモチベーションは上がりにくい。
そうした過去経験が人によって異なるため、モチベーションには大きな個人差がみられるのである。
そこで大切なのは、ポジティブな気分をもたらす記憶へのアクセスを良くしておくことである。思い出すと前向きな気分になれるエピソード、自分に自信が感じられるエピソードなどを時々思い出すことで、アクセスを良くすることができる。
どうも気分が乗らないときや大事な仕事を前にしてどうしても自信がもてないときなどは、その種のポジティブな記憶にアクセスすることで、前向きな気持ちで仕事に向かうことができる。
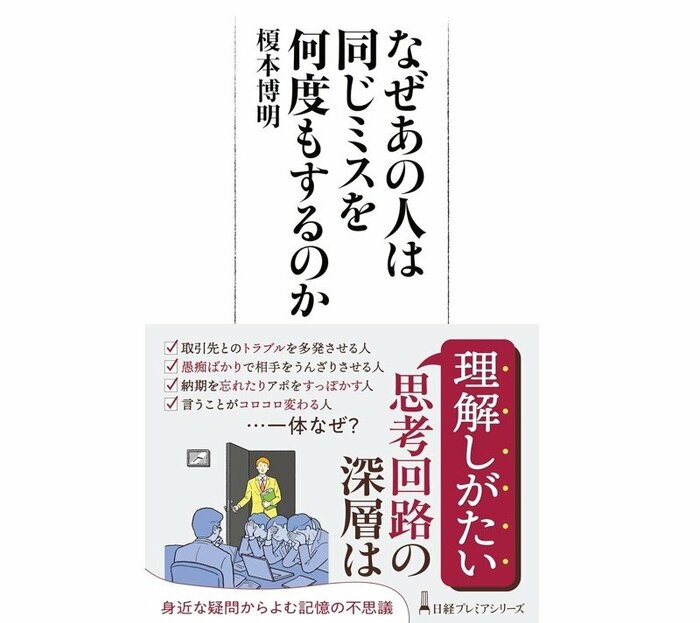
榎本博明
東京大学教育心理学科卒。心理学博士。MP人間科学研究所代表。著書に『「指示通り」ができない人たち』『勉強できる子は〇〇がすごい』『伸びる子どもは〇〇がすごい』『読書をする子は〇〇がすごい』『ほめると子どもはダメになる』『教育現場は困ってる』『「上から目線」の構造』など多数。






