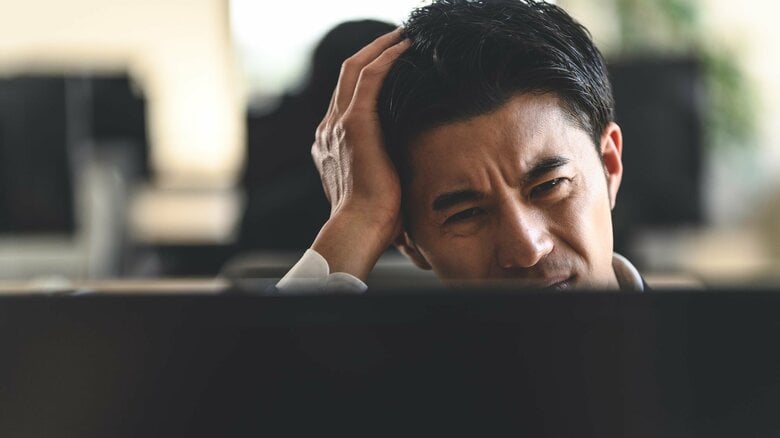周囲にいる「思い込みが激しく、話を聞いてくれない人」に頭を抱えることはあるだろう。
仕事の状況によっては、自分の言葉に耳を傾けてほしかったり、なぜそこまでかたくななのかと困ってしまう。
こうした事態を打開するためには、「思い込みが激しく、話を聞いてくれない人」に、すでにインプットされている情報を覆す必要があり、焦らずじっくりと話し合うことが大切になるという。
心理学者・榎本博明さんの著書『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』(日経プレミアシリーズ)から、一部抜粋・再編集して紹介する。
思い込みが激しいタイプの頭の中
仕事をしていて困る相手に思い込みの激しいタイプがいる。
向こうが不安に思っている点について、そこは大丈夫だという説明をしても、向こうのクレームが勘違いに基づくものであることを説明しても、なかなか納得してもらえない。
こちらがいくらていねいに説明しても、こちらの言い分がまったく向こうの頭の中に入っていかない。はじめからこちらの説明を聞く気がないとしか思えない。

このような相手とやり取りしていると、こっちの話にちゃんと耳を傾けてほしい、なぜそこまで頑かたくななのだ、とイライラするのではないか。
そうしたケースでは、すでに頭の中にインプットされている事前情報によって洗脳されているようなものなので、それに反する情報はなかなか素直に取り入れてもらえない。
「なぜそんなに思い込みが激しいのだ、少しはこっちの言うことに耳を傾けろよ」と言いたくなるだろうが、こうした事態を打開するには、すでにインプットされている情報を覆す必要があるため、焦らずじっくりと話し合うことが大切となる。
人は格好に左右されやすい
そのような思い込みの激しい人物は、けっして特殊な頭の構造をしているというわけではない。
じつは、だれにも思い込みで動く側面がある。そのことを示す心理学の実験をみてみよう。