エドモンドソンは、さらに研究を進め、その後の現場観察やアンケートでの自由回答、さらにはインタビューから、ミスについて率直に話せるかどうか、つまり心理的安全性がチームごとに大きく異なっていることに気づきました。
どうやら心理的安全性が、チームが学習し、高い成果をあげていくためのカギとなる要素のようです。
これを踏まえ、行われた次の研究では、エドモンドソンはオフィス家具製造会社の51チームを対象に、心理的安全性の効果を直接的に検証する研究を行いました(※Edmondson(1999))。
その結果、心理的安全性がチーム学習やチーム成果に大きく影響することが確認されました。この研究を契機として、心理的安全性は一躍脚光を浴びるようになり、学術研究だけでなく現場実践においてもキーワードとなっていったのです。
仲良しこよしの「ぬるま湯」ではない
読者の中には「ウチの会社は1つのミスが命取りになるような厳しさが必要な会社だから、心理的安全性のようなぬるい考えではダメだ」といったことを思った方もおられるかもしれません。
ここは誤解されることが多いところなので、改めて指摘したいのですが、心理的安全性は仲良しこよしの「ぬるま湯」状態ではありません。
むしろ厳しさが求められる組織でこそ、心理的安全性が必要となります。

「ぬるま湯」や「なれあい」のチームは短期的には居心地が良いかもしれません。けれどそれでは成果はあがらず、目標となる業績を達成できません。
また、ミスをして事故を起こすなど、顧客や社会に迷惑や損害を与えてしまう恐れもあります。それは望ましいチームの状態とは呼べず、心理的安全性の高いチームとは別物です。
真に心理的安全性の高いチームでは、ぬるま湯どころか、ときに厳しい意見も飛び交います。率直に発言しても大丈夫だという心理的安全性が確保できているからこそ、メンバーは率直に意見を言うことができるためです。
偉い人からの一方通行ではダメ
逆に、その風土がチームにない組織では、自分の意見を言わず押し黙ってしまうことが多いでしょう。
心理的安全性がチームにあってはじめて、メンバーは率直に自分の意見を述べながら議論を行い、失敗から学習することができるチームとなっていくのです。
ここでもう1つ注意すべき点は、「厳しく異論を述べること」というのが、偉い人からの一方通行ではあってはならないということです。
立場にかかわらず、双方向で議論ができることが重要となります。ときには上の立場の人に対しても、問題や誤りがあれば、それを遠慮せず率直に進言することができるチームをつくっていかなくてはいけません。
下の立場からの進言は、ときには未熟さからくる誤解であることもあるでしょう。しかし、それをただ上から叱りつけると、萎縮(いしゅく)するだけです。
チーム学習にはつながっていきません。今後その人は自分の気づきや疑問を尋ねなくなってしまうでしょう。また、大半は未熟な指摘であっても、その中には本当に誰も気づかなかった問題点を指摘していることもあるかもしれません。
普段から侮って聞く耳を持たなければ、大事な指摘を見落としてしまうことにもなりかねません。
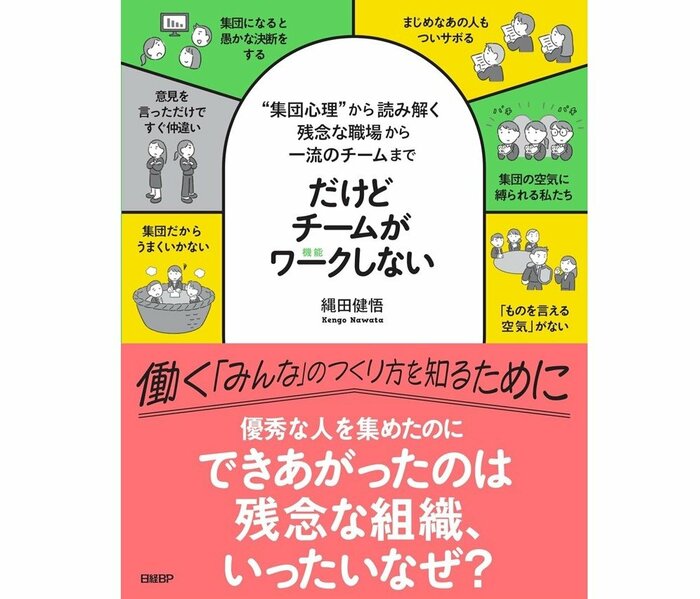
縄田健悟
福岡大学人文学部准教授。専門は、社会心理学、産業・組織心理学、集団力学。集団における心理と行動をテーマに研究を進め、特に組織のチームワークを向上させる要因の解明に取り組んでいる。一般社団法人チーム力開発研究所理事も務める。著書に『暴力と紛争の“集団心理”:いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ』(ちとせプレス)などがある。







