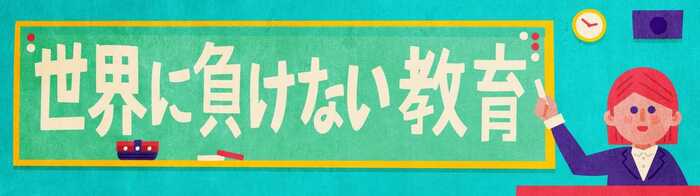手話で応援!「パラ駅伝は気づきの場」

東京都内の駒沢オリンピック公園で先月、「パラ駅伝 in TOKYO 2019」が開催された。
視覚や聴覚、肢体不自由などさまざまな障がいをもつランナーと健常者、合わせて9人がタスキをつなぎながら、全長約19キロを走る。
この日は1万7500人の観客が訪れ、公園内の陸上競技場や沿道は多くの声援に包まれた。
選手チームは、北海道から九州、そして海外はカンボジア(猫ひろしさん率いる!)から18チームが集まった。
また、国際パラリンピック委員会の特別親善大使を務める稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾のメンバーも応援に駆け付け、吉本所属の芸人たちもランナーとして参加した。
「パラ駅伝はある意味、気づきの場です」
こう語るのは、主催する日本財団パラリンピックサポートセンター(以下パラサポ)の小澤直常務理事だ。
たとえば競技場では、こんなアナウンスが流れる。
「2区は聴覚障がいのランナーが走ります。『頑張れ』や拍手を、手話で応援しましょう!」
そのとき観客は、聴覚障がいのランナーが、「頑張れ」の声援や拍手が聞こえないことに気づく。観客に配布されたパンフレット(折り畳むと応援用グッズになる)には、「がんばれ!」や「拍手」の手話のしかたが載っている。観客はみな、最初は戸惑いながらも、慣れない手話で楽しそうに選手を応援している。まさにパラ駅伝は、気づきの場だ。
インスピレーションを与えるパラリンピック

パラサポは様々な事業を通じて、障がいの有無にかかわらず誰もがスポーツを楽しみ、お互いの理解を深めるインクルーシブ社会の実現を目指している。その取り組みの一つが、パラ駅伝であり、パラスポーツ体験型の出前授業「あすチャレ!School」だ。
この教育プログラムは、パラアスリートが小中高等学校に赴き、子どもたちにパラスポーツ体験の場を提供する。さらに、パラアスリートが自らの体験をもとに「障がいとは何か?」「自らが経験してきた人生の中で何が大切だったのか?」を子どもたちに語る。「障がい者の人と話したことがない。聞きたいけど聞けない」という子どもたちが、リアルな声を聞く場なのだ。さらに学んだ子どもが親に教える「リバースエデュケーション」と言われる効果も、このプログラムには期待されている。
一年間で全国約300校で行われているが、「それでも応募が多すぎて回り切れない」(小澤さん)と言う。
2012年のロンドンパラリンピックの成功は、教育が重要な役割を果たしたと言われている。当時の教育担当者はこう語っている。
「パラリンピックは観客を魅了するものであり、同時にインスピレーションを与えます。そしてそのインスピレーションを活用すれば、ものの捉え方を変え、行動を変え、社会を変えることができます。そういった中で、若い人を対象としたパラリンピック教育は非常に重要なツールです」
イギリスでは、学校で「Get Set(ゲットセット)」と呼ばれるオリパラ教育を奨励した。パラリンピックには、「勇気」、「強い意志」、「インスピレーション」、「公平」という4つの価値感が存在する。
実際、ロンドン大会までの4年間に、イギリスでは650万人以上の子どもたちへ普及し、8割以上の学校が「子どもの熱意とモチベーションにポジティブなインパクトがあった」と答えた。このパラリンピック教育は、その後日本を含む世界で“レガシー”として受け継がれている。
インクルーシブ社会の誕生へ
パラリンピック教育やパラ駅伝の開催を通じて、小澤さんはスポーツの力を再認識したと言う。
「障がい者問題ということでど真ん中からいくと、たぶんうまくいかないんです。やはりスポーツがあって、それにダイバーシティがあるといろんな人が関わりやすくなる。スポーツの力はすごく大きいし、社会を作るものとして価値が高いです。私たちはこれまで、案外そこに目を向けてこなかったんじゃないかなと思います」
パラ駅伝に参加したランナーはほとんどが「もう一回出たい」と言う。
「やっぱり楽しかったと。あれだけの人前で観られて走ることはほとんどなかったと思うんです。今回はボランティアが700名来ました。一般募集のほかに、視覚障がいの人もボランティアをやってもらいました。ボランティア枠も毎年すぐにいっぱいになります」
インクルーシブ社会は、あらゆる人が混ぜ合わさることによって生まれる。そして、それを可能にするのが「スポーツの力」だ。

来年、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックがやってくる。
東京は世界で初めてパラリンピックを二度開催し、成功する都市となるだろう。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】
【関連記事:「世界に負けない教育」すべての記事を読む】
【画像提供:日本財団パラリンピックサポートセンター 】