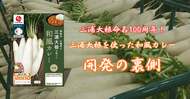株式会社FCEが主催する「チャレンジカップ」は、自ら掲げた目標に半年間取り組む挑戦を応援するイベントです。勉強、スポーツ、ボランティア、創作活動などジャンルは自由。2008年の初開催以来、これまでにのべ15万人が参加し、子どもたちは自分で決めた目標に向かって主体的に取り組み、人間的な成長を重ねてきました。今年で19回目を迎えるチャレンジカップは、8月1日にエントリー受付を開始。参加の条件はただ一つ、「半年後に達成したい目標を、自分自身で決めること」です。
本記事では、本イベントの実行委員長であり株式会社FCE取締役の尾上幸裕氏とチャレンジカップを立ち上げ期から現場で子どもたちを見守ってきたFCEエデュケーション事業本部の鈴木治氏に、それぞれの視点からその想いを伺いました。
「7つの習慣J®」と本質的な成長への願いから生まれたチャレンジカップ

左:鈴木氏 右:尾上氏
2004年にFCEエデュケーションが設立された当初から教育事業に携わってきた尾上氏。2018年には同社の代表となり、「チャレンジカップ」の実行委員長もつとめます。そんな尾上氏は、チャレンジカップの原点は「7つの習慣J®」そのものだったといいます。
尾上氏:私たちが提供する「7つの習慣J®」は、知識をインプットするだけの学習とは異なります。学んだことを“道具”として使い、子どもたちが自分の人生をより豊かにしていくためのものです。勉強よりも「実践」を何よりも重要視していると言えます。
前列中:PHPのびのび子育て増刊 子どもが伸びる7つの習慣 2014年 10月号(PHP研究所)
前列右:子どもの力をみるみる伸ばす7つの習慣J®(幻冬舎コミックス)
前列左:『完訳 7つの習慣 人格主義の回復 新書サイズ』(FCE/キングベアー出版)
後列:『7つの習慣 賢者のハイライト』シリーズ(FCE/キングベアー出版)
※「7つの習慣J®」とは、スティーブン・R・コヴィー博士の著書『7つの習慣』を日本の学生向けに再構成したプログラムです。自立と相互依存の原則に基づき、主体性、目標設定、優先順位付け、Win-Winの思考、理解と共感、協力、自己成長という7つの習慣を通して、生徒が自身の人生を主体的にデザインし、社会で活躍できる力を育むことを目的としており、現在は私立学校を中心に約100校で導入されています。
こうしたなかで、「7つの習慣J®」の授業で学んだ内容をどう日常で実践するか」という課題にも直面していました。
尾上氏:「7つの習慣J®」の効果を最大化する一環として生まれたのが、チャレンジカップです。子どもたち自身に、あえて高い目標を設定して取り組んでもらう。すると、達成に向かうプロセスで“壁”が生まれます。「7つの習慣J®」で学んだことを道具として使いながら、どうすればその壁を乗り越えられるのかを考え、実行していく。この体験こそが、本当の学びの価値だと考えました。自ら高い目標を立て、そこに向かって一生懸命頑張る機会を設けよう、というのが始まりのきっかけです。
こうして「生徒自身が本当にやりたい目標に向かって半年間取り組む大会」として、チャレンジカップが誕生したのです。
完全フリーテーマで挑戦できる――チャレンジカップならではの特徴
 チャレンジカップグランプリ決定戦の様子
チャレンジカップグランプリ決定戦の様子
チャレンジカップの大きな特徴のひとつが、テーマを自由に設定できる「完全フリーテーマ制」です。
企業や団体と連携して特定の課題解決を目指すイベントが多いなか、チャレンジカップでは生徒一人ひとりが「なりたい自分」や目指す目標を自ら決め、その挑戦を尊重する運営方針をとっています。
鈴木氏:「チャレンジカップでは、参加者によって目標もテーマもまったく異なります。スポーツに挑む人もいれば、学習やボランティア活動、創作に取り組む人もいる。こうした自由度の高さは、ほかにはあまりない特徴だと思います。」
もうひとつの特徴が、事後報告ではなく「事前エントリー制」を採用している点。
活動を終えたあとに報告するのではなく、挑戦を始める前に「この期間に、これをやります」と宣言してエントリーします。
活動期間は毎年8月から翌年2月末までの約7か月間。個人でもチームでも参加可能です。
・エントリー締切:11月30日
・活動の一部が8月1日~2月28日の期間に含まれることが条件
(例:4月から開始したチャレンジでも、12月まで継続していれば対象。ただし8月前に終了した場合は対象外)
審査は二段階で行われます。
一次審査は「活動報告シート」と先生の「推薦書」をもとにした書類審査、いわば地区予選のようなイメージです。
続く最終審査では、オンライン(Zoom)でのプレゼンテーション審査が実施されます。現在はほとんどの生徒がPowerPointなどを活用し、画面共有しながら発表しています。
評価は主に二つの軸で行われます。
・「チャレンジ度」:目標の難易度や継続性
・「人間的成長度」:挑戦を通じた内面的な成長や行動変容の度合い
鈴木氏:「『人間的成長度』では、チャレンジによってどれだけ行動や考え方が変わったか、成長の跡が見えるか、あるいは内面的な気づきや得るものがあったかを大切にしています。審査員が5段階で評価するほか、運営側も同じ観点で確認しています。」
目立たなかった生徒に光が当たる――心を動か す成長の瞬間
 2009年受賞者の写真
2009年受賞者の写真
チャレンジカップの魅力は、挑戦を通して生まれる生徒一人ひとりの変化にあります。
成績や部活動では表に出にくかった生徒が、この場で初めて注目を浴び、自信を深めるケースも少なくありません。
鈴木氏:「チャレンジカップでは、これまであまり目立たなかった生徒が、大きな成長を遂げて周囲を驚かせることがあります。内向的だった子がクラスのイベントをリードするようになることもあり、変化を間近で感じる瞬間はとても印象的です。」
特に記憶に残っている事例の一つが、2009年のグランプリ受賞者の男子生徒です。
彼は進学先で友人ができず、孤立した環境で悩んでいました。そんなとき、塾の先生からチャレンジカップを勧められ、「友だちを2人つくる」という自身にとって大きな目標に挑戦することを決意します。
発表では、挑戦の背景や取り組みの過程、そこで得た気づきを率直に語りました。
鈴木氏:「コミュニケーションが得意な子にとっては簡単に思える目標かもしれませんが、彼にとっては大きな挑戦でした。周囲と比較して優れているか?という相対評価ではなく、「その子にとって難易度が高いか、重要度が高いか」という絶対評価を行うチャレンジカップの審査の軸が受賞に繋がった象徴的な事例として、今でも強く記憶に残っています。」
もう一つ、2012年のグランプリ受賞者の女子生徒の事例も印象的です。
彼女はパティシエになる夢を持ち、30種類以上のオリジナルレシピを作るという目標を掲げて参加しました。ところが、活動中に母親を亡くすという大きな困難に直面します。
一時は活動を続けることすら難しい状況でしたが、「応援してくれていた母のためにも頑張りたい」という思いから挑戦を続行。結果的に50種類ものレシピを完成させ、文化祭での販売や菓子店でのインターンにまでつなげました。
 2012年受賞者の写真
2012年受賞者の写真
鈴木氏:「彼女は家庭の事情で部活動を辞め、学業の合間に時間を工夫して取り組んでいました。精神的にも、時間の確保の面でも通常では考えられないほど困難な状況だったはずです。そんな困難な状況でも計画を立て、やり抜いた姿は多くの人の心に残りました。」
18年間にわたる生徒の挑戦を見守り続ける鈴木氏の心境は、今も変わりません。
鈴木氏:「毎年、新しい挑戦に出会えることが楽しみです。『今年はどんな子が来るんだろう』と、審査の場に立つと背筋が伸びます。長く関わっていても、常に新鮮な気持ちで向き合えるんです。」
また、生徒たちの本質的な成長の在り方は変わらない一方で、プレゼンテーション能力は年々向上しているといいます。
鈴木氏:「探究学習など、まとめた内容を発表する機会が増えている影響だと思います。初期の頃に比べると、今の生徒たちのプレゼンは本当に上手になっていますね。」
生徒とともに成長を分かち合う――チャレンジカップのこれから
 チャレンジカップHPより
チャレンジカップHPより
こうした実践の機会を広げていくため、尾上氏は「参加する子どもたちの輪を広げてきた」と語ります。
尾上氏:当初は「7つの習慣J®」の受講生が中心でしたが、今では広く門戸を開いています。一人の生徒のチャレンジが周りを動かし、挑戦がまた新たな挑戦を生む「チャレンジの連鎖」が起きるのを目の当たりにしてきました。挑戦そのものが尊いものであると感じ、より多くの子どもたちに参加してもらいたいという想いから、参加対象を広げてきました。」
実際、過去には「7つの習慣J®」の授業を受けていない生徒がグランプリを獲得した例もあり、誰もが挑戦できるオープンなイベントとして広がりつつあります。
一方で、半年間にわたり生徒一人ひとりの挑戦を支えることは、先生方にとって大きな負担でもあります。
鈴木氏:「多少の負担はあります。だからこそ『中途半端にやるなら…』とためらう先生もいらっしゃいます。でも、一度取り組んでみると、生徒の変化や成長に立ち会える喜びは何にも代えがたいものがあります。少しでも興味を持っていただけたら、まずは気軽に参加してみてほしいですね。」

チャレンジカップを経験した学校では、翌年以降も継続して参加するケースが多いといいます。それは、生徒の成長に驚き、先生自身も新たな発見を得るからです。
鈴木氏:「『あの生徒がこんな挑戦をするなんて』『あの生徒にこんな一面があったなんて』と、参加した生徒の成長に驚いたという感想を多くの先生方からいただきました。生徒にとっても、先生にとっても、チャレンジカップは“気づき”の場になっていると思います。」
以前は大きな会場でリアルイベントとして開催されてきたチャレンジカップも、コロナ禍を機にオンラインイベントへと切り替わりました。その影響もあり、尾上氏は大会の規模感が縮小してしまったと感じているそうです。しかし、ここからもう一度、拡大へと舵を切り、子どもたちにチャレンジの尊さを広げていきたいと考えている、と尾上氏は語ります。
尾上氏:子どもたちの挑戦する姿は、私たち大人にも多くの学びを与えてくれます。現在の日本においても、新しいことに挑戦しようとする人が、周囲の目を気にしてしまう場面がまだまだあると感じています。私たちは、誰もが不安なく「やってみたい」と手を挙げられる文化、そして挑戦できない人も挑戦する人を心から応援できる社会を創りたいと考えています。
そうした社会を形成する一助となるような存在にまでチャレンジカップを育てていきたいですね。より多くの方々にこのイベントの認知を広げ、参加する子どもたちを増やし、いつかは武道館で開催したい、そんな大きな夢を描いています。
最後に、尾上氏に導入を検討している学校の先生方に向けてメッセージをもらいました。
尾上氏:チャレンジカップがここまで続いてこられたのは、多くの学習塾や学校関係者の皆様の支えがあったからです。導入を検討されている先生方には、ぜひその一歩を踏み出していただきたいと心から願っています。先生方の伴走は不可欠ですが、子どもたちにとって本当に意義のある大会だと確信しています。
教育機関の最も大切な役割は、子どもたちが社会に出て、自分らしく活躍できる力を育むことだと考えています。変化の激しい現代社会では、言われたことだけをこなす力だけでは不十分です。未知の壁に直面したとき、自ら考え、周囲の力も借りながら乗り越えていく力が不可欠になります。
チャレンジカップは、まさにそのプロセスそのものです。生徒が自ら目標を設定し、試行錯誤しながら壁を乗り越えていく過程が、人間的な成長を促します。先生方が「参加させてみよう」と決断してくださることが、子どもたちの未来を切り拓く大きなきっかけになります。ぜひ、この機会を子どもたちに届けていただきたいと思います。
チャレンジカップのテーマは、「自分史上最高」。生徒が自ら決めた目標に挑み、努力の過程で人として成長する姿は、見守る周囲の心にも大きな変化をもたらします。
挑戦する生徒たちの笑顔と、その一歩を支える大人の想い――18年間変わらない教育への情熱が、チャレンジカップを未来へとつなげています。
チャレンジカップ公式サイト: https://challenge-cup.net/
チャレンジカップ2026プレスリリース: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000338.000029370.html
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ