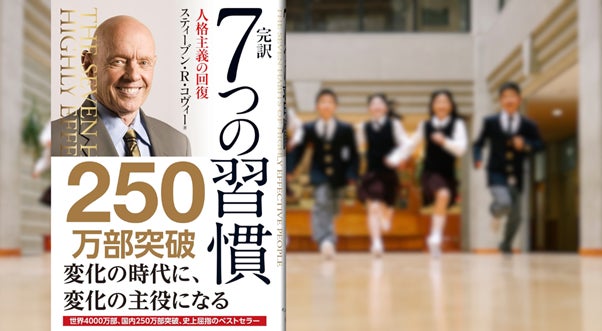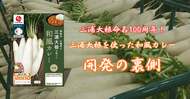「テストの点数だけでは測れない、“生きる力”を子どもたちに」
AIの進化や社会の不確実性が増すなかで、これからの時代を生き抜くために必要な力とは何か。多くの保護者や教育関係者が、その問いと向き合うようになっています。そんな時代のニーズに応える教育プログラムとして、株式会社FCEが提供する「7つの習慣J®」が注目を集めています。
世界的ベストセラー『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー博士著)をベースに、子ども向けに再構築された本プログラムは、すでに日本全国約100校で採用され、これまでに累計36万人以上の子どもたちが学んできました。2005年、岡山学芸館高等学校で学校として日本初導入されてから20年。今や各地の教育現場に深く根づき、子どもたちが自分で考え、自分で動く力を育む土台となっています。
なぜ「7つの習慣J®」は、これほどまで学校の教育現場に根づき、子どもたちの意識や行動、そして学校そのものの文化や風土にまで変化をもたらしてきたのか。その背景には、スキル習得にとどまらない、“人としてどう生きるか”という問いに真正面から向き合い続けた開発者たちの信念と、教育への熱い想いがありました。
今回は、株式会社FCE エデュケーション事業本部 文教事業部で「7つの習慣J®」の推進者であり、数々の学校での導入や運用を支援してきた川村洋行氏にインタビュー。プログラム誕生の裏側から教育現場のリアルな実例、そして未来への展望までを伺いました。
世界中で支持される普遍的原則が子どもたちの「生きる力」を育む
「7つの習慣J®」は、主に小学校、中学校、高等学校、そして専門学校の13歳から18歳の生徒が対象のプログラムです。土台となっているのは、スティーブン・R・コヴィー博士の著書『7つの習慣』。博士は、世界中の文献を研究し、目標を実現している人々に共通する「考え方」を7つの習慣としてまとめました。この考え方は世界共通、不変の成功原則として支持されています。
例えば、7つの習慣®の第1の習慣「主体的である」は、「選択の自由と責任」という原則をもとにしています。人は誰でも、どのような状況でも、なりたい自分、ありたい姿を思い描き、そこに向けて自分自身の言葉や態度、行動を選択する自由があります。しかし、当然、その結果には責任がともないます。それを自覚し、受け入れることから、初めて自分の人生は自分の選択で創られているということに気づき、行動が変わっていきます。また、より良い人間関係を築くためには、自分のWinだけ、もしくは相手のWinだけを考えていてもいけません。常に「自分と相手、双方の“Win-Win”を考えることが重要である」と説いているのが第4の習慣です。
「世界中で5000万部のヒットセラーとして人々に愛読されているのは、普遍的な考え方として多くの人々に受け入れられているからでしょう」と川村氏。
もともと学校のカリキュラムには、子どもたちの非認知能力を伸ばす時間として「総合的な学習の時間」が設定されていましたが、高等学校では必修科目とはされていませんでした。
しかし、新学習指導要領の改訂があり、現在では「総合的な探究の時間」として必修化されています。これらの学習時間の本来の目的は、子どもたちの「生きる力」を高めること。そこに『7つの習慣』をもとにした学習プログラム「7つの習慣J®」がぴったりと合致したのです。
「自分の人生を自分で切り開く力を子どもたちに」という情熱が「7つの習慣J®」を誕生させた
それにしても、なぜ「7つの習慣J®」は、日本で学校教材として作られるようになったのでしょうか。株式会社FCEがこの教材を子どもたちに届けようと決めた、その背景には、子どもたちへの深い想いがありました。
川村氏:もし、子どもの頃から7つの習慣®を学び実践していくことができれば、日本の未来を担う人材の育成に大きく貢献できる。これが、全ての始まりだったと聞いています。
そもそもの始まりは、代表である石川氏が、『7つの習慣』の書籍と出会ったことから始まりました。もしこの考え方を子どもの頃から学ぶことができたら、子どもたちの可能性は大きく広がるのでは、と考えたそうです。
代表の石川が7つの習慣®の研修に参加していた際、同じ研修に参加していた公立小学校の先生から「総合的な学習の時間」を使って7つの習慣®を教えているという話を聞きました。その先生は、フランクリン・コヴィー社の許可を得て、自ら7つの習慣®を実践されていたのです。
子どもたちの授業への参加意識も主体性も段違いで、「一番大切なことを優先する」「Win-Winを考える」といった言葉が当たり前のように交わされていました。そこで石川氏は「学校教育に7つの習慣を取り入れたら、日本の未来に大きく貢献できる」と直感したそうです。
その情熱のまま、アメリカのフランクリン・コヴィー社に赴き、ついに日本で子どもたちに教えるための「7つの習慣J®」のライセンスを取得。7つの習慣®を学校授業として学べるプログラム「7つの習慣J®」が誕生しました。
当時の社会課題も、このプログラムの誕生を後押ししています。
川村氏:当時、社会課題として認識されていたことのひとつに、『一生懸命勉学に励み、立派な大学を卒業した。しかし社会に出て、これまでと違った環境のなかでどうもうまくいかない。思ったような人生になっていかない。』と感じている若者が増えているということがありました。すばらしい学歴を持ちながらも、どこかで人生の選択を誤ってしまうといったニュースも出てきており、学力だけでなく、内面の教育も必要だという考えが広がり始めていた時期だったのです。
教材開発で最も難しかったのは「子どもたちの行動変容があるかどうか」だったと川村氏は振り返ります。そして、教材開発において苦労した点は「どの先生が教えても同じような教育効果が得られる」コンテンツであること。
川村氏:結果を変えるためには、まず行動を変えることが重要です。しかし、行動を変えるためには、そもそもの考え方を変える必要があります。ただ行動を変えるだけでは、一時的には結果がでても、長期的に継続することは難しくなる可能性があります。「7つの習慣J®」が目指したのは、10年経っても、20年経っても、子どもたちが充実した人生を送れることでした。そのためには、行動だけでなく、その根っこにある考え方を変えることにアプローチをする必要がありました。どうすれば子どもたちの考え方が変わり、行動変容につながるかという点は、今も常にブラッシュアップを続けています。時代のニーズに合わせてまさに今年、子どもたちの学び方そのものを変えることにチャレンジをしています。
近年、学習指導要領の改定により、一方的に教える授業ではなく「いかに子どもたちの主体的で対話的な深い学びを引き出すか」が重視されるようになりました。そのため、2025年からは授業の教え方を抜本的に見直したそうです。
川村氏:具体的には50分の授業のうち、これまでは先生の講義が約30分、残りが振り返りの時間だったものを、現在は先生の話す時間を15分程度に短縮。残りの時間を生徒同士の「対話的な学び」に充てるように変更しました。これにより生徒が自ら考え、意見を交わす機会が増え、より深い学びへと繋がるようになっています。
「7つの習慣J®」導入校に共通する本質的な「教育」への眼差し
前列左:PHPのびのび子育て増刊 子どもが伸びる7つの習慣 2014年 10月号(PHP研究所)
前列右:子どもの力をみるみる伸ばす7つの習慣J®(幻冬舎コミックス)
前列中:『完訳 7つの習慣 人格主義の回復 新書サイズ』(FCE/キングベアー出版)
後列:『7つの習慣 賢者のハイライト』シリーズ(FCE/キングベアー出版)
「7つの習慣J®」を導入している学校には、大切にされているいくつかの共通点があるそうです。川村氏は、その中でも特に重要な3つのポイントを挙げてくれました。
川村氏:1つ目は「建学の精神」の具現化です。すべての私学には、創立者が社会にどのような人材を輩出したいのかを考え、志したのか、ということを明文化した「建学の精神」があります。
つまり、多くの私学の目的は「建学の精神の具現化」にあるといえます。それこそが揺るぎない私学の価値になるのです。しかし、それを具現化するということは簡単なことではありません。教員、生徒、保護者にとって共通の認識、そして共通言語化をして浸透させていく必要があります。
FCEでは、それらを強力にサポートする教育プログラムとして「7つの習慣J®」を提案をしているといいます。例えば、Win-Winを考えようと言えば、大人でも、子どもでも、誰でもそれが意味することは理解ができます。「建学の精神」で伝えたいことと7つの習慣®が伝えたいことがぴったりと一致したとき、学校の根幹となる教育になると川村氏は話します。
川村氏:「7つの習慣J®」のご導入校の多くが、教員や生徒さんだけでなく、保護者の皆様が学ぶ機会もつくっています。なぜなら、それこそが「建学の精神の浸透」、つまり私学の使命だと考えるからです。
2つ目は、教員、子どもたちの教育の根本に「考え方」を育むことを据えている点だと川村氏はいいます。故・稲盛和夫氏の「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」という方程式にあるように、どれだけ熱意や能力が高くても、考え方がマイナスであれば、人生の結果もマイナスになってしまいます。
川村氏:7つの習慣®は「成功者の考え方」を研究した結果、導き出されたものです。どの時代、どの場所でも共通する成功のために欠かせない不変の「考え方」を学べるのが「7つの習慣J®」の教育プログラムです。しっかりコマをとって、時間をかけて、習慣化する価値は大いにあると考えています。
そして3つ目は、「教育の2つの側面」を重視している点です。教育の目的には、学力や語学力といった「認知能力」という目に見える部分と、主体性・道徳心・人間性といった「非認知能力」という目に見えない部分があります。「7つの習慣J®」の導入校は、この両方を高めることを大切にしているそうです。
川村氏:どれだけ優れたスキルを持っていても、内面の根っこがしっかりしていなければ長続きしません。逆に根っこが立派でも、スキルがなければ望む結果を出すことは難しいでしょう。だからこそ、この両方を高める教育に力を入れ、生徒一人ひとりの成長を促します。結果として生徒の内面が変わり、行動や態度が変わり、進学実績や部活動での活躍につながり、地域の中で選ばれる学校になっていく..。この20年、そんな学校をいくつも見てきました。
5年後、10年後も“選ばれ続ける私学”になるための学校変革の伴走者でありたい
「7つの習慣J®」を導入した私立学校は、実際にどのような変化を遂げたのでしょうか。川村氏がいくつか具体的な事例を教えてくれました。
川村氏:「7つの習慣J®」を継続されている学校の多くが、目覚ましいご活躍をされています。進学実績が大幅にアップしたり、部活動においても全国優勝など、目覚ましい結果を出している学校もあります。専願率が80%を越えている高校もたくさんあります。
それではなぜ、このような変化が起こるのでしょうか。それは生徒と共に、「7つの習慣J®」を教える教員自身が成長をされているからだと川村氏は話します。
川村氏:教員の成長は、生徒の成長に繋がります。生徒の成長は、教員の自己実現につながります。教員の自己実現は、学校の成長に繋がります。その連鎖が何年にも渡り繰り返されていくのです。当然、学校は見違えるように変わっていきます。それこそが、「7つの習慣J®︎」の本当の価値です。教える教員、教わる生徒、関わる人達、それぞれがWin-Winになっていく。5年後、10年後も選ばれ続ける学校になるために、取り入れるべき教育というのは、そういう教育ではないでしょうか。
「7つの習慣J®︎」では、プログラムを教える先生はファシリテーターとなる研修を受講します。20年で2,000人以上がこの研修を受講したそうです。受講された先生方は10年経っても、20年経っても口々に「あの時、あの研修を受けたから今の自分がある」と話すそうです。先生たち自身が変化し、その変化が授業を通して生徒たちに波及していく循環が生まれているのです。
川村氏:ただし、「7つの習慣J®」は特効薬ではありません。短期的な効果を求めるのなら他にもいろんな方法があります。しかし、5年、10年といった長期的な成長をお考えになるのであれば、とても可能性のある教育プログラムです。教員が変わり、生徒が変わり、やがて学校が変わっていきます。論より証拠。それはご導入校の多くが、全国各地で証明をされています。
「7つの習慣J®」は、導入すればすぐに進学実績アップや、部活動で全国優勝できるといったいわゆる結果を約束するものではありません。表現するなら、建学の精神に基づく校風と生徒を育成するための土台であり、“実現したい学校としての在り方”といった信念を根本から実現するために、長期目線で共に学校の風土を育てていく伴走者なのです。
「成長し続ける学校」を共に創るために試行錯誤の日々。サポート体制と未来への願い
近年、主体性・協調性・責任感・目標達成力といった「非認知能力」が重要視されるようになっています。この流れは「7つの習慣J®」の導入を容易にしているのでしょうか。
「そうとは限りません」と川村氏は語ります。具体的なハードルとして、物理的な「コマ数」の確保と「教員の負担」が生じること。
川村氏:「総合的な探究の時間」の必修化で学校には大きな変化がありました。一つは「コマ数」です。どの学校でも既に何かしらのカリキュラムが組まれています。そのため、「7つの習慣J®」を導入するということは、既存のカリキュラムを大きく見直すことからはじめる必要があります。当然、それには時間がかかります。もう一つは「教員の負担」です。どの学校も例外なく、教員不足で困っていますし、教員一人あたりの負担は20年前よりも大きくなっているのが現状です。
他にも、タブレットやデジタル教材の導入など、保護者に新たな教材費用の負担がかかることも課題として挙げられます。学校変革に取り組みたいのにハードルが高い、と感じる学校経営者の方にもプログラムを届けるため試行錯誤し、2025年4月には「7つの習慣J®」の最も根幹となる要素を体系化した「第1の習慣×セルフコーチング」を開発・リリースしました。実感を得やすく、かつ“考え方”の基礎となる子どもたちの主体性に特化した7コマのプログラムです。
(「第1の習慣×セルフコーチング」に関しては、別の機会に詳しくご紹介いたします)
さらに、学校経営そのものに対するサポートも伴走という形で行っているそうです。保護者向けの「講座」の開催支援や入学式での「7つの習慣J®」のオリエンテーションなども支援の一例です。
川村氏:私たちの願いとして「7つの習慣J®」を学校に導入してもらうことだけに留まらず、導入くださった学校が、成長し続けていくことを大切にしています。そのためには、学校の経営全般にも目を配り、悩みの解決につながるようなサポートが必要です。そのため、お取引のある全国200校以上の学校様から成功事例を集め、それを各学校の経営課題に合わせて情報を提供したり、年に一度、全国の私立学校の経営者が一堂に会する研修会を開催したりなど、さまざまな取り組みを提案しています。
FCEが「7つの習慣J®」の導入を提案する目的は「成長し続ける学校作りに貢献する」ことだと川村氏は強調します。
川村氏:私たちは単なる教材屋ではなく、学校経営の伴走者でありたいと思っています。そのため、目的に到達するための支援を続けていくことを大切にしています。
私学の成長のために。日本の未来を担う子どもたちの幸せのために。

最後に、導入を検討している学校経営者の方へ、川村氏からのメッセージです。
川村氏:少子化が進行し、社会の状況が刻一刻と変化する現代。答えがないと言われるこの時代を、子どもたちはやがて大人になり歩んでいきます。そして、その一人一人の歩みにより、日本の未来がつくられていきます。これからの日本の未来を託された子どもたちに、本当に残していくべき教育とは何でしょうか。私はそれこそが、私学に脈々と受け継がれている建学の精神だと思っています。それを具現化していくことが、子どもたちが「自分の人生を自分の力で切り開く」ということに繋がっていくと考えています。
もし、その想いに共感していただけるのであれば、「7つの習慣J®」は建学の精神の具現化にお役に立てる教育プログラムだと確信しています。ご関心がある学校関係者様は、ぜひ書籍『7つの習慣』を手に取ってみてください。そして、もし共通する点が多々あるとお感じになりましたら、貴校の建学の精神の実現のために、5年後、10年後も選ばれ続ける学校づくりのために、そして、日本の未来を担う子どもたちの幸せのために、「7つの習慣J®」の導入をご検討頂けたら幸いです。
※『7つの習慣』及び「7つの習慣J®」はフランクリン・コヴィー・ジャパン社の登録商標です。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ