高市早苗氏が自民党新総裁に選ばれた。首相に選ばれれば日本初の女性総理が誕生する事になるが、高市外交が本格的に始動すれば、同氏がこれまで示してきた保守的信念がどこまで外交に展示されるかにもよるが、日中関係には変化が生じる可能性がある。

しかし、外交は理想論のみで成立するものではなく、日本経済にとってアジア最大の貿易相手国である中国との関係悪化は、日本企業の事業継続における最大の脅威の一つである。
したがって日本企業は、高市政権下の今後の日中関係の行方について、二つの主要なシナリオと、それらが連鎖的に引き起こす複合的なリスクを深く分析しておく必要があろう。
シナリオ1:現実主義による保守強硬姿勢の「トーンダウン」
一つ目のシナリオは、高市氏が首相という現実の政治的責任を負う中で、外交の安定と国内経済への配慮から、自らの強硬的な信念や姿勢を戦略的に抑制するというものである。
たとえば、日中間の過度な緊張悪化を抑えるため、懸念材料となっている秋の靖国神社参拝を首相在任中は控える、あるいは慎重な対応に転じるなどが想定される。この行動は、中国との間で「緊張を管理しよう」という政治的なシグナルとなり得る。

このシナリオの下では、日中両国ともに関係を「管理可能な状態」に維持しようという意識が高まり、日中経済関係において、中国による報復的な輸出入規制や、日本企業への露骨な事業妨害といった突発的かつ過度な緊張が生じる可能性は比較的低くなる。
企業にとっては、少なくとも政治的な予期せぬリスクが抑制され、中長期的な事業計画やサプライチェーンの最適化を、より安定的な環境の下で進めることが可能となる。これは、一時的な政権交代に伴う混乱を最小限に抑え、日中経済の相互依存関係を温存するので、日本企業にとって最も望ましい形といえよう。
シナリオ2:信念貫徹による関係冷え込みと経済的威圧の強化
一方、高市氏が、自らの強硬的な信念や外交姿勢に「一切の抑えをかけない」という対極のシナリオも想定される。
この場合、中国はこれを「対中強硬派による敵対的行動」とみなし、日中関係が急速に冷え込む恐れが生じる。関係の冷え込みは、単なる政治的言辞の応酬にとどまらず、中国による日本への経済圧力という形で具体化するリスクが高まる。中国はこれまでも、他国に対し、政治的な不満を背景に、輸出入規制、非関税障壁の強化、観光客の制限といった形で「経済的威圧」を行使してきた経緯がある。
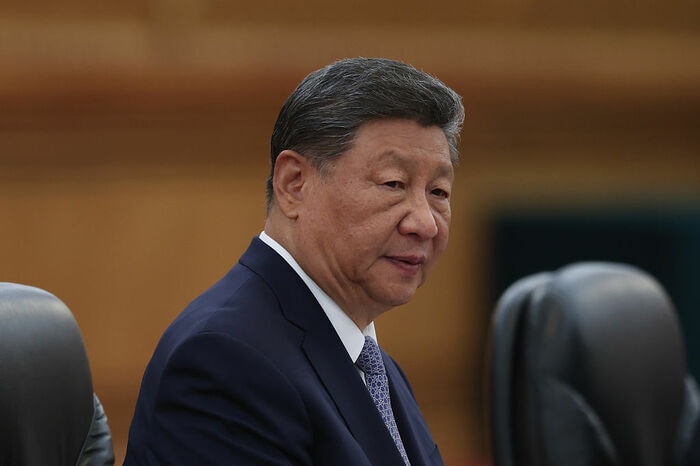
高市政権が強硬姿勢を貫けば、中国は「政治と経済の分離はありえない」という論理で、日本企業に対して報復措置を講じる可能性が高い。具体的には、特定品目の輸出入規制、中国国内の日本企業に対する反スパイ法やデータ安全法などをより厳格に適用した事業活動への高いリスク賦課、さらには国民感情を誘導した不買運動などが考えられる。
このシナリオでは、日本企業は短期間で事業環境が劇的に悪化する「カントリーリスク」に直面することになろう。
複合的リスク:日米連携深化が招く構造的な摩擦拡大
さらに、上記の二つのシナリオのどちらを選んだとしても、日中間の経済的摩擦が構造的に拡大するという第三の複合的なリスクも無視できない。
高市氏は、軍事・防衛だけでなく、経済安全保障分野を含めた多層的な日米関係の深化を掲げる姿勢を堅持しており、これは高市政権の核心的な外交方針として維持されるだろう。

たとえ、高市氏が靖国参拝を見送るなど保守強硬姿勢を外交的に抑制したとしても、「経済安全保障を軸とした日米の結束強化」は継続する。
近年の半導体覇権競争に象徴されるように、米中間の先端技術やサプライチェーンの支配権をめぐる争いは熾烈を極めており、日本が日米の経済安全保障連携を強化し、対中輸出規制や重要技術の囲い込みに加担すれば、中国側の対日不満は強まることになる。
中国から見れば、これは「日本がアメリカ側の対中包囲網の一員として、経済的な主権を侵害しようとしている」と映るためである。その結果、政治的な対立とは無関係に、「経済安全保障」を大義名分とした中国による対抗措置が発動され、日中の経済関係で摩擦が拡大するシナリオもあり得る。
これは、短期的な政治対立のリスクを抑えたとしても、長期的に避けがたい「新冷戦」のような論理であり、日本企業は米中関係を常に天秤にかけて戦略的に考える必要がある。
求められる「米中への過度な依存回避」
高市外交がどの道を進むにせよ、日本企業は、短期的な政権の動きだけでなく、米中対立の構造的な深化という長期的なリスクに直面する。
日中関係の悪化、あるいは日米連携の強化、そのいずれの動きも、中国による経済的威圧やサプライチェーン分断のリスクを不可避的に高める。日本経済にとって中国市場は依然として重要だが、政治的な緊張が事業環境を一夜にして悪化させる現実を直視する必要がある。

したがって、日本企業が不確実性の時代を生き抜くためには、特定の二大大国に過度に依存する構造からの脱却が急務となる。
だからこそ、米中に過度に依存しないサプライチェーンの構築や強靭化、および地政学的なリスクヘッジとしてのグローバルサウス諸国との関係強化が、日本経済の安定と成長にとって極めて重要となるのだ。
【執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】






