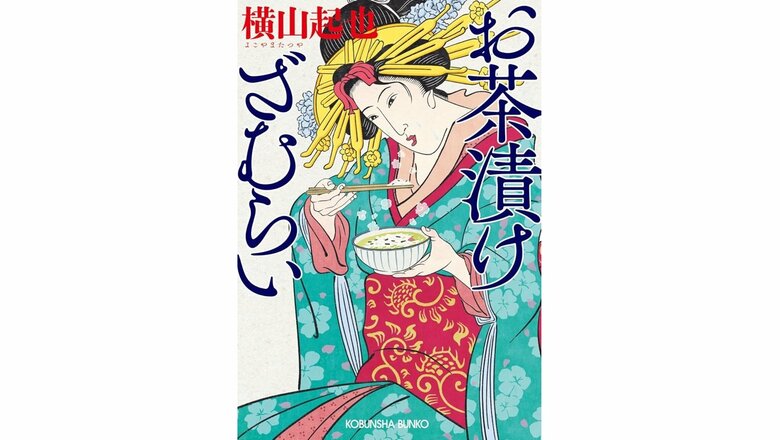未明が相談がてら訪ねた先は
いや、その言い方は正しくないかもしれぬ。
ひょんなことから出会って共に酒を呑む仲がここ数年続いているから未明が勝手にそう思っているだけで、先方はこちらのことを友人と思っているのかどうかもわからぬ。
かなり妙な男なのだ。
「秋の日は釣瓶(つるべ)落とし」とは言い得て妙で、城を出た頃には明るかったのに、ほの青い宵闇が混じりつつある。
湯島の友人の住まう屋敷に行きついて腰の大小をはずし、その戸を開けて「御免」と声をかけてしばらく、 奥から家主が姿を現した。
「……誰かと思えば未明じゃねぇか」
面白くもなげにそう言いながら懐手(ふところで)で顎を撫でている姿が、 まるで芝居役者のようである。
顔貌(がんぼう)は端整にして鋭く、研がれた鑿(のみ)の如し。冷たい三白眼でこちらを見やるその仕草ひとつで、いすくめられる思いがする。
物事を世のなか通りには信じぬ鈍色の光がその眼差しに満ちている。がしかし、女たちはその目配りから色気を感じるらしく、贔屓が引きもきらぬ。少しこけた頬の虚弱な印象も艶となっているらしい。
背の高い痩身を折り曲げながらも、どこか一本筋が通っている立ち姿。齢は弱冠二十と少しにもかかわらず、その佇まいに隙なし。裏返した羽織をぞろりと肩にひっかけたその異装。
血しぶきを浴びたような羽裏模様ばかりがやたらと派手。それでいて風体は荒れておらず、微に入り細をうがち丁寧に行き届いている。