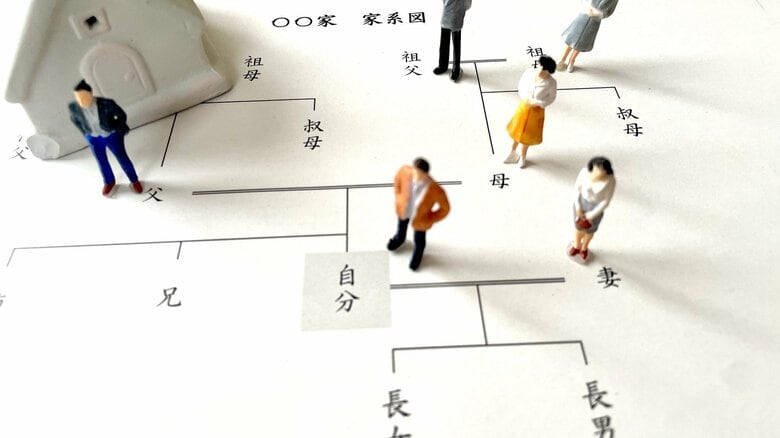居場所が分からない場合の対処法
最終手段としては、裁判所を利用することになりますが、その前にできることはあります。
まずは、相続関係を確定するために戸籍を集める際に、所在が分からない相続人の住所を調べる方法です。具体的には、相続人の「戸籍の附票」というものを取得します。
戸籍の附票は、聞き慣れない言葉だと思います。戸籍と同様に本籍地で発行する証明書で、戸籍が作成されてから今までの住所が記載されています。住所の変遷が分かりますし、現在の住所を確認することもできます。

戸籍関係の取得には、十分に注意を払う必要があります。重要な個人情報ですので、不当に取得した場合には、刑罰の対象となることがあります。
取得は慎重に行わなければなりませんが、相続手続きのために相続人の確定が必要であれば自分以外の相続人の戸籍や附票の取得は可能とされています。住所が分かれば、手紙を出してコンタクトを取っていくことになります。
SNSからたどり着く場合も
少し前までは、過去の年賀状のやり取りで住所が確認できたケースなどもありました。しかし、これだけ年賀状じまいが増えている昨今、そこから手繰っていくのも難しくなっています。同様に、固定電話を持たない家庭が増えているので、携帯の番号が分からないと連絡が難しくなっている現状も相続手続きに影響しています。
その代わりというわけではありませんが、SNSを使って連絡が取れたという事例が多くなっています。筆者もイギリスの方が相続人だった案件で、Facebookでつながることができやり取りをしたこともありました。

最近では、きょうだい間で相続手続きのためのライングループを作り、情報や状況を共有しながらスムーズに最後まで手続きを終えた家族もいらっしゃいました。
SNSは、相続で時に効力を発揮することがあります。しかし、情報漏洩など様々な問題をはらんでいます。やはり、慎重に利用することが望ましいでしょう。