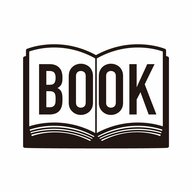自分のことをわかってほしいと話しに来る方もいらっしゃいます。つきあうこともあるのですが、私はそこで聞いた話をたいてい覚えていません。
ある時は一時間にわたって体の具合が悪いという話をしていた人もいました。しばらくは聞かざるをえません。それで一時間ほど辛抱して聞いたうえで、「あなたは今日、最初から最後まで自分の話しかしていませんよ」と言って終わりにしました。

私の書いたことや話したことから、「先生は私のことがわかってくれている」というような声をくださる方もいます。他の人が言わないようなことを書いているからでしょうか。気に入ってくださるのはありがたいことではあるのだけれども、全体としては、かなり誤解があるのではないかと思うのです。
基本的に自分の都合を主張することをとうの昔にやめているので、あまり他人にわかってもらう必要がない。だからといって、誰とでも平等に接することはできない。他人とつきあうにあたって気になるのは、むしろ疲れるかどうかということでしょうか。
相手に無理やり反応を求めるといった人は疲れます。いちいち何かを聞いてくる。もちろん私とは合わないAさんでも、別のBさんとはものすごく合うことはあります。
日常で大事なのは、合うかどうか。夫婦でその相性が悪いと大変でしょう。それは上司と部下、教師と生徒、医者と患者なども同じで、人間関係をうまく続けられるかは、そこが根本になってきます。
なぜかこの人と一緒だと落ち着かないというようなことがある。そうすると日常が安定しないのです。
しかし合わないのは別に自分のせいではありません。また、誰とでもわかりあえるなどと過剰な期待もしないほうがいいでしょう。
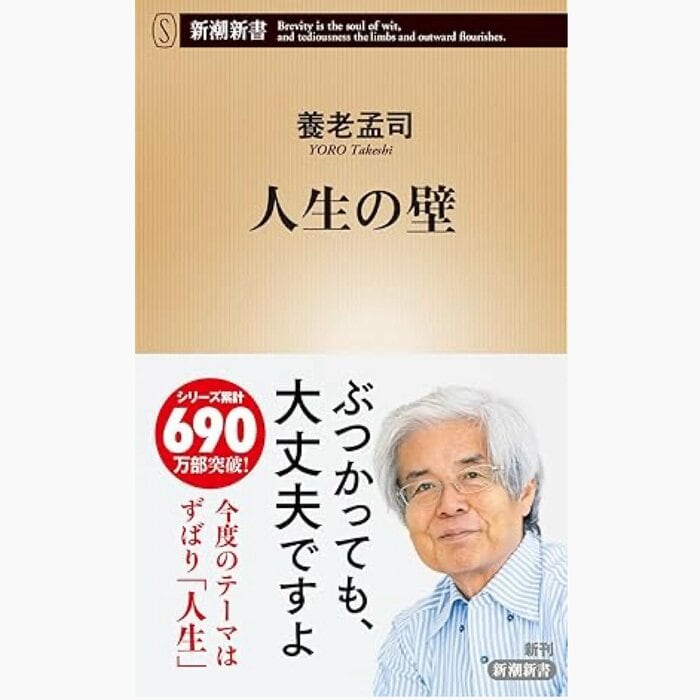
養老孟司
1937年、神奈川県鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒業。専攻は解剖学。東京大学名誉教授、京都国際マンガミュージアム名誉館長。1989年、『からだの見方』(筑摩書房)で、サントリー学芸賞受賞。ほかに、『唯脳論』(青土社/ちくま学芸文庫)、『バカの壁』(新潮新書、毎日出版文化賞受賞)、『養老孟司の大言論(全3巻)』(新潮文庫)、『遺言。』(新潮新書)『バカのものさし』(扶桑社文庫)、『ものがわかるということ』(祥伝社)など多数。