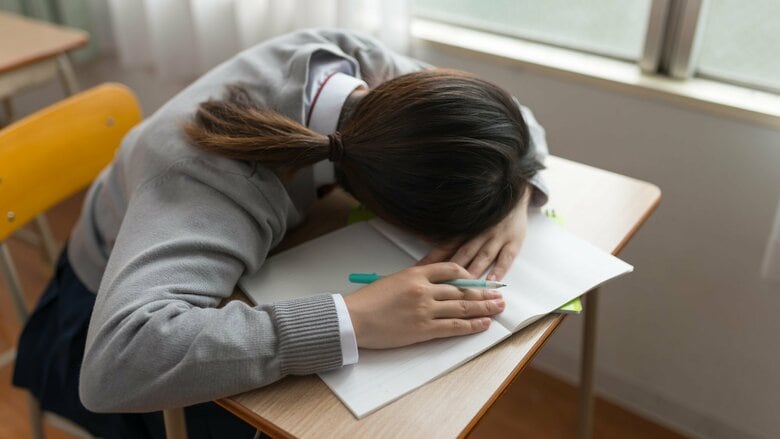生きる上で欠かせない「睡眠」。
しかし、「日本人の睡眠不足や寝溜めの習慣は子ども時代に定着している」という。
作家、科学ジャーナリストの茜灯里さんの著書『ビジネス教養としての最新科学トピックス』(インターナショナル新書)から日本人の睡眠傾向とリスクについて一部抜粋・再編集して紹介する。
近年の日本人の睡眠時間
人生のうち約30%を費やす睡眠。疲労回復に必須なだけでなく、不足すると生活習慣病のリスクが高まったり、ストレスやうつ状態が悪化したりするとされており、心身の健康を保つために欠かせない営みです。
日本人の睡眠は、先進国の中で最も短いことが各種の調査で示されています。けれど、これまでは成人に関する研究ばかりで、子どもの睡眠に対する調査はほとんどありませんでした。
このほどアメリカ睡眠学会のオンライン誌「SLEEP Advances」に発表された日本人の子どもの睡眠習慣に関する調査結果と、近年の日本人の睡眠時間の傾向を見てみましょう。
高校生は「社会的時差ボケ」が起こっている
広島大学の田原優准教授と、早稲田大学・柴田重信研究室、東京工業大学・髙橋将記研究室、ベネッセ教育総合研究所は、全国の小学4年生から高校3年生までの9270人(各学年、男女それぞれ515名)を対象に、「子どもの生活リズムと健康・学習習慣に関する調査」を2021年6月に実施。その結果、子どもの睡眠習慣は、学齢が上がるにつれ、遅寝、遅起きが顕著になることが確認されました。
高校生では、1週間の平均睡眠時間が7時間9分で、日本人全体の平均(7時間22分、OECD〔経済協力開発機構〕の調査〔21年〕)よりも短いことが分かりました。
つまり、睡眠時間の短さは高校生のうちから習慣化していることが示されました。

さらに詳しく見ると、高校3年生の平日の平均睡眠時間は6時間36分と短く、休日は8時間以上と、休日に「寝溜め」をしていることが分かりました。
この原因は、「子どもの夜ふかし」にありました。
調査によると、高校3年生は平日、休日にかかわらず、平均就寝時刻が24時を過ぎていました。平日は学校があるので朝6時半頃に起床せざるを得ず、睡眠不足になります。
そこで休日に長時間寝ることで、平日に溜まった睡眠不足を解消していることが分かりました。
1週間の睡眠不足は、小学生は平日合計1時間程度でしたが、高校生では平日合計2時間半から3時間にまで増えていました。そのために、高校生は「社会的時差ボケ」(平日と休日の生活リズムの時刻差)が平均で1時間を超えており、生活リズムの乱れが目立ちました。
睡眠時間は男女で違う?
また、男女差を見ると、平日には差は見られませんが、女子のほうがより休日に寝溜めしている傾向が見られました。
さらに、平日の起床時間は、学校があるために基本的に学齢や男女による差は少ないと考えられますが、高校生女子は男子や中学生までの女子よりも早起きする傾向がありました。
これは「身だしなみにかける時間」が長くなるからと推測されています。
男女で必要な睡眠時間が違うことは、2016年に英ラフバラー大学睡眠研究センター所長のジム・ホーン教授らが行った調査など、多くの先行研究で示されています。
ホーン教授は「睡眠不足と心理的疲労、抑うつ感、怒りなどとの関連がより強いのは女性で、女性は男性よりも長い睡眠時間が必要」と話しています。

今回の広島大学グループの研究では、子どもでも睡眠不足や社会的時差ボケが精神の健康状態に関連するのか、それは男女差があるのかを検討しています。
「疲れやすい」「いらいらする」といった各質問に対し、「とても感じる」から「まったく感じない」までの4択で回答するアンケート調査では、睡眠不足や社会的時差ボケが大きい人ほど「疲れやすい、いらいらする、気分が落ち込む、昼間に眠くなる」といった精神的な不健康を訴える傾向がありました。
さらに、この傾向は男女共に同じでしたが、女子のほうが睡眠不足や社会的時差ボケとの関連が強いことが示されました。
近年は、規則正しい睡眠習慣の重要性に対する理解が進み、ゲームやネットの過度な使用による子どもの夜ふかしが健康や学業成績に影響することが懸念されています。
この研究では子どもの睡眠不足、特に女子の睡眠不足の悪影響が示唆されました。保護者を含めた睡眠教育で、生活リズムや規則正しい睡眠を早期に伝えることが大切でしょう。
睡眠不足になると健康へ影響?
21年のOECDの調査によると、先進国を中心とする33カ国の中で、日本の睡眠時間はもっとも短く、アメリカとは89分、中国とは100分の差がありました。
日本人の平均睡眠時間の推移は、総務省が1976年から5年ごとに行っている「社会生活基本調査」で見ることができます。
2000年代に入ってから一貫して減少傾向でしたが、最新の令和3年の調査では10歳以上の約19万人の平均睡眠時間は7時間54分で、前回の7時間40分に対して初めて増加傾向に転じました。

ただし、調査では「テレワーク(在宅勤務)をしていた人はしていない人に比べて、睡眠、趣味・娯楽などの時間が長い」という傾向も見られ、コロナ禍での生活様式の変化の影響が示唆されます。
日本人の睡眠時間の減少に歯止めをかけるためには、テレワークが定着するのかなども課題になりそうです。
睡眠不足が健康に悪影響を及ぼすことはよく知られています。
インスリンや成長ホルモンなどの分泌が低下して糖尿病や高血圧が起こりやすくなったり、食欲抑制ホルモンのレプチンの分泌低下と食欲ホルモンのグレリンの分泌増加で肥満しやすくなったりすることが、これまでの研究で確認されています。
さらに、免疫力が低下して炎症反応が起こりやすくなる現象も観察されています。
短くても長くてもリスクがある
もっとも、睡眠時間が短いことは悪いとは言い切れません。
適切な睡眠時間には大きな個人差があり、短い睡眠時間で健康を保てる「短眠者(ショートスリーパー)」も存在します。さらに、近年は「睡眠時間が長いリスク」も注目されています。
全国の住民の健康状態を30年近く追跡調査した「JACC Study」では、約10万人の睡眠時間と総死亡リスクの関係も調べられ、睡眠時間が短いだけでなく、長くても死亡リスクが上がることが分かりました。
7時間睡眠の人の死亡率を1とすると、男性では睡眠時間が4時間以下の人の総死亡リスクは1.3倍になる一方、10時間以上の睡眠でも1.4倍になっていました。女性では、4時間以下で1.3倍、10時間以上で1.6倍でした。

もともと体調がすぐれない人が、長時間、横になっている傾向があることも加味しなければなりませんが、睡眠が長すぎる場合には「睡眠中毒(睡眠慣性)」と呼ばれる症状があることも知られています。
寝すぎたり二度寝をしたりすると、起きた後にかえって眠気が残り、頭がはっきりせず調子が悪くなるという現象です。
この状態で車の運転などをすると、事故のリスクが高まると考えられています。
生まれた時から当たり前にとっている睡眠ですが、自分にとって適切な睡眠時間を知ることが、人生の生活の質を上げるのに重要な要素となりそうです。
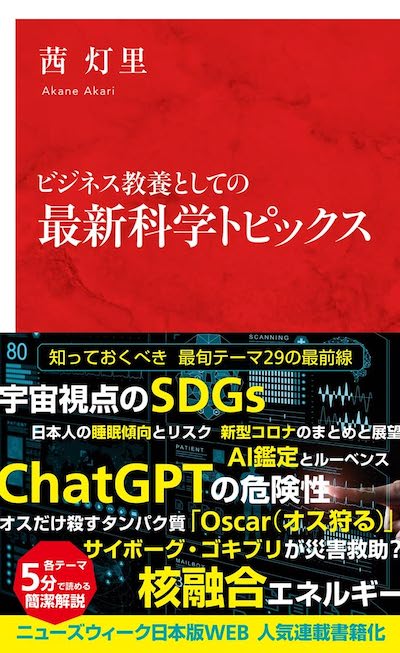
茜灯里
作家・科学ジャーナリスト。著書に第24回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作『馬疫』(光文社)、『地球にじいろ図鑑』(化学同人)など