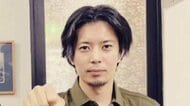長野県軽井沢町の静かな工房で、特別なテディベアが生まれています。それは亡くなった家族の服を着た「お形見ベア」。これまでに約150体が依頼を受けて製作され、深い悲しみの中にいる人々の心に寄り添い続けています。「祖母がいるわけじゃないですけど、また会えたというか」「娘がいてくれた証しです」「主人がそこにいるみたいな気持ちになりました」。小さなぬいぐるみは、なぜこれほどまでに人の心を動かすのでしょうか。
■震災が変えた仕立て職人の人生
シマ・インターナショナル軽井沢ベアーズを営む島邑和之さんが、「お形見ベア」の制作を始めたのは2008年のことでした。
「学校の制服など記念のベアは作っていましたが、お形見のベアの注文があるとは予想もしていませんでした」と振り返る島邑さん。
最初に依頼をした人は、子どもを亡くした自分の姉に、その子のワンピースを着せたベアを贈りたい、と話したといいます。
依頼があった当時、島邑さんは妹をがんで亡くした直後で、両親も早く亡くしていたことから、「人の死に対して近い感覚」があり、妹を悼む思いもあって、制作を引き受けることに。その後は口コミでお形見ベアの注文が入るようになります。
人生の転機となったのは2011年の東日本大震災。もともとスーツの仕立てを生業としていた島邑さんは、卒業式シーズンを前に受注した大量の完成品が岩手の工場から届かず、倒産の危機に立たされます。
その時、「震災で多くの方が亡くなる、そういう光景を目にしたときに、オーダースーツの仕事は他の人もやっているがリメイクベアの仕事は自分にしかできない、と思ったんです」と、当時売り上げの5%しかなかった、「記念」と「お形見」のベアをメインの仕事にしようと決意したのです。
■何か心の拠り所になるものを
神奈川県川崎市の高橋さん(女性 39歳)は、祖母のお形見ベアを作りました。
「私にとって祖母はすごく大切で、母親に相談できないことを話せるような近しい存在でした」
そんな祖母を失った時の喪失感は大きく、「ぽっかり穴が開いた感じ」だったといいます。
お形見ベアを依頼した理由は実家に暮らす母親への心配からでした。
「母は一人だけの親を亡くしたので、何か心の拠り所になるものを残せたらと思ったんです」
ネットで「お形見ベア」にたどり着き、軽井沢ベアーズに依頼。ベアに着せる服は、自分が小さいころよく祖母の家に泊まりに行っていて、実家に送り届けてもらった時に祖母が必ず着ていた服を選びました。
完成したベアを見た母は「本当の形見というか、母はその中で生きているのかな」と笑顔を見せます。
高橋さんも祖母が本当にそこにいると感じると話します。
「ベアが来て気持ちが前向きになったので、今まで挑戦したかったけどできなかったことをやってみようと思って」
英語の勉強を再開。TOEIC受験の目標点を決めて挑戦することにしました。
祖母のベアは今、高橋さんの自宅にあります。2025年、5歳の娘に、祖母のことを覚えておいて欲しいからです。
一緒にいられたのは、亡くなる前のわずかな時間。それでも娘は「おっきいばあば」のことは覚えていると話し、「これからはずっと一緒にいます」と、ベアを愛おしそうに抱きしめます。
■17歳で旅立った娘への想い
群馬県伊勢崎市の斎藤さん夫婦が長女を失ったのは2008年4月のことでした。部活の卓球で県の代表にも選ばれたことがある長女は、特別練習からの帰り道に交通事故に遭い、17歳の若い命を奪われました。
「自分の中では時間が止まったまま」と母は心境を語ります。
お形見ベアのことは知人に聞き、通っていた高校の制服と、卓球の大事な試合では必ず着た「勝負服」のユニフォームで作りました。
「卓球を一生懸命頑張っていた姿を残したい」
出来上がったベアを見た瞬間、娘だと思ったそうです。
「ベアの存在自体が、娘がいてくれた証し。いつも一緒にいる感じです」
父も、「本当は、制服もユニフォームも見たくても見られない。でもベアがいることで、見られるし、卓球や勉強や友達との情景を思い出すことができる」と話します。
■夫のベアと交わす毎日の会話
軽井沢ベアーズの島邑さんは、2024年、不慮の事故で右目を失い、左目も視力低下が進んでいて、将来に不安を感じています。
普段、ベアを渡したあと、依頼者に再び会うことはあまりありませんが、仕事が続けられなくなる前にどうしても会いたい人がいました。
早くに亡くした自分の母親がなんとなく重なるという、新潟県十日町市の山本さん(女性76歳)です。
山本さんは10年ほど前に、父、そして夫を相次いで亡くしました。
「父の時はすごく泣きました。主人の時は悲しすぎて涙も出ませんでした。あんまり悲しいと涙って出ないんですね」
お形見ベアのことはテレビで偶然知り、「自分にぴったり」と思って、依頼したといいます。
雪のある日、新潟県十日町市の山本さんを訪ねた島邑さん。4年ぶりの再会です。
元気に暮らす様子に安堵する島邑さんに、山本さんはベアとの日常を話します。それはまるで夫がそこにいるかのようです。
「ベアはお父さん(ご主人)の代わりだから、普段はソファにいて、ご飯のときは食卓に行って、一緒に食べて。この年になると医者通いも仕事の一つ。そういう時も、じゃあ行ってくるねとか言ってね。帰ってきて、ただいま、また明日も元気でやろうねとかって、話しかけています」
山本さんの家を後にした島邑さんは、「やっと会いたい人に会えた。クマちゃんと今も仲良く暮らしていただいている。そのことに私はパワーを頂いて、また頑張っていけそうです」と話します。
■無念の思いを胸に
横浜市の佐藤さん(女性59歳)は、産婦人科医としてクリニックを営んでいた夫を、がんで亡くしました。
「主人が亡くなった直後は、何もできなかった自分の無力感、罪悪感とか申し訳なさとかの気持ちが強くて、悲しくて悲しくてという毎日だった」と振り返ります。
しかし、お形見ベアとの暮らしの中で、徐々に心境が変化します。
「主人はおそらく精一杯生きたし、やりたいことは全部やっていけたんじゃないか、そういう気持ちが強くなってきて、主人の死を受け止めることができました」
夫は「重複がん」で命を落としました。重複がんは、あるがんの治療後に別の部位に新たながんが発生するもので、診療科が異なるために発見が遅れてしまうケースも少なくないとされます。
夫は、医師でありながらそれに気づけなかったことを悔やみ、重複がんの知識があまり知られていない現状から、新聞社などに記事執筆を呼び掛けるなど啓もう活動に力を入れていました。
佐藤さんは、助産師として夫と一緒に働いていたクリニックで今も働いています。
夫が亡くなって1年ほど休養した後、再び仕事に戻るにあたり、夫の想いを受け継いで患者に接していこうと決めました。
「主人は自分と同じ悔しい思いをする人が一人でも減って欲しいと願っていましたので、患者さんの体調の変化とかを早く気づいて差し上げて、検査につなげていただきたいという思いで、日々頑張って診療しています」
■再出発の日々をお形見ベアとともに
「グリーフケア」という言葉が注目されています。家族など大切な人を病気や事故で失った深い悲しみを抱える人への、心の支援を指します。
関西学院大学教授の坂口幸弘さんは「死別という体験は誰もがいずれは経験する。その悲しみやつらさが非常に長引いたり重篤になると、うつ病などの心のリスクもあり、そうならないような支援が必要」と語ります。
お形見ベアについては、「亡くなった方との繋がりは続いていく。残された者の心の拠り所になる点では、お形見ベアもグリーフケアとしての役割を果たしている」と評価します。
高齢化に伴う多死社会化は進み、亡くなる人の数は2040年頃にピークを迎えるとされています。別れと向き合う場面も増えるといえ、それとともにグリーフケアの重要性もより高まっていくのではないでしょうか。
最愛の家族を失う大きな悲しみを背負った人たちは、再出発の日々をお形見ベアとともに過ごし、ベアに、そして周りの人たちに力をもらいながら、確かな希望の毎日を歩み続けています。
〔この記事は、NBS長野放送で2025年9月26日に放送した「NBSフォーカス∞信州 いってくるね。クマちゃんのグリーフケア」をもとに構成しています〕