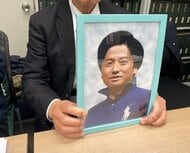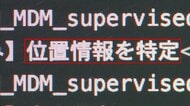“見えないナッツ”のリスク
対応が急がれているのが、外食や、量り売り店で提供される中食(なかしょく)の場におけるアレルギー対策だ。ナッツ類は、粉末状やペースト状にして目に見えない形で含まれていることもあり、知らぬ間に摂取してしまうリスクがある。
外食・中食は事業規模や営業形態が幅広いうえ、提供される商品が多岐にわたるが、食物アレルギーに関する情報提供が義務付けられていない。
原材料が頻繁に変わることや、原材料の意図しない混入(コンタミネーション)を防止するため、調理の場を食材によって切り分けることが難しいためだ。
表示制度の整備と啓発進む…
政府は対応を強化している。
厚生労働省は2017年の「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」で、「関係業界と連携し、実行可能性にも配慮しながら、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進する」と定めた。
事業者向けには、食物アレルギー表示の基礎や実際に取り組む際のポイントを示し、患者向けには、店舗利用の際に気をつけるポイントなどを幅広く学べるよう、パンフレットや動画制作などを通じて普及啓発を行っている。

消費者庁はアレルギー患者団体向けの実態調査を行っていて、2025年度中にとりまとめる予定だ。
消費者庁幹部は「自主的にメニュー表示を行う事業者は増えていると認識している。そうした最新の民間事業者の動きや患者・関係者の声を把握したうえで今後の対策を検討したい」と話す。