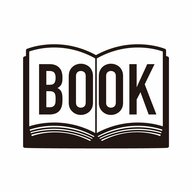この子はもしかしたら何かの拍子に来年死ぬかもしれない。そんな気持ちがあれば子どもを大切にするのは自然なことでしょう。
実際に子どもを亡くした経験を持つ親も多かったのです。そういう人は他人の子どもにも寛容になります。
子どもは大人の予備軍ではない
子どもがいつ死ぬかわからないと思えば、いまのうちに好きに遊ばせてあげようと思うようになるのが自然です。その気持ちは想像できるでしょう。
いまは子どもの時期について、大人になるための貯金をする時期のように考えている人が多いのではないでしょうか。いま頑張っておけば、がまんしておけば、将来いいことがあるぞ、というリクツで子どもに無理をさせる。

すべては将来のための投資、という考え方です。子どもを大人の予備軍としか見ていません。
コロナ禍の時期、子どもたちにずっとマスクをさせることになったのは記憶に新しいところですが、その時のリクツと、この「予備軍」のリクツは少し似ています。
健康のためにはがまんしろ、おじいちゃんおばあちゃんに感染させないために、いまはがまんしろ。すべては将来のため、不安をなくすため。しかし、もしも来年にはこの子が死ぬかもしれないと想像して、それでもあれこれ強いるでしょうか。もっといまの時期を楽しんでほしいと考えるほうが自然でしょう。
将来のためにがまんしろ、先にはいいことがあるぞというのは、子ども時代そのものに価値を置いていないということです。
子どもには子どもの人生があり、その毎日がとても大切なものだと考える。これが子どもを大切にする基本なのではないでしょうか。
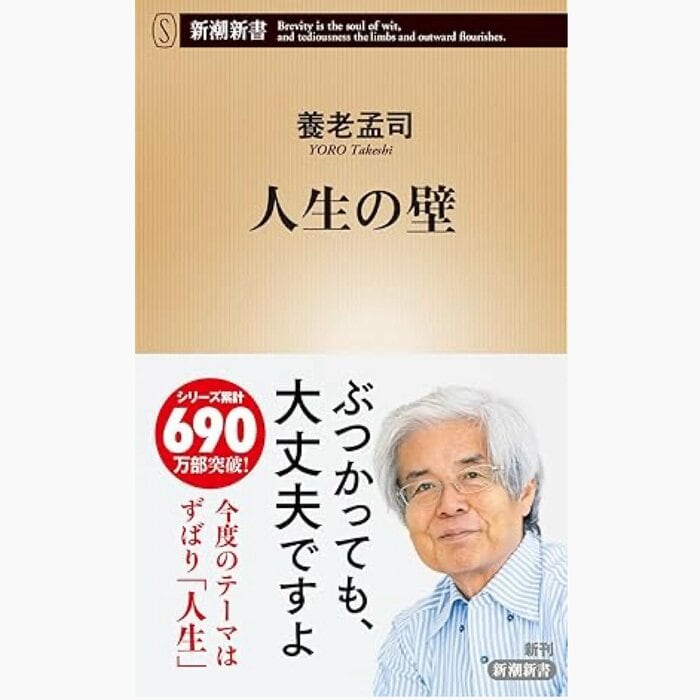
養老孟司
1937年、神奈川県鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒業。専攻は解剖学。東京大学名誉教授、京都国際マンガミュージアム名誉館長。1989年、『からだの見方』(筑摩書房)で、サントリー学芸賞受賞。ほかに、『唯脳論』(青土社/ちくま学芸文庫)、『バカの壁』(新潮新書、毎日出版文化賞受賞)、『養老孟司の大言論(全3巻)』(新潮文庫)、『遺言。』(新潮新書)『バカのものさし』(扶桑社文庫)、『ものがわかるということ』(祥伝社)など多数。「壁」シリーズは累計700万部を超えた。大の虫好きとしても知られ、鎌倉の建長寺に虫塚を建立し、毎年法要を行っている。