在京テレビ局や新聞社などが加盟する日本新聞協会は2020年6月、メディアスクラム防止のために現場で記者が代表を決めて取材をすることなどを掲げた申し合わせを公表しました。これは実名が事実の核心であり、正確な報道に不可欠であるというメディアの考え方を理解してもらうには、実名報道を拒否する一因ともなっているメディアスクラム対策により一層、取り組むことが必要だと考えたからです。
(参考記事:メディアスクラム防止のための申し合わせを公表…京アニ放火殺人事件や川崎児童殺傷事件など受け)
昨年5月に川崎市多摩区で発生した小学生児童ら20人殺傷事件の被害者遺族の取材は、この申し合わせを策定する事例のひとつとなりました。担当記者の報告です。
「現場記者からの発案」
昨年5月、神奈川県川崎市の登戸駅近くで当時51歳の男がスクールバスを待っていた私立カリタス小学校の児童の列に刃物を持って襲いかかり、小学6年生の女子児童と保護者が死亡し、18人が重軽傷を負った。襲いかかった男はその場で自殺した。

亡くなった女子児童の自宅に到着するとすでにテレビ、新聞などの記者やカメラが集まっていた。先に取材をしていた同僚の記者によると被害児童の父親は少し前に自宅から出たが、各社の取材には応じなかったということだった。
私が最初に思ったことは「これではたとえ話したくても話せないのではないか」ということだった。目の前には自宅前に待機する総勢10数社のメディアの記者やカメラマン。このままではもし遺族が「何か話したい」と考えていたとしても話せる状況ではないし、なにより遺族の気持ちを考えれば応じてもらえるかもわからない。
そんな状況の中でメディアが取り囲むのは逆効果以外の何物でもないと感じた。現場にいた他社の記者らにも同じような思いがあり、次のような対応がまとまった。
(1)新聞1社、テレビ1社で声掛けを行い取材の可否を確認する。
(2)取材が可能であれば近くで待機する各社を呼ぶが、無理なら呼ばずコメントなどを取り各社と共有する。
協議の結果、テレビと新聞からそれぞれ代表を出すことになり、私と新聞社の記者2人が自宅近くにとどまり、ほかの記者やカメラマンはいったん退いた。
まもなく父親が帰ってきたので、2人で声をかけた。名刺を差し出して「短時間でいいのでお話を伺えませんか」と問いかけると「今の状況では話せない。ただ早めに何らか対応しないといけないと思っている。落ち着いたら記者クラブを通じてコメントは出すつもりなのでそれを待ってもらえないか」と応じてもらった。そして足早に家の中に入っていった。
こう話してくれた父親にこれ以上お願いすることはできないと思った。「記者クラブを通じてコメントを出す」との回答を共有し、これ以上とどまってもご家族への負担になるのでその日は撤収することで各社合意した。
翌日、「本来であれば、取材にお応えし、我々の気持ちをお話しすべきところですが、今は全く気持ちの整理がつかない状態で、失ったもののあまりの大きさと深い悲しみに打ちひしがれています」というコメントが神奈川県警記者クラブに寄せられた。

「思いを馳せること」
数日後、関係者の出入りの可能性があるため女子児童の自宅付近で取材をしていた際、被害にあった女子児童のご遺体が自宅に戻ってきた。
そこにはメディアの記者が5社ほどいて、最初は状況が分からず各記者はデジカムで撮影していたが、棺には納められておらず葬儀会社とみられる人にストレッチャーで運ばれ、自宅に袋を抱えられて入っていった。
撮影の後、「今の映像を使いますか?私は使わないように社に伝えます」と他社の記者に聞くと皆も同じ思いを持っていたようで、各記者が本社に電話で説明してこの映像が使われることはなかった。
なぜ使わなかったのか。それは被害者に対し思いを馳せた結果だろう。現場にいた記者は全員被害者のことを思ったはずだ。そして被害者の遺族のことも。記者の被害者への考え方が変わり、それが共通の認識になりつつある表れだと思う。
「記者に必要なもの」
昨年5月、都内の老人ホームで入所者の男性が職員に暴行され死亡した事件の取材では、被害者の娘がインタビューに応じてくれた。その中で「お父さんの無念を晴らしたい。その手助けになるなら答えられる範囲で答える」と時折涙を流しながら語ってくれた。
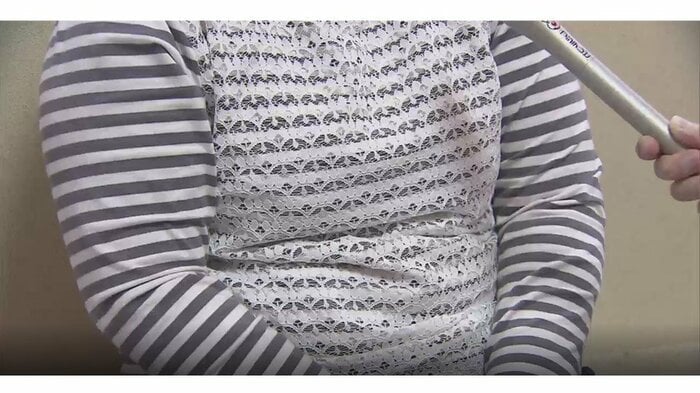
このように無念の思いを世に伝えてほしいという被害者もいる。その被害者の声を届けるために被害者の元に向かわなければならない。

取材現場では各社の自由な取材が前提だが、特に被害者取材でメディアスクラムが発生するような状況では各社で協議した上で、取材相手への負担を減らす取り組みが行われるようになっている。
それは過去に問題になった取材手法からの脱却と時代の変化に合わせたものといえるだろう。この「モラル」は当たり前のことといわれるかもしれないが、それが当たり前でなかったことにより様々な問題が起きてきた。
この「記者のモラル」がどう浸透していくか、また取材にどう活かしていくかは我々が日々考えなければならないことであるし、一方で相手のことを考えすぎたがために萎縮した取材になってもならない。いつも被害者のことを心に留めながら事実に迫る取材を続けていくことが必要だと思っている。
(執筆:フジテレビ社会部 山﨑康平記者)





