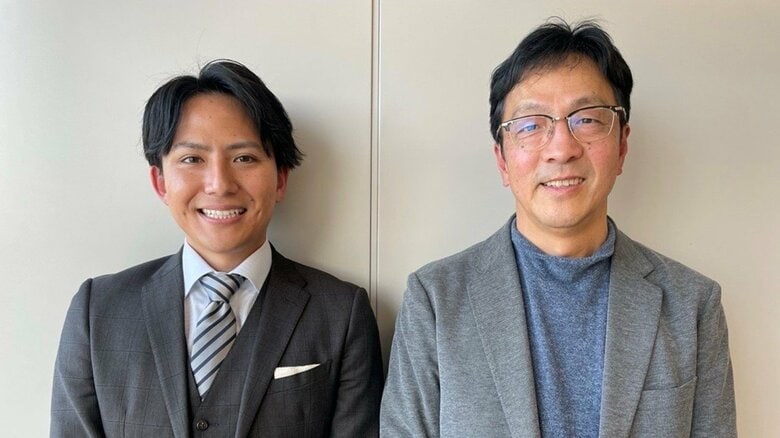「国際女性デー」が制定されている3月にあわせ、フジテレビのアナウンサーが自分の視点でテーマを設定し取材し、「自分ごと」として発信します。
2024年2回目の担当は安宅晃樹アナウンサーです。
近年、ジェンダー平等実現のため様々な制度改革やイベントが行われ、女性が産休・育休を経て、子育てをしながら職場復帰できる環境は整いつつある。
一方で、私も3歳の息子を育てる身として感じるのが、依然として進まない“男性”目線での男女共同参画だ。
“働くママ”だけでなく、“育てるパパ”も暮らしやすい社会にしていくには何が必要なのだろうか?そして、真の意味でのジェンダー平等とは何なのだろうか?NPOファザーリング・ジャパン理事、企業経営者、そして「元祖イクボス」と呼ばれている川島高之氏に話を伺った。
子どもと一緒にいるだけで不審者扱い

――川島さんが現役で子育てをされていた時代は、もっと男女格差の大きい時代だったわけですよね?私も日々、保育園の送り迎えを行っていますが、朝の送りはパパがいても、お迎えでパパが来ている姿はほとんど見ることがありません。
NPOファザーリング・ジャパン理事 川島高之氏:
私は26年前に子どもが生まれて、その頃は朝の保育園の送りですら、パパは私だけでした。平日の昼間に公園やスーパーに子連れで行こうものなら不審者扱いをされたくらいです(笑)。
そういう時代でしたので、仕事をする上でもやはり男女の格差は大きかったです。私は、総合商社に勤務していたので国内含め世界中の方と何度も商談の場を経験してきましたが、日本の場合、私の目の前の席、つまり意思決定者の席に女性が座ることは数える程しかなかった。
一方で、海外では、かなりの頻度で女性が目の前にいるか、目の前に男性が座っていたとしても、その隣、ナンバー2の席には女性がいることが多かったです。

――なぜ日本では、そうした構図が生まれやすいのですか
川島氏:
一番は、これまでの「意思決定者=男性」の既得権益の意識が大きいと思います。
「オールド・ボーイズ・ネットワーク(男性中心の組織文化や人間関係のこと)」という言葉があるんですが、簡単に言うと“楽”なんですよ。
私も今年還暦を迎える身として分かる部分もあるのですが、それは趣味やプライベートの世界では問題ないことだが、その“楽さ”を仕事の世界にも持って来ていることが一番の問題だと思います。

川島氏:
実はこの言葉自体は、欧米にも同じようにあるんです。でも、「それではだめだ」ということでクオータ制など法律で規制されたり、訴訟になって負けたりして、変わってきたんです。
だから、欧米が進んでいるというより、変化を余儀なくさせられてきたという部分もあるので、日本もこれからしっかり変わっていくことは出来ると思います。
川島氏の常套句は「MBAよりPTA」
――川島さんは他のコミュニティにも進んで入っていったのでしょうか
川島氏:
私は仕事と子育ての合間に、少年野球の監督、PTAの会長、NPOの代表などを担い、積極的に仕事以外のコミュニティに参加してきました。
その経験から、ワーク(しごと:報酬を得る仕事)、ライフ(私ごと:家事・育児・親・趣味・勉強など自分や家族のこと)、ソーシャル(社会ごと:地域活動・ボランティア・NPOなど)という3つの世界(居場所)を持つことが、非常に有意義だと思っています。

川島氏:
例えば、ダイバーシティな職場は強くて業績も良いと言われるように、個人の中でもダイバーシティが必要なんです。何か新しいものを生み出すには異なる分野を掛け算するというのが基本動作ですが、ワーク・ライフ・ソーシャルという3箇所に居場所を持っていれば、自分ひとりの頭の中で容易に掛け算が成立する、つまり新しいことを生み出せる人財になれるんです。
また、PTAやNPOなどのソーシャル活動が、組織を運営するマネジメント能力を鍛えてくれます。
「MBAよりPTA」は私の常套句です。他にも色々と理由はありますが、いずれにせよ働き盛りの男性にも極力ライフとソーシャル部分を大切にすることで、結果的に仕事の成果や能力も高まると思いますし、逆に子育てなどライフでの経験を持っている女性は、それを強みにして仕事でも活かして欲しいなと思います。
権利主張するには職責を
――「そうできるのであればそうしたいが、現実はそうはいかない」「パパも子育てにもっと注力したいのに、どうしても家庭にコミットせず仕事に没頭する人の方が評価されやすいのではないか」という悩みがあるのですが
川島氏:
仰る通りで、そうは簡単にいっていないから、日本のジェンダーギャップ指数が146カ国中125位なんでしょうね。大切なのは、上司と部下の双方が歩み寄り、変わっていくことだと思います。
まずは部下。つまり、いま子育て真っ盛りの世代は、堂々と自分の意思を上司に主張していいと思います。ただ、気をつけなければならないのが、「権利主張する前に職責を果たそう」という覚悟を持つことです。
「男性だって育児のために早く帰る権利があるんだ」という主張は正論なのですが、その主張をするには、自らに課された職責を全うし、会社にコミットしなければならない。権利主張だけだと自分が気がつかないうちに「既得権益者・ぶらさがり型」の部下に成り下がってしまう可能性が高いし、そういう部下が多い組織は「ゆるい職場」になってしまい業績が下がるでしょう。
つまり個人にとっても組織にとってもマイナスしかないです。だからこそ、私は誰よりも生産性を高めることに徹してきました。

川島氏:
“生産性=仕事の成果/仕事の時間”だと考え、普通に働いている人が1=1/1だとすると、子育てをしながらだと、残業ができなかったり、子どもの発熱などで休まなければならない日もあったりして、どうしても分母は0.7くらいになってしまう。そこで分子も0.7になってしまうとダメで、じゃあ1だったらいいのかというと、それでもダメなんだと気づいたんです。
だって、他の人は休日出勤や残業もしているのに、こっちは早く帰ったりしているので。分子が同じ1で、分母が1と0.7の人間がいると、やはりいつも目の前で働いている人間が評価されるのは仕方がないんです。
だからこそ、分子は1.4くらいにしなければならない。そうすると、1.4/0.7ということで、1/1より生産性は2倍になるんですよね。かける時間を1/2にする、かけた時間に対して成果を2倍にするなど「生産性倍増」のつもりで、仕事に集中しまくるのです。

川島氏:
結果的に成果が出なかったとしても、その姿勢を周りの人たちは評価してくれるので主張も認められるようになるんです。これは子育てに限らず、介護であったり趣味であったり、何でも同じだと思います。
今の時代だからこそ求められる「イクボス」とは?
――一方、育児する男性を応援する組織にするために、上司としてどんな歩み寄りが必要でしょうか
川島氏:
まず何が問題なのか整理すると、いまの上司世代の男性に子育てを経験してきた人が少ないので、“どこにどう気を遣えば良いか分からない”ということだと思います。
仕事と違って子育てというのは、コスパもタイパもなく、ある種、合理性を考えられない仕事ですよね。365日24時間対応で、なおかつ責任者は自分であるという大変さがある。一方で、これほどまでに楽しいことはないと思うんです。
そうしたことを知らない「24時間働けますか」という時代を生き抜いてきた人たちが部長や社長になっているのですから、子育ての大変さを分からないのはしょうがないと思います。ただ、やはり時代も変わってきたので、上司も変わっていかなければならない。そこで私は、管理職や経営者時代に意識してきたことを、イクボスの定義と10ヶ条にまとめあげ、世に出しました。
その後約10年間、「イクボス生みの親」としてNPO法人ファザーリング・ジャパンでの活動を通じてイクボス普及に務めています。

――「イクボス」という言葉の定義を改めて教えてください
川島氏:
「育児」と「上司(ボス)」を組み合わせた造語なのですが、以下3つの定義を満たす(目指している)経営者・管理職・上司のことです。
① 部下の私生活と仕事をともに応援
② ワーク・ライフ・ソーシャルを自らも満喫
③ 組織の目標達成に強い責任感
簡単に言うと、“経営者や上司が多様な働き方を理解し、時間や場所に制約のある人間でも働きやすく働き甲斐があり、生産性の高い職場になるようマネジメントしていこう”ということです。
制約というのは、何も子育てに限りませんから、まずは部下が何を大切にしているのかを上司が知っていくというところが大きな一歩ですね。働くママだからと言って「子育てがあるから早く帰りな」というのは、これも古い価値観からくる一種の偏見で、もしかしたら「もっと仕事に没頭したいのに」と思っている女性もいるかもしれませんからね。
現在イクボス企業同盟に260を超える企業が加盟してくれているので、この輪がもっと広がればいいなと思っています。

――子育て世代としても、会社がイクボスを宣言しているのは非常に心強いですね。最後に川島さんの思う「真のジェンダー平等」とはどんなものでしょうか
川島氏:
男性・女性・ワーク・ライフ・ソーシャル(WLS)全てが、同じテーブルに乗って扱えるようになるといいですよね。これまでは、男性=仕事、女性=家庭となって天秤にすらかけられなかった部分を、それぞれの価値観に基づいて、やりたいことをやれる社会になるのが真のジェンダー平等じゃないかなと思います。
WLSの3軸という話を先程しましたけど、本人の意思に基づいて、仕事一本、子育て一本の人だっていていいんですよ。それもダイバーシティの一つなんです。決して皆が同じバランスになる必要はなくて、全ての価値観を受容し、社会の一員として共に歩んでいくことがダイバーシティと言えるんだと思います。そして、今しかできないことを優先するというのもとても大事。

川島氏:
WLSのバランスは、人生を通して常に同じである必要はなくて、例えば「今は子育て中心」みたいにその時にしか出来ないことに比重を置きつつ人生設計していくと考えれば、安宅さんのような悩みのある方もスッキリすると思います。子育てを楽しむ権利は性別に関わらず、すべての人にありますからね。子育てを楽しんでください。
“育てるパパ”が当たり前な世の中を夢見て
これまでの私は、自分の中の軸が確立していなかった。もっと正確に言うと、軸はあるものの、周囲の声や評価を気にして、自分の軸を貫き通す覚悟がなかったと思う。
今回、川島氏の話を伺い“悩みの根幹”に気づくことができた。
ワーク・ライフ・ソーシャルのバランスは人生を通して取ればいい。
今しかできないことを大切に。
スッと肩の荷が下りた気がした。
(取材・文/フジテレビアナウンサー 安宅晃樹)
「ジェンダーについて、自分ごとを語る」
2023年に続き、フジテレビアナウンス室では、アナウンサーが自主的に企画を立ち上げ、取材し、発信します。
「私のモヤモヤ、もしかしたら社会課題かも…」まずは言葉にしてみることから始める。
#国際女性デーだから
性別にとらわれず、私にとっての「自分ごと」、話し合ってみる機会にしてみませんか。