不安やつらさなどメンタルの不調を抱えているときは誰にでもある。
そんなとき、すべてが“自分のせい”だと考えてしまうことはないだろうか。
アスリートたちが日々実践するメンタルを守るための方法を取り上げている、プロフェッショナルコーチ・坂井伸一郎さんの著書『メンタルトレーニング大全』(アルク)。
今回は、環境が変わって不安になったときの心得を一部抜粋・再編集して紹介する。
「自分」ではなく「環境」が原因の場合も
メンタルの不調を抱えているとき、自分を責めてしまうことは、さらに自分を追い込んでしまいます。
どんなことも、自分だけに100%原因があるということはありません。
とはいえ、自分以外にも原因があると考え出すと、今度は自分ではない誰かのせいだと考えてしまいがちです。

もちろんその可能性もゼロではありませんが、それ以外にも原因は考えられます。自分自身でも他者でもない、それは「環境」です。
時間の経過とともに、社会は変わっていきます。時代の変化は環境を変え、さらには世の中の生活スタイルや価値観、常識を変えていきます。
環境の変化は止められるものではありませんが、多くの人は変わることに負担やしんどさを感じます。
そんなとき、アスリートはどのようにしてメンタルを整えていくのか。2つの方法があります。
変化の中身を“具体的”に考えてみる
1つ目は「具体をいち早くつかむ」ことです。
「何だか不安」と感じるときには、環境の変化を意識することから始めましょう。何がどう変化しているのか、変化の具体的な内容がわかってくると、それだけでも気持ちは少し落ち着きます。
例えば、スポーツの世界では道具やウエアの使用ルール、禁止薬物のルール、試合進行のルールなど、さまざまなルールが頻繁に変わります。
新しい状況はアスリートにとっても非常に不安なもの。「これでよかったっけ?」「急にそんなことを言われても…」とフラストレーションが生まれます。
準備してきたことの効果が薄れるかもしれない、初めての状況にすぐ適応して試合を戦えるのか、という不安は恐怖に繋がります。
そのため、違いを認識したら漠然と受け止めるのではなく、「何がどう変わったのか」「どれくらいの差異があるのか」をすぐに理解することから行います。
変化の内容がわかると、表面的なことだけではなく、変化の背景や理由にまで意識が向くようになります。
すると、次の変化も予想しやすくなります。予想する力が高まると、また次の新たな変化へ準備する力が備わってきます。
変化に怒らず一度、受け入れてみる
2つ目は「急な変化でも腹を立てない」ことです。
今までは問題なかったことが急にNGになることもあります。
スポーツに限らず、トランプゲームの「大富豪」でも2上がりや8切り、都落ちなど、一緒にゲームをするメンバーやその場の雰囲気によってルールが変わることはあります。

そこでいちいちルールにあらがったり、「それならやらない!」と完全に拒否する人はいないですよね。
いつもと違う場面や状況にすぐ腹を立てたり、1つ1つに疑問を持っていては、自分のメンタルも疲弊します。
深刻な事案や誰かに危害が加わることでなければ、まずは一旦受け入れてみるのはどうでしょう。どんなことも変わって当たり前、変化しないものは世の中にないのです。
メンタルを整える過程で、どうしてもつまずいてしまうこともあります。それは「過去にこだわる」ことです。
以前のルールや従来の常識、習慣、方法など、過去に親しんだものは手放すのが難しいものです。経験してきたことにはたくさんの「わかっている」が詰まっているので、安心できます。
でも過去とは、今や未来をよくするために生かすもの。
周りの人も自分も現在を生きているのに、自分だけが過去を引きずっていては、周囲との目線が揃わなくなります。周囲は違和感を感じるでしょうし、その違和感は自分にも伝わってくるでしょう。
「過去から何を学んだか」ということに目を向け、「その過去を、これからどう生かしたいか」と自分に問いかけてみるのがいいと思います。目線は自分の足元からその先へ移しましょう。
「一番よかったときの自分」は基準にしない
アスリートにとって「イメージを持つ」ことは重要です。
イメージづくりをして練習や試合に臨むものですが、このときにやってしまいがちなのが「過去、一番よかったときの自分」を基準にすること。
過去から学ぶこと自体は悪くありません。ただ、そのイメージのなかにいる「過去の自分」と「現在の自分」が同じわけではありません。
当時と今では筋肉量が異なるでしょうし、関節の柔軟性や可動域も同じとは限りません。当時使っていた道具や、ホームとするスタジアムやフィールドの環境も異なる可能性があります。ルールでさえも、過去とは完全に一致しないかもしれません。
体調も状況も環境も、完全に揃うということはないのですが、それにもかかわらず、無意識のうちに「過去、一番よかったときの自分」が頭のなかにずっと住み続けてしまうケースを見かけます。
過去の自分を追いかけても現在の自分は苦しくなるばかりなので、「一番よかったとき」を基準にするのはお勧めしません。
また、過去の理想的な環境にこだわることは、現在の自分を追い詰めます。「環境が変わった。では、次に自分はどうするか」と切り替える潔さも必要なのです。
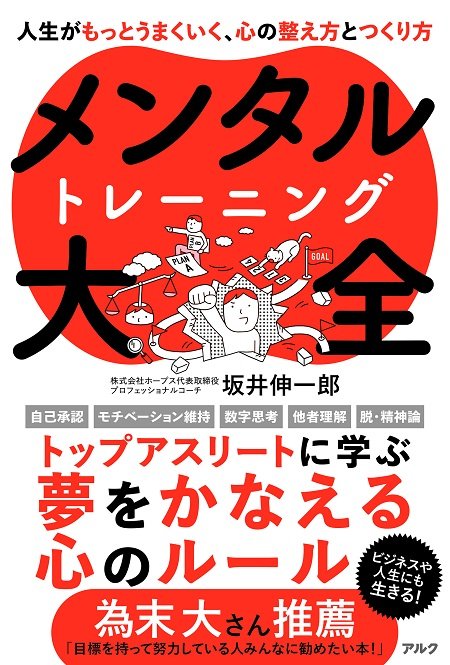
坂井伸一郎
株式会社ホープス代表取締役。プロフェッショナルコーチ(ACC、CPCC)。株式会社高島屋、ベンチャー企業役員を経て2011年に独立起業。現在はプロスポーツ選手やトップアスリートに向けた座学研修を行う会社を経営。自らも講師として年間1000名を超えるアスリートに座学指導を行っている。専門領域はマインドセット・アスリートリテラシー・チームビルディングなど






