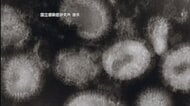「危機的な感染状況が続いている」
「今週の新規陽性者数は、連休中の休診による検査数の減少、検査報告の遅延等の影響を受けた可能性があるため、注意が必要であります」 東京都の新型コロナウイルスモニタリング会議では新規感染者の7日間平均が前回の1万7686人から、1万4564人に減り、増加比も、減少傾向を示す0・82倍なった。
ただ、このままの0・82 倍で減っていったとしても、1 週間後の 2月24日の新規感染者数はおよそ1万1942人との推計が出された。 国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、連休や検査の遅延が影響した可能性もある、として現状について「危機的な感染状況が続いている」とクギをさした。

リバウンドに向かうリスクが
「ここで人々の接触機会が増えると、新規感染者数が十分に減少しないまま、リバウンドに向かうリスクがあります」 夜の繁華街の滞留人口は、昨年末の高い水準から43.3%減。居住地から3km圏内で生活を完結するステイホーム率も50% を超えているが、東京都医学総合研究所 の西田淳志社会健康医学研究センターセンター長はリバウンドの可能性にもふれ、「ピークアウトがけっしてゴールではない」とクギをさした。

重症者は今後さらに増加も
「重症患者数は、新規陽性者数よりも遅れて増加し、その影響が長引くことに警戒する必要があります」 医療提供体制については、先週と同じく都民のおよそ80人に1人が検査で感染が確認され入院、宿泊、自宅のいずれかで療養中で、重症者数は先週から4割弱増えた81人になったとのことだった。
入院患者のうち酸素投与が必要な方の割合は、先週の14・4%から、25・8%に上昇、東京都医師会の猪口正孝副会長は、感染者の中の高齢者割合が増えていることが「かなり影響している」として今後も酸素投与が必要な患者が増える、との見方を示した。

高齢者の3回目接種がカギ
「40%ラインに到達するときの今後の感染状況をしっかりと見極めていきたいと思います」 都内の高齢者で3回目の接種をすませたのは33・7%で、東京 iCDC専門家ボードの賀来満夫座長は今後も1日当たり2%ぐらいずつ増えていく、との見通しを示した。
オミクロン株とは感染予防効果が異なるが、としたうえで、デルタ株の時は高齢者のワクチン接種率が40%に達したあたりから重症者数や感染者数がかなり低下したので今後の推移を注視する、と話した。
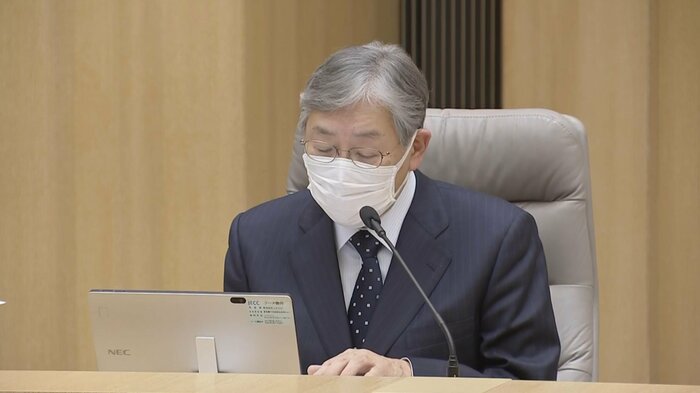
ステルスオミクロン 都内初の市中感染
「BA.2が今後、市中感染が広がっている状況になるのかならないのか、早く見極めていきたい」 さらに賀来座長は、海外の一部地域で拡大しているいわゆるステルスオミクロン株「BA.2」の市中感染が東京都内で初めて確認されたことを明らかにした。
都の検査では「BA.2」が去年12月に1件、今年に入って1月に5件、2月に1件見つかっていて、1月に見つかった5件のうちの2件が海外リンクなし、いわゆる市中感染だったという。
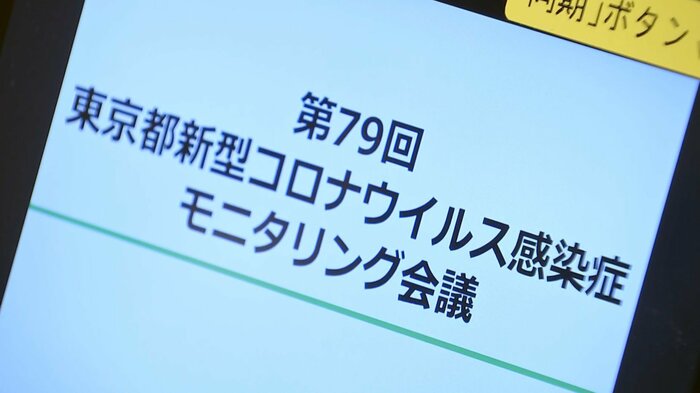
都は、12月と1月はゲノム解析で確認されたが、2月に入ってからのは東京都独自の「BA.2」に対応した変異株スクリーニングPCR検査で確認。 「BA.2」は国内で主流となっているオミクロン株と比べて感染力が強いと見られていて、専門家からは感染拡大に懸念の声もあがっている。
感染者減“実感”は4月
「東京都の感染者が減ったと実感できるのは4月に入ってからだと思う。3月中はそこまでまだ下がりきらない」 ある都の関係者は、今後の見通しをこう話した。 下がりきらない感染者数を抱えて、社会を回していくためには、水際での検査と停留の徹底が非常に重要となるだろう。 本当のウイズコロナとなれるのか、この年度末で明暗がはっきりするのかもしれない。
(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)