拙速なワクチン開発は危険
「治療薬と異なり、ワクチンは健常な人にも接種する。そして、効果が継続するよう設計されている。従って、ワクチンが異常を生じさせるかもしれないリスクが予防効果を上回るようなことがあってはならない。」
「既存のワクチンの副作用もゼロではないが、実用化前に安全性を十分に確かめる努力は為されてきた。新型コロナウイルスのワクチン開発も慎重に進めなければならない。」
ウイルス学が専門の獨協医科大学・増田道明教授は常々こう言っている。
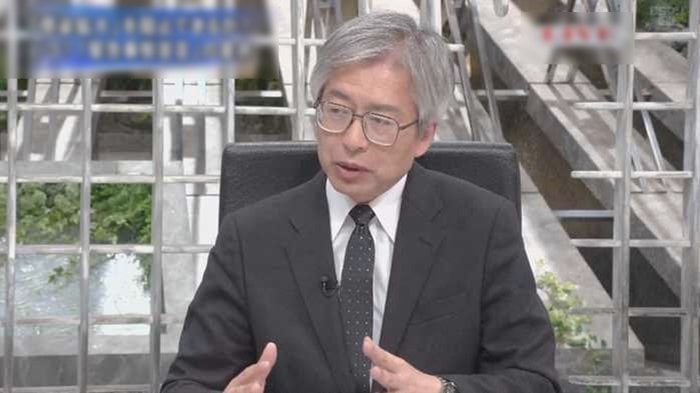
医学・医療の観点からは常識中の常識ということなのだろう。「天然痘の撲滅などワクチンが人類にもたらした福音は大きい」とはいえ、拙速なワクチン開発は危険でもあるとのことらしい。
ファイザー社が開発中の新型コロナウイルスワクチンが、臨床試験で90%超の確率で感染を予防する効果が確認できた、というのは筆者には間違いなく朗報に聞こえる。
これを受けアメリカの株式市場が急騰したのに象徴されるが、新型コロナウイルスに“有効なワクチン”の登場を人類は首を長くして待っている。
未だわからないことが多い
しかし、このワクチンは、まだ実用化されたことが一度もないmRNAワクチンというタイプで、まだわからないことも多いという。(注・末尾に追記あり)
まず副作用・副反応についてである。
ファイザー社はこれまでのところ重大な懸念は生じていないと言うが、せいぜい数か月という短期的な観察結果である。長期的な副作用についてはまだ分からない。4万人以上の被験者を対象とした臨床試験とはいえ、10万人に1人というような稀な副作用についてはわからない。例えば、重大なアレルギー反応が起こるのか、起こるとすればどの程度の頻度なのか、まだはっきりしないらしい。
次に、効果・効能についてである。
90%超の確率で感染を予防できるというが、そもそも感染自体を防げるのか、感染しても発症するのを防げるのか、発症しても重症化を防げるのか、重症化しても命を救えるのか、具体的なところはまだ示されていない。2回接種することが必要のようだが、その後いつまで効果が持続するのかも不明である。
さらに、「抗体依存性感染増強」の有無もはっきりしていない。
通常、ワクチンを接種してできた抗体は、我々を感染症から守ってくれる。しかし、ウイルスによっては、抗体が存在すると却って感染力を増す場合がある。例えば、デングウイルスは日本でも2014年に問題となったが、それに対して開発されたワクチンが一時期東南アジアなどで使われた。しかし、このワクチンは「抗体依存性感染増強」のリスクが認められ、使用が制限されている状況だという。
検証可能な形でのデータ共有が大事
増田教授は「そもそも新型コロナウイルスのワクチンについては、学会発表や論文に先行して、部分的な情報だけが流布するのが昨今の風潮になっている。科学的視点から検証可能な形でデータや情報の共有が行われることが望ましい。」と今回の発表について述べている。
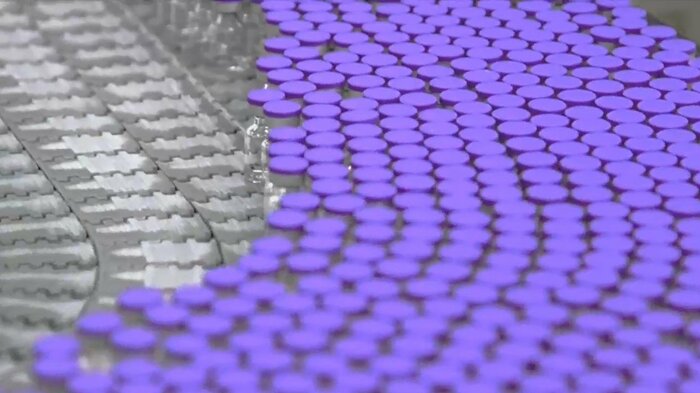
例えば、ファイザーは、これまでのところ、年齢階層別の有効性までは発表していないという。英・ガーディアン紙は「一般的にワクチンは高齢者になればなるほど効きが悪くなる傾向がある」が、この点の詳細はファイザーの新たな発表を待たなければわからないと報じている。
また、90%超に有効というが、残る10%弱の人々にそうでないのは何故かも明らかになっていないとガーディアン紙は指摘している。単なる確率の問題なのか、効かない人に何か共通点があるのか、これらについても発表を待つ必要があるという。
現在のワクチン開発を巡る状況について、増田教授は「新型コロナウイルスは世界に甚大な影響をもたらしており、ワクチンの実用化は人類全体の切なる願いであることはよく理解できる。mRNAワクチンの有効性を否定できないのも事実である。しかし、その効果や安全性を科学的にしっかり確かめることも大切で、特に何十億人もが接種するかもしれないワクチンならなおさらである。科学的客観性とは相入れない事情を優先して、拙速な実用化が進められるようなことがあってはならないと思う」と強調している。
繰り返すが、期待は大きい。
不明の点のいくつかは、遠からず出されるであろう詳細な発表によって明らかになると思われる。ファイザーが予定通り承認申請をすれば来月にも接種が始められるとの見通しをアメリカのアザー厚生長官は示したというから、期待が一層高まるのもやむを得ないと思う。
しかし、断片的な情報で一喜一憂せず、開発途上の過度の楽観は最後まで禁物ということを実際には肝に銘じるのが大切なようだ。
(追記)増田教授によれば、ウイルスに対する従来のワクチンは、
・弱毒化したウイルスを生きたまま使うもの(麻疹など)
・ウイルスをホルマリン処理し感染性を失わせたもの(ポリオなど)
・ウイルスを分解してタンパクを精製したもの(インフルエンザなど)
・ウイルスタンパクを遺伝子工学の手法で製造したもの(B型肝炎など)
のいずれかである。どれもウイルスのタンパクを含んでおり、それがヒトの免疫反応を促す。しかし、今回のワクチンはmRNAワクチンというタイプである。これは、タンパクの設計図となるmRNAという物質を接種して、ヒトの体内でウイルスタンパクを作らせようとするワクチンである。
ファイザーが開発中のものは超低温(マイナス70℃)で輸送・保管する必要があるとされる。そうだとすれば、実際に接種するという話になった時、日本でも一般開業医では取り扱いが難しく、ロジスティック上の大問題が生じる可能性があるという。
【執筆:フジテレビ 解説委員 二関吉郎】
【表紙画像:ファイザー社提供】






