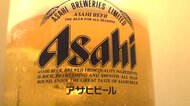6日にノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学特任教授の坂口志文さんが、生中継で「イット!」に出演しました。
SPキャスター・山口真由氏:
先生の会見を拝見していて、私は継続する力と決断する力に非常に感銘を受けました。40年継続されたのはもちろんですけれども、1つの論文を契機に当時の大学をやめて愛知県のがんセンターに移るのはかなりの決断だったと思うんです。研究者に必要な資質について何かアドバイスありますか?
大阪大学特任教授・坂口志文さん:
平凡なアドバイスになりますが、研究を続けていくという時には、自分の興味がまず最初にあって、それを持続していくというか、続けていくうちに興味自体がどんどん強いもの、あるいは形が少し変わってより現実的になり、より豊かなものになっていくとそういうことだと思います。その間には、いろんな人との出会いもあるかと思いますし、他の人の新しい発見もあります。そういうものを合わせてだんだん自分の興味というのが形を作っていってその成果が出ていく。大体はそういうコースをたどるんだと思います。
青井実キャスター:
坂口さんご自身が研究を続けてこられた力というか、そういったものはどういうところから湧いてこられたんでしょうか?
大阪大学特任教授・坂口志文さん:
私の場合には研究を始める当初に、免疫系というのは自分を守るだけではなくて自分を攻撃するという不思議な現象ですので、この二面性ですね。その裏にあるような制御のメカニズムというのが知りたかったと。そこの興味を持続できた、また制御性T細胞に関しましては研究の初期から携わること関与することができて、今日まで来たというようなことです。それが私たちにとってはある意味ラッキーなことだったと思います。
宮司愛海キャスター:
制御性T細胞に関してですが、がんやアレルギーの発症を抑える予防・治療への活用の応用が期待されています。具体的にがんについては注目度が高いと思いますが、どのような予防や治療ができるんでしょうか?
大阪大学特任教授・坂口志文さん:
現実的に臨床試験が進んでいますのは、制御性T細胞というのはがん組織に非常にたくさんいます。免疫反応を抑えているんですね。それを何とか抗体薬とかで減らしてやれば現在のがんの免疫療法がもっと効果的になるんじゃないかということが1つです。もう1つは進行したがんじゃなくてもっと初期のがん、例えば、がんと診断された時からとにかく免疫反応を上げる。そうしますと、将来ひょっとして転移とか起こる可能性があるんですが、もしそういうような確率を減らすことができれば、今のがんで亡くなる方の90%はがんの転移で亡くなります。その転移が90%が半分になったと免疫力を上げることによって、そうすると半分のがんの患者さんを救うことになります。がんが、ひとところにずっととどまっている限りは怖い病気じゃありませんので、そういうような次の段階、次の新しい初期のがんに対するがん免疫療法、そういうものがこれから進展してくるんだと思います。
青井実キャスター:
近い将来とは大体、どれぐらいと私たちは考えればよろしいのでしょうか?
大阪大学特任教授・坂口志文さん:
今、言いましたような治療法は10年以内には実現できる。それくらいのスピード感で前に進めるだけかと思います。また、がんの免疫療法アレルギーや何かを抑えること。そういうものも20年以内の間には、普通のお医者さんにかかられた時に治療法の1つになっておると。そういう時代になるのを期待しております。
東京歯科大学市川総合病院・寺嶋毅教授:
ご自身が発見された制御性T細胞が、すごく膨らみというか幅広く広がったり、あるいは臨床の現場でがん免疫であるとか、そういうところに応用されている感触があるんですが、ご自身も臨床に結び付くなと思われた何かタイミングとか出来事はございましたか?
大阪大学特任教授・坂口志文さん:
私たちはマウスを使っていわゆる基礎研究でこういう制御性T細胞などを発見してきたわけでありますが、免疫学というのはすぐにワクチンとか、がんの免疫療法もそうですが人の疾患とすぐに結びつく学問です。その意味で定年に近くなったころから最後は人にどれだけ応用できるかどれだけ治療に寄与できるか、そういうことを考え出してそれから今日に至っているということになります。
宮司愛海キャスター:
研究費の話をきのうの会見の中で阿部文科相にされていましたが、日本の研究費はアメリカの4分の1程度ということで、研究費に関しての提言などございますか?
大阪大学特任教授・坂口志文さん:
ガソリンがなきゃ車が動かないように、どこに行くにしてもそういう意味では日本が科学立国で英語を目指す以上は、今の状況というのは少し寂しいように思います。それは免疫学に限らず、いろんな分野で皆さんの意見を聞きますともう少し何とかならないだろうかというのはよく聞く話です。他の国と比べて少し低すぎるんじゃないかということで、日本の経済が良かったころは低い率でありましても総額としては良かったんですが今、経済もこういう状況ですと少し寂しいように思います。
青井実キャスター:
日本でもたくさん研究者の方がきっと頑張られているわけですが今回、坂口さんが受賞することになった意義・意味どのように感じていますか?
大阪大学特任教授・坂口志文さん:
やはり今、研究費用の話がありましたが、それプラス研究者、広くいろんな人がいろんな研究をしてその中で面白い成果が出た時にはそのサポートを少し濃くしてあげるとか、あるいは研究者のポストも任期制にして全て競争させるだけじゃなく何が本当にいいのかを考えてほしいとは思っております。
7日はスタジオに東京歯科大学市川総合病院の寺嶋毅さんにも来ていただきました。
青井実キャスター:
寺嶋さん、どうお話を聞きました?
東京歯科大学市川総合病院・寺嶋毅教授:
最後にありましたが、医師あるいは研究者にとって研究する環境はどんどん金銭的環境が厳しくなっていますから、そういう中でモチベーションを高めるような明るいニュースというかそういうきっかけになったんじゃないかと思います。
青井実キャスター:
山口さん、そういう意味では、たとえ短期間で結果が出なくても役に立たないから批判するんじゃなくて、検討を重ねて夢を持つ若者に含めてメッセージを出すことが必要ですよね。
SPキャスター・山口真由氏:
私がもう1つ思ったのは、基礎研究に通じて坂口先生は創薬ベンチャー創業者としての顔もお持ちですよね。日本初の技術が2025年3月にアメリカに移したという話があります。創薬の市場に投入するのがアメリカのほうが早いというのもあって、そこの研究と企業のエコシステムも必要なのかなと思いました。
宮司愛海キャスター:
政府としてはどんなことが支援できると思いますか?
SPキャスター・山口真由氏:
政府との駆け引きも大事ですが、坂口先生は財団とか民間の資金がアメリカが非常に多かったとお話をされていて、民間の役割も考えたほうがいいのかなと思いました。
青井実キャスター:
寺嶋さん、今回の受賞ですが、医師を志す方や研究をされる方にも影響って非常に大きいですか?
東京歯科大学市川総合病院・寺嶋毅教授:
例えば免疫、おっしゃられたようにいい役割、行き過ぎとか免疫ってとても微妙だったりいろんな役割を持っているので、改めて体の仕組みはとても面白いなということで興味を持ったり、医学とかそういう方面に進む人が増えてくれるとまたいいと思います。見習いたいというか、研究ってつらい時期もあったり、でもこうやって成果というのは皆さんに明るい光になるのかなと思います。