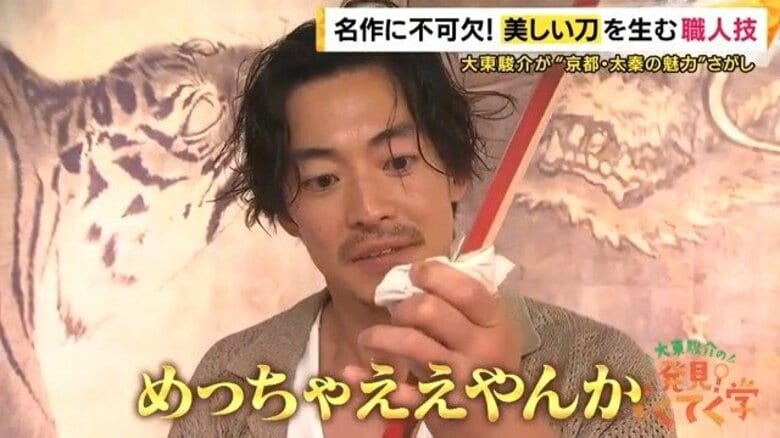俳優の大東駿介さんが、訪れた街のうんちくや、まだ地元住民にも知られていないような魅力を探す「発見!てくてく学」。
今回の舞台は京都市の太秦(うずまさ)です。
京都の太秦は、日本映画の歴史と共に歩んできた特別な場所です。
1926年に名優・阪東妻三郎がこの地に撮影所を開設したことをきっかけに、数多くの撮影所が生まれ、「日本のハリウッド」と呼ばれるようになりました。
【大東駿介さん】「俳優をやらせてもらってると京都で撮影するんですけど、本当に長い時は3カ月くらい京都でいて、ここ『通勤の道』です」
今回は大東さんが太秦で、時代劇の撮影の裏側に迫ります!
■東映太秦映画村はことしで開村50周年
最初に訪れたのは、「東映太秦映画村」。
ことしでオープン50周年を迎える国内初の映画テーマパークです。
まるで江戸時代にタイムスリップしたようなリアルな没入体験ができると、国内外を問わず幅広い層から人気を集めています。
来春には新エリアもオープン予定です。
映画村には、実際の時代劇などの撮影も行われているからこその「驚きの仕掛け」がたくさんあるそうなんです!
【大東駿介さん】「映画村に隣接して撮影所があるんです。先輩の古田新太さんに会って、『仕事終わったし、飲みに行こか』って言われてそのままここ(映画村)で飲んだ」
大東さんにとっても思い出深い映画村。
俳優をしながらガイドも務める小畠徳子さんの案内で、撮影の裏側を探っていきます。
■池落ちシーンの秘密!スターが落ちるときは…
映画村を歩いていると、急に見えてきたのが、恐竜!?
池に浮かんでいるのは名物、「江戸港町の恐竜」です。
【小畠さん】「48歳くらいです。そのとき特撮が流行ってたみたいで…」
この池は時代劇でおなじみの「“池落ち”シーン」に使われるそうです。
ここには意外な「裏話」がありました。
【小畠さん】「大物俳優の方がドボンってなると、ちょっとここは話が変わります。水を一旦抜く。電動ブラシでこすって綺麗な水を用意する」
【大東駿介さん】「“スター専用池”に変わるわけですね!でも、なかなか(大物ではない)中ぐらいの人悩みますね。どの境目で磨こうかっていうね」
ただ、透き通った水だと恐竜が見えてしまうため、「入浴剤」で色付けしたりもするそうなんです。
また、池に落ちる役者には「水はまり手当」が出ることも!
【小畠さん】「夏は『少々ええやろ』という感じですが、冬は『(寒いから)かわいそう』ということでちょっと上げてもらえる」
■映画村のなりたちと無限の組み合わせを生み出すセット
元々は撮影所のセットを1日だけ市民に開放したのが始まりだった映画村。
1日で2万人もの来場者が訪れ、反響を受けて半年後に正式オープン。
なんと3日間で7万人以上の来場者を記録し、その収益を使って新たな作品を生み出していったのです。
映画村には意外なセットの秘密も。
セットの壁ですが…よく見ると、下に「車輪」が付いています。
撮影所の敷地は限られているため、セットを移動させることでさまざまなロケーションを生み出せるのです。
【大東駿介さん】「おもしろ!これで町並みが変わる。路地を作れる。プロの美術さん、大道具さんがこういう風に作ってるというわけですね」
■時代劇支える「斬られ役」は緻密な計算と技術の賜物
続いて大東さんが向かったのは、映画村に隣接する東映京都撮影所。
11棟のスタジオがあり、大ヒット中の映画「国宝」の一部の撮影もここで行われたんです。
ここには時代劇に欠かせない「斬られ役」と呼ばれる専門の役者がいます。
1952年に発足した東映剣(つるぎ)会は、殺陣(たて)のプロ集団。
彼らの技術がなければ、時代劇のリアルな斬り合いシーンは成立しません。
【大東駿介さん】「殺陣師はどういったお仕事なんですか?」
【東映剣会会長・殺陣師 清家三彦さん】「基本的にはアクション、剣劇であったりとかっていうそういうシーンであったり場面のふりをつけていくのが、殺陣師の仕事」
【大東駿介さん】「武道なんですけど、何が違うかっていうとそれが映像に特化しているというところが大きな点で、例えば、刀って実際に斬るわけじゃないじゃないですか。カメラがどのアングルにいて、どこだったら斬られているように見えるかとか本当に繊細な作業」
角度によっては、実際には体に当たっていない「バレる斬り方」となってしまうので、うまく相手の体を利用して、本当に斬っているように見える「バレない斬り方」をするのが大切なんだそうです。
役柄、シチュエーションだけでなくカメラの位置まで計算されているのです。
■大東さんも「斬られ役」に挑戦!
【大東駿介さん】「斬る側の強さとかどれだけシーンが緊迫しているかは『斬られ役』にかかっている」
実際に、清家さんと「斬られ役」の佐々木さんの殺陣を見せてもらいました。
【清家三彦さん】「どうぞ斬ってくださいとやってると面白みのない動きになる」
【大東駿介さん】『「斬られ役」のリアクションで剣筋がどう通っているか分かる。映画をそういう目線で見ていただくと、まるで見方が変わる!殺陣のシーンあっという間に過ぎていくじゃないですか?そのあっという間の一瞬が、スローにしてお酒飲めるぐらい技量が詰まってる」
せっかくなので、大東さんも「斬られ役」に挑戦!!
最初は「できるもんじゃないから」と断っていましたが、始まると、さすが役者!
息遣いや顔の表情で斬られた痛みを表現しましたが…
【清家三彦さん】「長い!よくある!」
尺が長すぎました…。
■「水戸黄門の印籠」を作った小道具店
最後に大東さんが訪れたのは、時代劇や現代劇で使用される小道具・美術品を取り扱う「高津商会」。
水戸黄門で使われた印籠や銭形平次の投げ銭など、数々の小道具で名作を支えてきました。
前身は1897年ごろに開業した古道具店で、100年以上前の本物の甲冑などを揃えていたのです。
職人の出嶋英和さんに小道具を紹介してもらいます。
【出嶋英和さん】「うちの倉庫は普通の学校の体育館が5つぐらい。そこにぎっしり、30万~40万点ぐらいの道具が入ってます」
この規模は全国でも2社だけなんだそうです!
■時代劇の「刀」は“卵の白身”でできていた
高津商会では本物の刀は使えないため、他の美術品に負けないクオリティの刀を作り出しています。
刀作りを担当する職人の引田清人さんに、その技を教えてもらいました。
まず木製の刀身に下地材を塗り、その上に厚さ0.1ミリ以下のスズを使った金属箔を貼り付けます。
さらに意外だったのは、金属箔を貼り付ける接着剤には「卵の白身」を使用していること。
本物の接着剤だと剥がしにくいため、張り替えが必要になった際に卵白なら簡単に剥がせるというわけです。
【大東駿介さん】「僕ら当たり前に使わせてもらってるけど、1本が仕上がるまでにこれだけの職人技があるってことですからね」
大東さんも刀作りに挑戦させてもらいましたが、「めちゃくちゃええやんか」と感激していました。
京都・太秦には、日本映画の歴史と共に歩んできた職人技が今も息づいています。
これからも日本の映画文化を支え続ける、太秦の魅力を感じる旅でした。
(関西テレビ「newsランナー 大東駿介の発見!てくてく学」2025年9月11日放送)