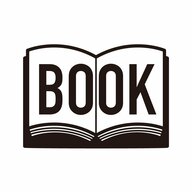羅臼町では、上水道事業1か所、簡易水道事業2か所で水の供給が行われています。今回の事故が発生した地域には、1967年に建設された簡易水道浄水場があり、これまでに一度も更新されていません。こうした老朽施設が、漏水を通じて地盤への影響を及ぼしていた可能性があります。
町の水道事業は、人口減少に伴う料金収入の減少にも直面しています。設備の更新を進めると事業収支が悪化してしまうため、老朽化の進行が止められないという悪循環に陥っているのです。
実際に、羅臼町の有収水量率は44.8%と、全国平均を大きく下回っています。これは、浄水場から送り出した水が100リットルだとすると、実際に家庭や事業所に届くのは44.8リットルで、残りの55.2リットルは漏水していることを意味します。
こうした災害リスクを軽減するには、漏水や水圧の異常を早期に検知するためのモニタリング技術の導入が不可欠です。
現在では、国内外の自治体で先進的なモニタリングシステムが導入され、事故の未然防止に成功している事例も増えています。
しかし、その導入や運用には財源と人材が必要です。異常を検知しても、すぐに対応できる体制が整っていなければ意味がありません。財政制約と技術者不足という二重の課題が、全国の自治体に重くのしかかっています。
羅臼町での土砂崩れは、老朽化した水道施設が引き起こす災害の「予兆」として受け止めるべきです。
これを教訓とし、各地の自治体は水道インフラの更新と点検体制の強化を急ぐ必要があります。とくに、山間部や斜面に施設を持つ自治体では、地質の特徴や気象条件とあわせて、よりきめ細かなリスク評価と予防策の導入が求められます。
気候変動の影響で、今後さらに豪雨災害が増えることも予想されています。もはや老朽化は「目に見えない水の問題」ではなく、人命と直結する危機です。羅臼町の事例を他人事とせず、いま行動することが問われています。
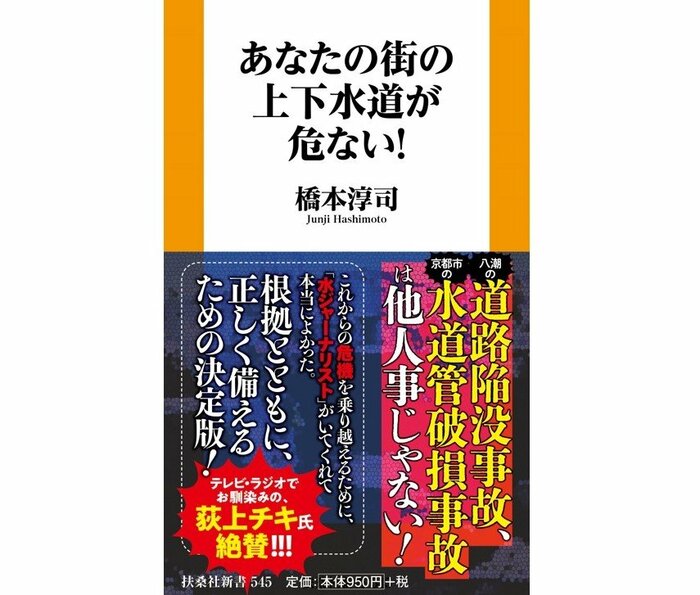
橋本淳司
1967年群馬県生まれ。アクアスフィア・水教育研究所代表、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。著書に『水辺のワンダー~世界を歩いて未来を考えた』(文研出版)、『水道民営化で水はどうなる』(岩波書店)、『67億人の水』(日本経済新聞出版社)、『日本の地下水が危ない』(幻冬舎新書)、『100年後の水を守る~水ジャーナリストの20年』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など多数