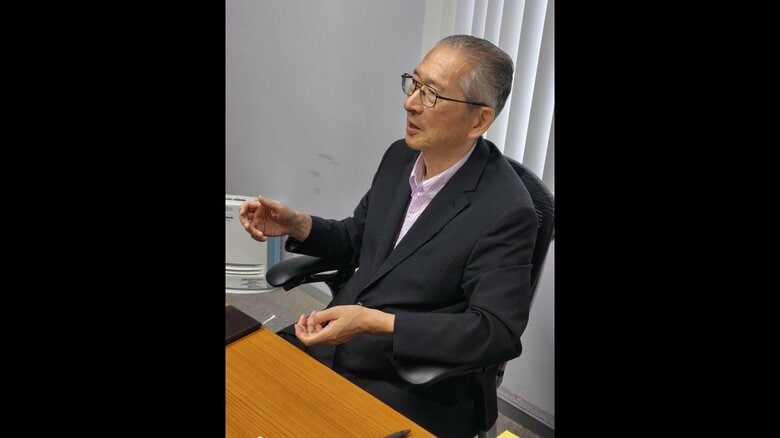7月の参院選をめぐり、立憲民主党と国民民主党の支援組織である「連合」が取りまとめた総括案が判明した。この中では、立憲・国民民主両党の候補者一本化を評価し、与党の過半数割れは「まさに連合の組織力によるもの」とする一方、立憲民主党に対し、「党存続の危機」と指摘し、早急な対応を求めている。今後の立憲民主党の課題、石破政権との向き合い方、参政党の躍進などについて、連合前会長に迫った。
「消費税減税は天下の愚策」 石破内閣不信任案「政権構想もなく出すのは無責任」
「消費税の減税は天下の愚策だ。連合の方針とも乖離(かいり)する。立憲民主党も国民民主党も参院選で掲げるべきではなかった。将来世代のことを考えると無責任だ」
FNNの単独取材に対し、厳しくこう指摘するのは、労働組合の中央組織「連合」前会長の神津里季生氏だ。神津氏は、連合会長を2015年10月から3期6年間にわたって務めた。2017年には連合が支持していた民進党(旧民主党)が希望の党との合流騒動を経て、立憲民主党と国民民主党への分裂に至る過程も支援組織のトップとして経験している。
まず参院選で大敗した石破首相に対し、自民党内から公然と辞任を求める声が出ていることについて尋ねると、神津氏は次のような見方を示した。
「今を乗り越えることができれば、それなりに長く政権運営できる可能性はある。政策合意を目に見える形で実現し、その成果を国民に分かりやすく示すことができれば、支持率が上がっていく可能性もあるのではないか」
野党内では、石破内閣に対する不信任決議案の扱いが焦点となってきたが、提出をめぐっては温度差が浮き彫りとなっている。
臨時国会が召集された8月1日、立憲民主党の野田代表は記者会見で、次のように語った。
「対決姿勢は別に秋だってよい。総括をした上で戦う準備をして、しっかり戦って勝ちに行くことが大事だ」
臨時国会での内閣不信任案提出見送りを示唆する発言に、国民民主党の玉木代表は記者団に対し、「何で今ではなくて秋なのか。そこがよく分からない」と疑問を呈し、次のように述べた。
「選挙前の通常国会の時にも出さないという判断、今回も出さないということで、なぜ秋なら出せて今なら出せないのか。有権者の皆さんに納得できる説明が必要ではないか」
これに対し、取材の中で神津氏は、内閣不信任案を提出する場合には、その後の政権構想も合わせて提示すべきだとの考えを次のように示した。
「ただ引きずり下ろすだけだったら意味がない。安定的な政権構想があれば出すことも視野に入れられるが、それがなくて出すのは無責任だ。出した後の政権構想もなく出すのは烏合の衆のやることだ」
「落ち着いた政治をやってほしい」 立憲に足りないもの「政策はよいが伝え方が…」
参院選で国民民主党や参政党が躍進する中、立憲民主党は改選前と同じ22議席にとどまり、比例代表では約739万票の得票だった。前回3年前の参院選と比較すると、約62万票増やしたものの、2024年の衆院選と比べると400万票以上減らし、自民党、国民民主党、参政党の後塵を拝した。
こうした結果について、連合の総括案では、「衆参両院での与党過半数割れを達成できたことは大きな成果であり、まさに連合の組織力によるもの」と強調。
立憲・国民民主両党が全国32ある1人区で候補者の一本化を進めた結果、野党が自民党に勝ち越したことについて、「連合・立憲民主党・国民民主党が力を合わせれば結果を出せることが証明された」としている。
一方、立憲民主党については、「全国的にも党勢に欠け、接戦区での新人の競り負けや比例票数が新興政党の後塵を拝したことなどは、立憲民主党が与党に対峙するもう1つの選択肢になり得なかったことを意味している」と厳しい評価を下し、次のように求めている。
「立憲民主党は党存続の危機であるとの認識のもと、今回の結果と野党第一党としての責任を重く受け止め、早急に対応をはかる必要がある」
取材の中で、神津氏に立憲民主党に足りないものは何かを尋ねると、30秒近い沈黙の後、言葉を選びながら次のような見方を示した。
「一言で言い表せないが、持っている政策はよいと思う。世の中に立憲民主党の政策のよさをどれだけ分かりやすく伝えていけるかだ」
参院選の結果を受けて、立憲内では執行部の刷新を求める声も出ている。これに対し、神津氏は、「変な責任論で人事をやるべきではない」とした上で、次のように続けた。
「落ち着いた政治をやってもらいたい。そしてそれをどのように世の中に伝えていくか。そうすればチャンスがあるのではないか」
連合の総括案では、「国民民主党や参政党がSNSを組織的に駆使し、効果・訴求力を発揮していた一方、立憲民主党の場合、関係者の努力は多としつつ相対的に遅れをとった印象が否めない」と指摘しているが、神津氏も、「例えば、SNS対策を強化し、時間と権限を与えるべきではないか。せっかくよいことをやっていても、それが世の中に見えなかったら意味をなさない」と語った。
「政策本位で与野党協議重ねるべき」 参政党「議論に耐えうる政党か問われる」
参院選の投開票から2日後、連合の芳野会長は記者会見で、立憲民主党や国民民主党が与党と連立政権を組むことについて、「あり得ない。緊張感ある政治体制が確立できなくなる」と、否定的な考えを示した。
これについて、神津氏に尋ねると、「連立に入ることが落ち着いた政治において不可欠であれば否定はしない。しかし、必ずしもそうとは言えない状況ではないか」と強調した。その上で、「まずは政策本位で与野党協議を重ねていくべきだ」との考えを示した。
立憲民主党は、先の衆院選で少数与党に追い込んだことを受け、「熟議と公開の国会」を掲げ、国会審議を活性化させ、政策活動費の廃止や補正予算の修正など一定の成果を上げた。
一方で、企業・団体献金の禁止や選択的夫婦別姓制度の導入など懸案とされてきたテーマについては、与党との意見の隔たりは埋まらず、実現には至っていない。こうした状況を踏まえ、神津氏は次のように求めた。
「為にする議論ではなく、税制、社会保障、そういったものを全部俎上に載せて、大きな画を作っていく議論をしてほしい。しばらくはそれをやれる環境だと思う。そして、与野党協議は密室ではなく、できるだけオープンにすべきだ。そうすると政党の立ち位置も明確になる」
さらに、話題は参院選で躍進した参政党にも及んだ。連合の総括案では、参政党の躍進について、「疑問視する向きも多いが、単に風やSNSだけで議席を伸ばしたわけではない。地道に党員を増やし、各地で参加型の活動を進めるなど、党の土台づくりに力を入れてきたうえでの党勢拡大であり、立憲民主党も国民民主党もその点は見習う必要があるのではないか」と指摘している。
神津氏はこうした見方について、「所属する地方議員が結構いる。そう簡単に熱が冷めるものではないと思う」と同調した上で、次のように訴えた。
「日本人ファーストというキャッチフレーズを掲げていたが、与野党協議を重ねれば、参政党が政策議論に耐えうる政党なのか、本当の意味での地力が問われる」
FNNが23・24両日に実施した世論調査では、政党支持率で立憲民主党が5.2%、国民民主党が9.3%だったのに対し、参政党は9.9%で、初めて野党トップに立った。
政権交代を目指す立憲民主党が国民からの支持を取り戻せるか、躍進した参政党が政策議論に耐えうる政党として支持を広げるか、今後の与野党協議の行方に注目が集まりそうだ。
(フジテレビ政治部 野党担当キャップ 木村大久)