これまでに発見された麻酔薬の化学構造式を調べても、これといった共通点がなく、作用メカニズムを深掘りする手がかりがありません。科学の作法に則った合理的な新薬開発ができないのです。
麻酔が人間の本質に迫る!?
そんな麻酔薬が、いま別の観点から注目され始めています。人間の本質に迫るツールになる可能性があるというのです。
オックスフォード大学のルッピ博士は2024年4月、「ネイチャー人間行動」誌へのコメントで「麻酔薬は意識の解明に役立つかもしれない」と述べています(※)。
「麻酔」という単語は「感覚が麻痺して酩酊に似た状態になる」という意味から生まれたのでしょう。その通り。麻酔薬を投与すると意識が消えます。

意識障害の患者の脳の状態は、麻酔状態とそっくりです。つまり、麻酔の作用点を探究してゆけば、意識の謎に迫ることができる可能性があるのです。
意識は、誰もがそれとわかる身近な現象ですが、脳科学的には難物で、ほとんど解明されていません。脳研究の最後の謎になるかもしれないとも言われています。
こうした暗中模索の中で、麻酔は研究者に示された数少ない糸口なのです。だからこそ、なおのこと、麻酔薬の作用メカニズムがわからないことがもどかしいのです。
医学は進歩します。10年後に、まったく新しい作用機序を持った麻酔薬が新規開発されている可能性もあります。「意識」の実態が解明される日が来るかもしれません。
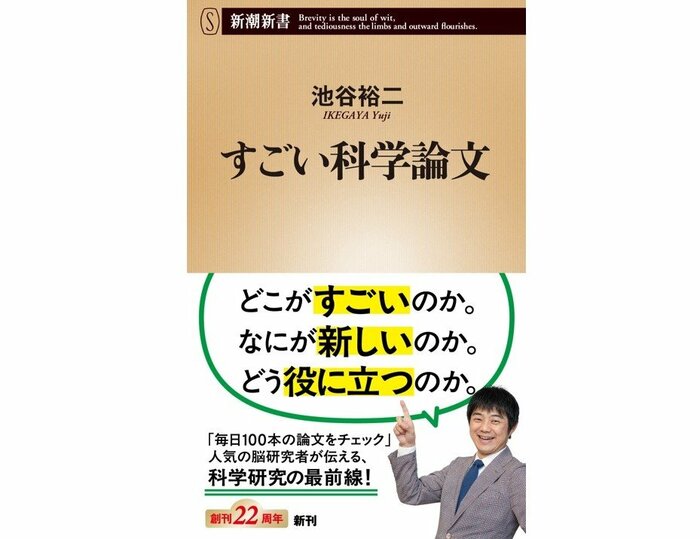
池谷裕二
1970年静岡県生まれ。薬学博士。東京大学薬学部教授。脳研究者。2024年、『夢を叶えるために脳はある』で第二十三回小林秀雄賞を受賞。著書に『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』『脳はなにかと言い訳する』『パパは脳研究者』『生成AIと脳』など。
(※)Luppi, A. I. What anaesthesia reveals about human brains and consciousness. Nat. Hum. Behav. 8, 801–804 (2024).






