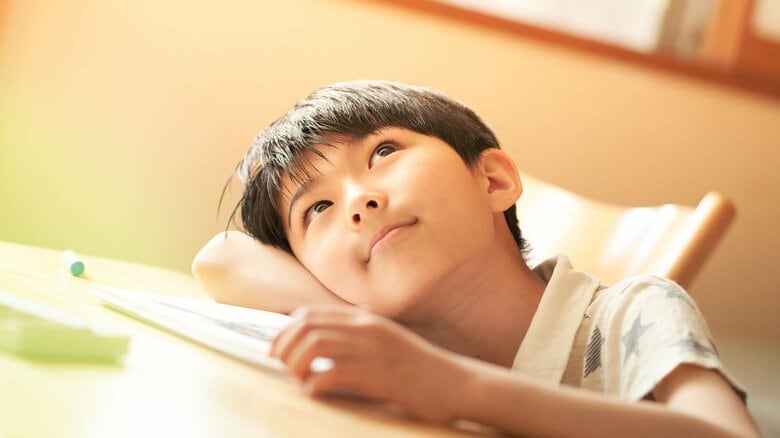「声かけ」一つで子どもの学ぶ意欲や積極性が育まれ、親自身のマインドも変わっていくという。
そのためには家の中で子どもが「ひとりで夢中になれる場所」も必要だとのこと。
二児の父親でもあるベネッセ教育総合研究所・主席研究員の庄子寛之さんの著書『子ども教育のプロが教える 自分で考えて学ぶ子に育つ声かけの正解』(ダイヤモンド社)では、自分で考えて学ぶ子になるための5つの声かけを取り上げている。
親の目の届かないところにいると不安が募るばかりだが、そんなときこそ子どもとどんな会話をするかが大事になる。なぜ、「ひとりで夢中になれる場所」が必要か、一部抜粋・再編集して紹介する。
早ければいいというわけではない
親の見えないところで何をしているか、気になります
→ひとりで夢中になれる場所を認める
「何が正解かわからないから、早めにやらせてみる」
一見、よさそうに見えますが、一番いけないやり方です。
「将来役に立つかもしれない」という思いから、早期教育に熱心な家庭が増えています。気持ちはよくわかりますが、よくありません。
3歳の子をもつ親なら、「親3年目」。初めて親になったのですから、わからないことだらけです。不安を抱える中で聞こえてくる、「早く運動経験をさせたほうがいい」「中学受験をすると、将来安泰」などの危機感を煽る言葉に反応してしまいます。

首都圏模試センターによると、2024年の首都圏私立・国立中学校の受験者総数は過去2番目の5万2400名で、受験率は18.12%と過去最高になりました。
首都圏では5人にひとりは中学受験をしています。小さいうちから、子どもにとってよりよい教育を受けさせたいという親の思いがわかります。
教員時代、クラスで習い事を一つもしていない子は、ほとんどいませんでした。今や、「運動」と「勉強」の習い事を掛け持ちしている家庭が当たり前です。
子どもによりよい人生を歩んでほしいという思いより、「親としてちゃんと育てているように見えたい」「周りの家がしていることをしないと不安」が大きいのではないでしょうか。
子どもから、「こんな習い事がしたい」「こんなところに行きたい」と言ってくる環境を整え、すぐやらせてあげられる準備をしておくことです。